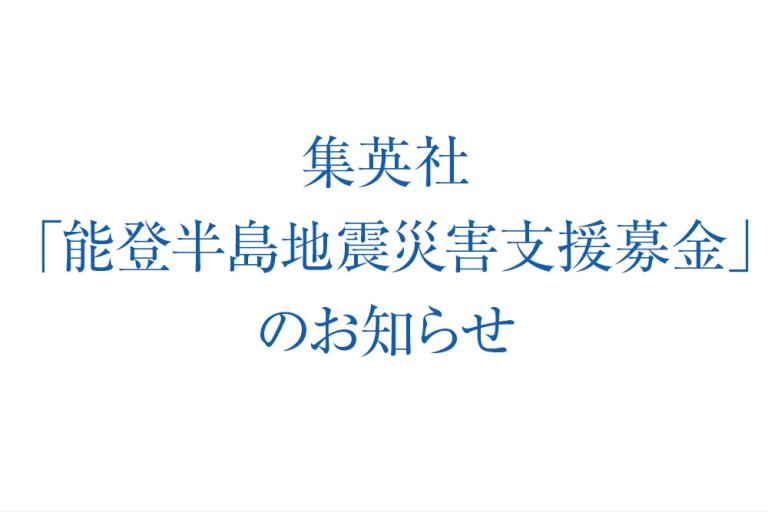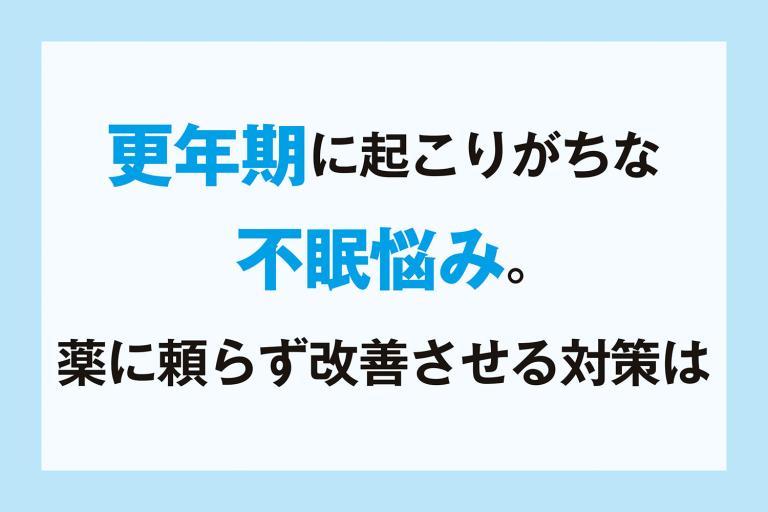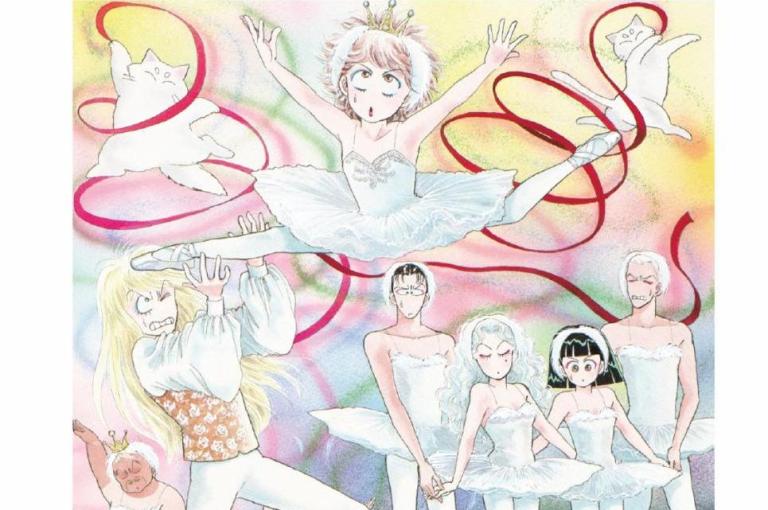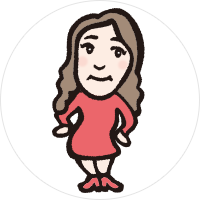大腸肛門科&婦人科のドクター直伝
このやり方で便秘をすっきり解消!
便秘をこじらせると20年後に骨盤底筋疾患を招く心配も。日頃の生活習慣を見直して、自分に合う便秘解消法を見つけましょう。
教えてくれたのは…
山名哲郎さん Tetsuo Yamana
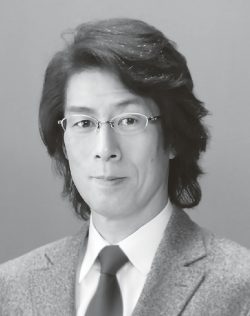
秋田大学医学部卒業。JCHO東京山手メディカルセンター大腸肛門病センター部長。日本大腸肛門病学会専門医、指導医。便秘などの排便障害、痔疾患、骨盤底疾患(直腸瘤・直腸脱)、大腸がんなどの診断・治療に取り組み、直腸瘤には後腟壁形成術、直腸脱には腹腔鏡下直腸固定術を行う。おもな著書に『スーパー便秘に克つ!』(文藝春秋)など
松峯寿美さん Hisami Matsumine

東京女子医科大学卒業。東峯婦人クリニック名誉院長。日本産婦人科学会専門医。女性専門外来の先駆けとして、妊娠・出産、更年期、老年期まで、婦人科系QOLを保つ医療を実践。骨盤底筋トラブルの治療や子宮脱を改善する経腟手術を行う。おもな著書に『50歳からの婦人科 こころとからだのセルフケア』 (高橋書店)など
朝1杯の水&朝食で腸を目覚めさせる
朝1杯の水を飲むなど、飲み物や食べ物が胃に入ると、胃が結腸(大腸の上の部分)に指令を出し、消化管が動き出します。「 この〝胃結腸反射〞を毎朝のルーティンにすると、条件反射で便意を感じやすくなるので、おすすめです。なぜ、朝がいいかというと、就寝中は副交感神経が優位なので、起床後に水分や朝食をとることで、胃腸を目覚めさせることができるからです」(松峯先生)
特に朝は大腸のぜん動運動が起こりやすい時間帯。朝食を抜くと、せっかくのぜん動運動が起こらず、それが便秘のきっかけになることも。排便リズムを習慣づけるためにも、毎朝決まった時間に朝食をとり、食後のトイレを日課にしましょう。
食物繊維をしっかりとる
食物繊維は便の材料のおおもと。便のかさを増やして、腸のぜん動運動を活発にする働きがあります。また、水分を含む性質があり、便を軟らかくしてくれるので、積極的にとってほしいと思います」(山名先生)
食物繊維には、海藻や果物などに含まれる水溶性食物繊維と、きのこ、野菜、いも類、大豆食品、穀類に含まれる不溶性食物繊維の2タイプがあります。これらをバランスよくとるためにも、ご飯を主食にした和食がおすすめ。ちなみに、成人女性は1日に17~18gの食物繊維をとるのが望ましい(厚生労働省の食事摂取基準)とされます。「日本人の平均的な摂取量は11~12gと少なめなので、食物繊維のサプリメントで不足分を補ってもいいでしょう」(山名先生)
イラスト/内藤しなこ 取材・原文/大石久恵