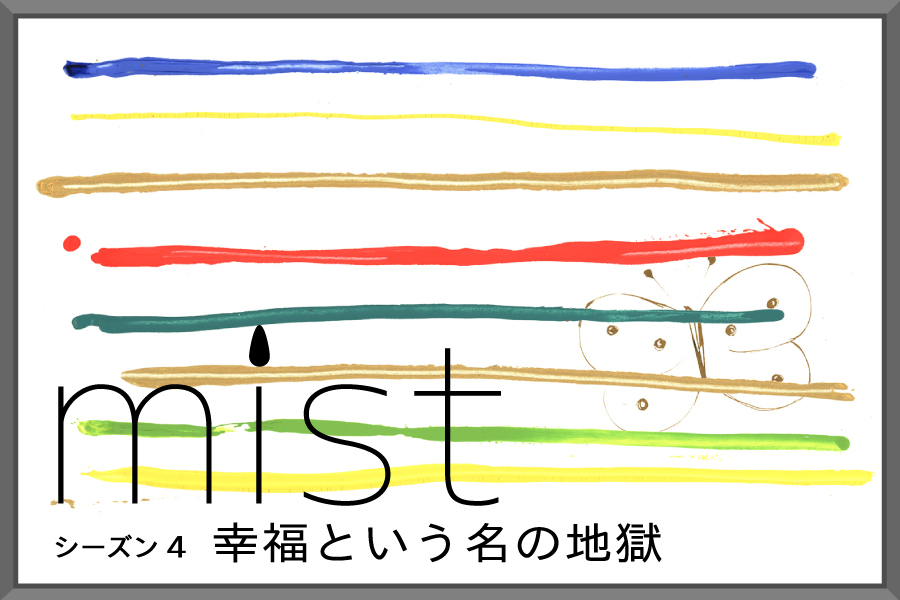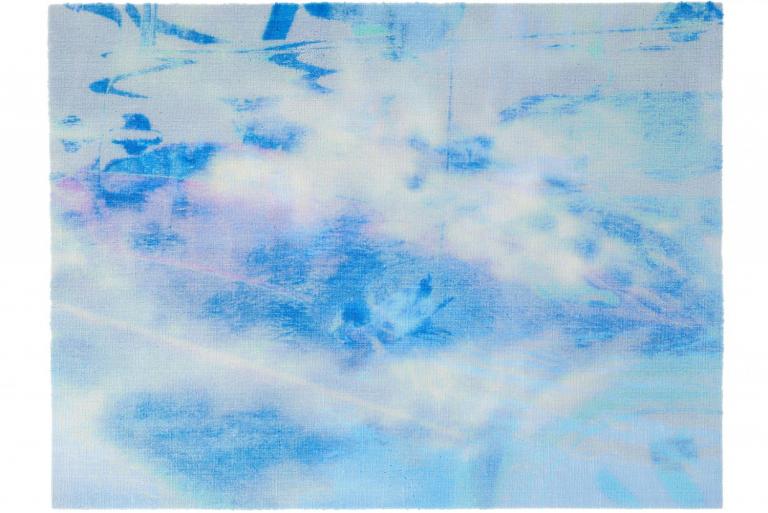第1話 もう、うんざり
本当にもう、うんざりだった。このまま消えていなくなりたい・・・。
そう、貴美子は思った。延長された四度目の緊急事態宣言がやっと解除されても、夫のリモートワークは続いていた。
世の中の大人女子はそろりそろりと動き始めているのに、貴美子は気持ちの切り替えがまだできていなかった。親友の瞳とも相変わらず、ドライブスルーでお裾分けなどするだけの付き合いしかできていない。
いまだ家族とだけだ。後期高齢者となった母と、夫、そして、たまに帰って来る息子。コロナ禍で社会人になった息子は、彼女でもできたのか自分の部屋を借り、滅多に帰ってこなくなった。
夫の誕生日には珍しく帰って来て、気の利いた酒をプレゼントしていた。たぶん彼女が選んだものだろう。その夜は夫と楽しそうに酒を酌み交わしていた。酒を飲まない貴美子は、なんだか疎外感を感じて散歩に出た。
11月になり、朝晩はだいぶ冷え込むようになった。
「さぶっ」
北風がぴゅううっと吹いた。薄いスパッツにスカートでは、もう足腰が冷えてくる。そろそろ腹巻しなきゃだな・・・。だいぶ毛量も減ったから、北風が吹くと頭も寒い。貴美子はダウンジャケットのフードをかぶり、紐をきゅっと引っ張った。
若い頃なら冬場に頭が寒いなんて、感じたことはなかったのにと、貴美子は自分の加齢をわびしく思った。
それでも貴美子は久しぶりに、深く息を吸えることに気づく。
一人はなんて、気持ちがいいんだろう・・・。
ワクチン接種も二回目を終え、いま二週間目で一番抗体ができてる時期だ。副反応も倦怠感ぐらいであまりなかった。本来ならこの辺で、お出かけをしたいところなのだが。自粛生活が長かったためか、もうお洒落をして出かけるのが億劫になっていた。
今日も一日家にいたから、少しは歩かねばと思い、氏神様まで歩いた。
東京郊外の町は閑散としていた。逆に緊急事態宣言下の方が、近所に人が多かったぐらいだ。それでも境内に入ると、貴美子は少し、気分がよくなった。
人気のない本殿に手を合わせる。
「コロナがこのままなくなりますように。第六波など来ませんように」
貴美子は深々と頭を下げた。
四度目の緊急事態宣言で、東京都は酒類の提供が一切禁止となった。夏は、近隣住民のバーベキューが増えた。お盆休みには人が集まり、庭先やベランダで盛り上がっていた。
「屋外ならいいってもんじゃないよね。あんなに人呼んで盛り上がったら、飛沫感染するじゃん」
貴美子は夫に愚痴った。
「だよな。親戚も友達も呼ばず、うちは家族だけ」
夫は嬉しそうに言った。そもそも、家族が大好きで友達があまりいない夫は、むしろ家族だけで過ごせる自粛生活に幸せを感じているようだった。それが、貴美子の癪に障った。
記事が続きます
夫は役場勤めの公務員だからか、四角四面で面白味がない。もっと面白い人だったら、家族でだけ過ごす自粛生活だって、楽しかったに違いない。でも、女性とほとんど付き合ったことのない真面目な男だから、何十年連れ添う貴美子とすら、何を話していいか分からないようなのだ。
それなのにコロナ禍、休みの日には必ず、スーパーにまでついて来るようになった。暇なのは分かるが、お父さんがついて来る家が多く、店内がそれこそ密になってしまう。
緊急事態宣言になるたび、近所のスーパーに「代表者一名でお願いします」と貼り紙が貼られた。
東京都の感染者数が五千人を超えたころ、貴美子は、これじゃあスーパーで罹患してしまうと、不安になった。
車でたった五分のスーパーに、夫はまるで貴美子が運転できないかのように、嬉々として車を出した。家では出来る限りソーシャルディスタンスを取っているから、狭い車内に、しかも隣に並んでいるのが、夫は嬉しそうなのだ。
「いやもう、退屈過ぎて息が詰まるんだよ。一緒に車乗ってるとさ、ホントに呼吸困難になりそう。しかも土日スーパー混んでるから、駐車場待たされたりしてさ」
と瞳にライン電話で愚痴ると、
「家族がいるだけいいじゃん」
と決まって言われる。公務員だからコロナ不況でも生活は安定していて、それが瞳には「羨ましい存在」だというのだ。
独身で、派遣で働く瞳には、貴美子の安定した生活は羨ましいかもしれない。
が、コロナ禍になってからというもの、貴美子にはそれが、どうにも幸せとは思えなくなっていた。
なにしろ、金太郎飴みたいに、切っても切っても同じ顏。もう、家族の顏なんか、見たくもなかった。
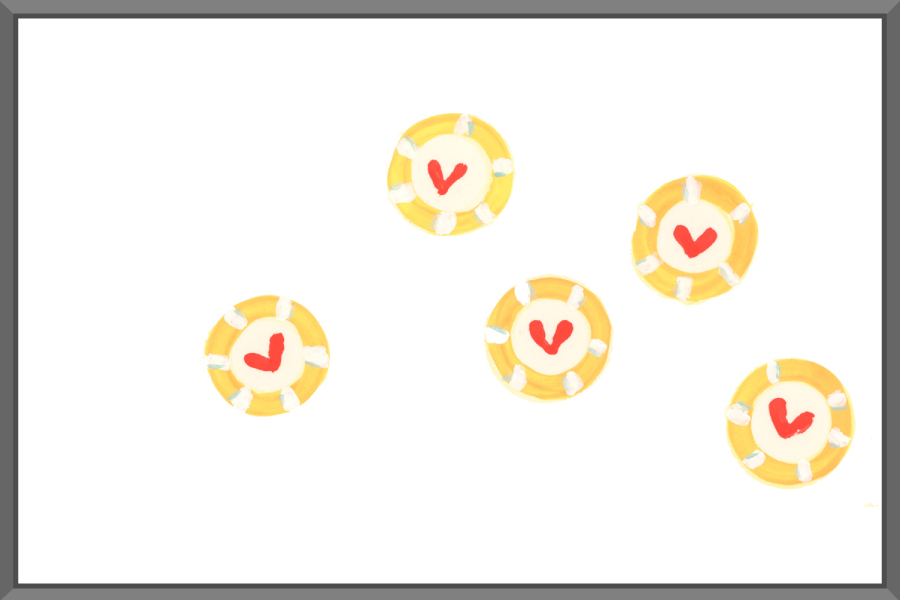
イラスト/押金美和
◆mist シーズン1、2、3のこれまでのお話は、こちらでお読みいただけます。
◆次回は、11月4日(木)公開予定です。お楽しみに。