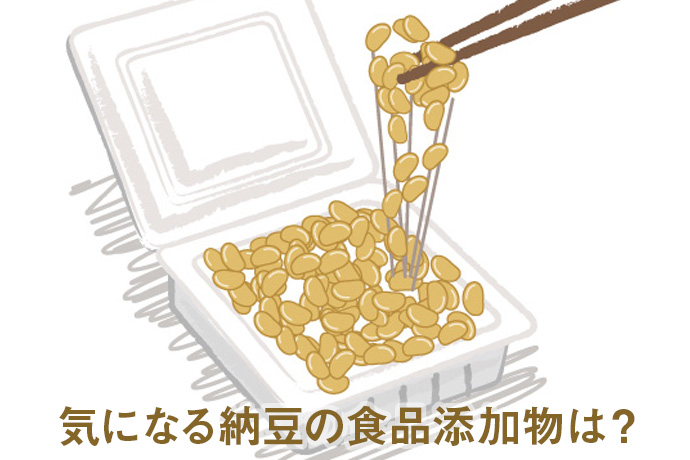ローズのようなフローラルなアロマの白ワインに出会い、手掛けたのは誰? と頭から離れなかったワイン「ぎんの雫」。
 ワイン持ち寄りのホームパーティで出会ったそれは日本酒の清々しさも兼ね備えていてお刺身や和食にピッタリだったことを憶えています。
ワイン持ち寄りのホームパーティで出会ったそれは日本酒の清々しさも兼ね備えていてお刺身や和食にピッタリだったことを憶えています。

聞けば、シャトー・ムートンやオーパス・ワンを手掛けた世界にその名を知られるフランス人醸造家、パスカル・マーティ氏が7年の構想を経てつくりあげたワインでした。
想いが強いと(笑)願いが通ずるのか、マーティ氏に直接お話しを伺うことができました。

白ワインの魅力であるアロマは、できる限り低温で発酵を行うことでその効果や魅力を高めることができるのですが、その下限温度は12℃程度というのが定説でした。
パスカル・マーティ氏は「10℃以下の低温下で完璧なワイン醸造のプロセスを進めることができれば、その白ワインは画期的なものになる」と考えました。
しかしながら、低温発酵に適応した酵母がなく、アルコール度がワインとして一般的な水準に達しなかったりでなかなか満足のいく結果が得られなかったそうです。
そんな中、マーティ氏は日本酒に出会い、日本酒作りが発酵温度は5℃以下で進む段階があることを知り、漠然と思い描いていた低温発酵ワインが一気に現実化していきました。
日本でのある出会いが大きかったと言います。
その出会いとは⁈

「獺祭」の生みの親、旭酒造 櫻井博志氏と日本醸造協会でした。
日本酒の7号酵母を用いて2~3度温度を下げ発酵させていきます。
発酵が終わるまで約40日ほどかかるのだそうです。通常ワインの発酵が2週間ほどと考えると長く発酵することで酵母の影響が大きく表れ、奥行きのある味のワインになる理由が分かります。
長い時間をかけてゆっくりと発酵が進むのでその間に酵母の世代交代が何度も起こり大量の澱が発生する。この発酵過程で起きる対流により、澱が絶えずタンク内を回遊するので自然なバトナージュを行なっているかのような効果が表れ、ワインの豊かな風味に繋がっているのだそう。
 清酒7号酵母を用いてチリで生まれた超低温発酵白ワイン「ぎんの雫」は日本の伝統とフランスの文化とチリのテロワールの結晶。
清酒7号酵母を用いてチリで生まれた超低温発酵白ワイン「ぎんの雫」は日本の伝統とフランスの文化とチリのテロワールの結晶。
「ぎんの雫」というネーミングとラベルのデザインは「神の雫」原作者 亜樹直氏が書き下ろし、それぞれの国の叡智の結晶でもあります。

携わった方の並々ならぬ熱い想いが感じられます。
ワインのミネラル感がシーフードにピッタリです。

この1月から六本木のフレンチビストロ「ル・プティ・マルシェ」にて日本初のワインテイスターとして活躍する大越基裕氏監修のマリアージュコースが提供されているので「ぎんの雫」をピッタリな料理とともに堪能してみては。