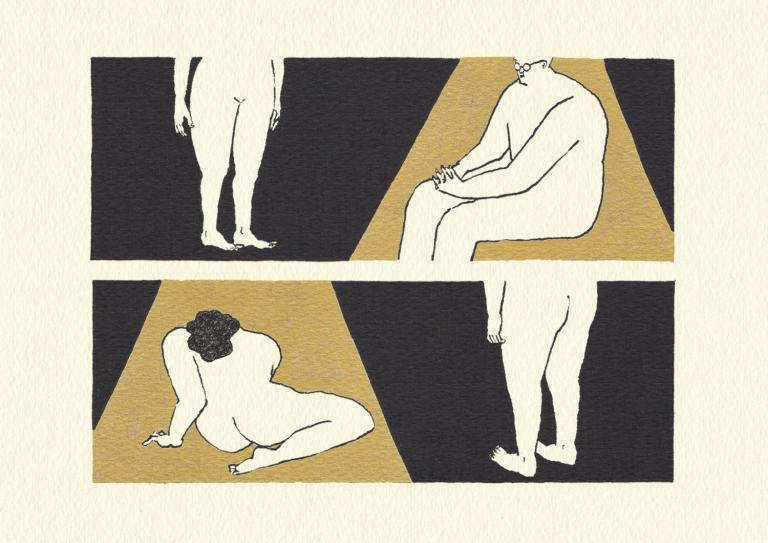第7話 理想のパートナー
「お昼できましたよー」
「はーい」
美穂はスマホをデスクに置き、リビングに急いだ。いい匂いが漂って来る。
なんだろうこの幸福感・・・。
テーブルには見たこともないランチョンマットが敷かれ、タイ料理店さながらのガパオライスが、アイスミントティとともに置かれていた。
「すごい!! レストランみたい」
「エスニック料理は得意なんです。
タイ、ベトナム、韓国、中国、モロッコ料理もできますよ」
「ええー、マジですか?」
「さあ、いただきましょう」
なんなんだ、菅野君、お袋さんかよ? 美穂は泣きそうになりながら、菅野君お手製ガパオライスを食べた。
「美味しい・・・」
それは店で食べるものよりずっと優しく、体に良さそうな味だった。
「するするいけちゃう」
止まらなくなってパクパク食べる美穂を、菅野君は微笑みながら眺め、自分も食べた。
家の中でもソーシャルディスタンスを取ってくれているから、菅野君はキッチンカウンター、美穂はリビングのテーブルだ。
「ふわー、美味しかったぁ! ご馳走様」
美穂が一気食いして食器をキッチンに持って行くと、
「あ、置いといてください。僕が洗います」
と言う。
「え、でも作っていただいたんだから、洗い物は私が・・・」
「すみません、最後までやり遂げたい性格なんです」
見ると、それまで汚かったシンクは、知らないうちにぴかぴかに磨き上げられている。い、いつのまに・・・。
菅野君は感染予防対策もしっかりしてくれていた。
「ここは伊藤さんの家なので、私がマスクをしますね」
と言い、自室で仕事をしている時以外は、マスクをしてくれていた。
調理の際も、手洗い手指消毒を徹底して、使い捨ての手袋までしている。
「ええー、そんなのいいですよ。そこまで気を使っていただかなくても・・・」
と、美穂が恐縮すると、
「いえ、私は間借り人ですから、気は使わせていただきます」
菅野君はニッコリと言うのだった。
こんな人材が、独身で五十まで残っていたとは・・・。美穂は不思議に思った。もしかしてゲイ? でも、そしたら男と同居したいだろうに。バツイチの冴えない女と同居しても、いいことなんかなんにもない。
現にこうやって、世話することになっているじゃないか。でも・・・。
もし菅野君がストレートで、美穂と結婚、いや、そこまでいかなくても友達以上の関係になってくれたら、まさに理想のパートナーではないか。美穂は思った。まずは、ゲイかストレートか、確認する必要がある。
生春巻き、キムチ豆腐、回鍋肉、鶏肉のモロッコ風スープクスクス添えと、菅野君の手料理は完全に美穂の胃袋をつかんでいた。梅雨の半ばにふわっと暑くなった日には、今年初めての冷やし中華も作ってくれた。
「本当に、美味しすぎてありがたいんですが、毎食毎食、申し訳なさすぎます」
と言うと、
「いえ、料理や掃除はいい気分転換になりますから」
とニコニコしている。いったいその機嫌の良さは、どこから来ているのか。
それは、もしかしたらこの食事からかもしれなかった。
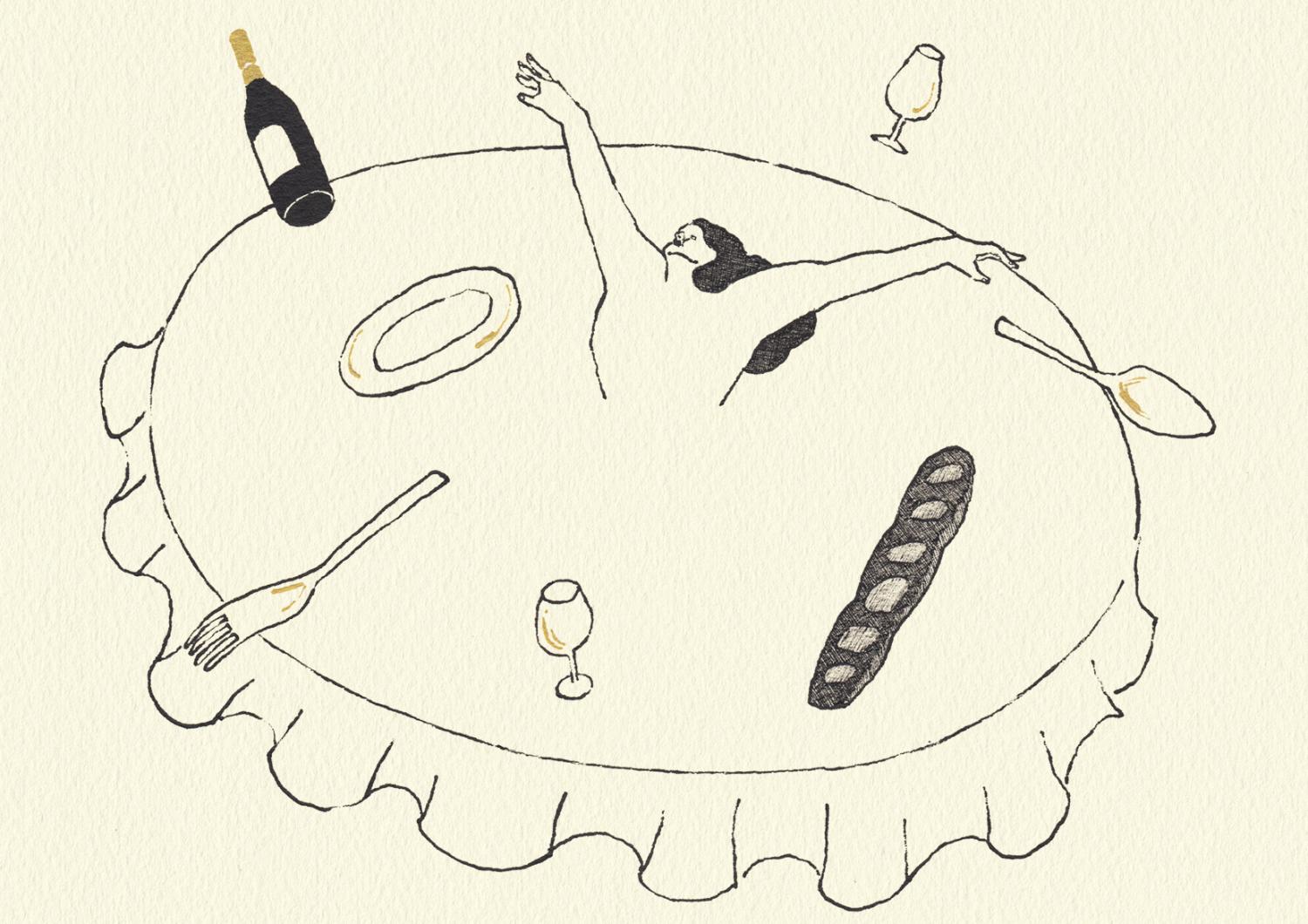
イラスト/ナガノチサト
美穂はいつしか、昼から呑むのをやめていた。
ランチは菅野君が食事に合わせたソフトドリンクを添えてくれるし、終業後は美味しいつまみを作って、それに合うお酒を出してくれるから、深酒をすることもなくなった。
菅野君は酒の飲み方がきれいで、食事とのマリアージュを楽しむだけ。つまり、一、二杯が限度だった。食後はまた温かいお茶を出してくれるので、そのままだらだらと酒も飲めなくなった。
「ほら、今日のデザートは水まんじゅうですよ」
「きゃー♡」
すっかり餌付けされ、懐く美穂だったが、今度は、やがてリモートワークが終わり、菅野君が出て行ってしまう日が来るのが、怖くなってきた。そしたらまた、独りぼっちになってしまうのかと。
記事が続きます
七夕の日、美穂は思い切って、菅野君を誘った。
「あの、良かったら今夜、スパークリング開けませんか?」
美穂は冷蔵庫で冷やしてあった、久しぶりにディンデリで買った七夕用のスパークリングワインを取りだして、見せた。
「いいですねぇ。じゃ僕も泡に合うつまみ、作りますよ」
美穂が仕事を終え自室から出ると、テーブルには既に、オードブルが並べられていた。生ハムメロンは、角切りのメロンが生ハムで包んである。
トマトとモッツァレラチーズのサラダ、ガーリックトースト、チーズはパルメジャーノレジャーノが、薄くスライスしてあった。
「すごい、魔法みたい・・・」
いつの間に買い出しに行ったのか。
スパークリングワインはすでに、ワインクーラーに入っている。ワインクーラーなんて、何年ぶりに使っただろうか。
「あ、すみません、戸棚の奥から取り出して、勝手に使っちゃいました」
「いえいえ、すごい埃被ってたでしょう?」
菅野君は苦笑している。中にはレジ袋が詰まっていたはずだ。世の中エコバッグ時代だから、何年も前の・・・。
「では、開けましょうか」
白いふきんをクロス代わりに使って、菅野君はソムリエよろしく、スパークリングを開けた。シャンパングラスもぴかぴかに磨かれている。
バカラのペアグラスの片割れを美穂用に、もう一つはブーブクリコのセットについていたのを、菅野君は自分用に用意していた。違いの分かる、そして常に低姿勢の男だった。
「乾杯」
「乾杯」
緊急事態宣言は延長につぐ延長、六月末にやっと解除となった。
とはいえリモートワークは続き、社は今後も出社七割削減を続ける方針だ。自宅軟禁生活も慣れてしまい、こうやって誰かとグラスを合わせること自体が、夢のようだった。
「ああ、美味しい」
酒を味わって飲んだのは、久しぶりだった。いつも、酔うために飲む。
そんな生活で、心身ボロボロになっていた美穂は、お母さんのような菅野君に、自分自身を繕ってもらっていた。
「うん、マスカテルな、美味しい泡ですね」
「こんな丁寧な生ハムメロンも初めてですよ。美味しい」
「あ、それね、母のやり方なんですよ。子供の時から、食べやすいように皮をとって、巻いてくれたんです」
「子どもの時から生ハムメロンって、菅野君お坊ちゃまなんですねー」
「いや、酒飲みの両親のもと、つまみで育っただけです」
菅野君の作った美味しいオードブルをパクパクつまみながら、美穂はスパークリングをどんどん飲んでしまった。誰かに注いでもらう酒は、こんなにも美味しいものか。酔っぱらって来ると、ついに本音が出た。
「もう、ソーシャルディスタンスはいいです。こっちに来てください」
そう言って、自分の座るソファの隣を、パンパンと叩いた。
「いやでも、PCR検査もしてないですから・・・」
と菅野君は言ったが、美穂も譲らなかった。
「私だってしてないですから、お互い様です」
すがるような目に、情にほだされた菅野君は、
「わかりました。じゃ」
と言って、マスクをして隣に座った。一メートルほど離れて。
「え、マスクしたまま、どうやって飲むの?」
美穂が聞くと、菅野君は、
「僕はもう充分いただきましたから」
と言う。見るとボトルは空だった。
「あー、ごめんなさい。私ばっかり飲んじゃって・・・」
と美穂が言うと、
「いえ、お酒はあまり飲めないんです」
と言う。
「実は僕、病気なんですよ」
「え」
美穂は急に酔いが醒める思いだった。