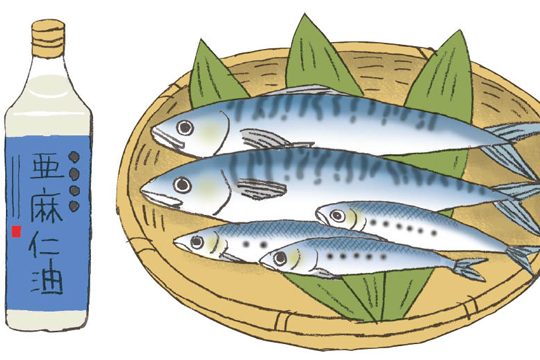終末医療を支えてきた看護師から、がんを告白され、託されたミッション
今回紹介する佐々涼子さんの最新作、『エンド・オブ・ライフ』は、2013年と2018年の、2つの時空間を行き来して書かれています。
著者の佐々さんは、2013年から、在宅看護の取材を始め、患者の立場に立つ医療を続ける京都の診療所を訪れていました。そこで見た終末医療のありようは、前編でもご紹介したように、「死」というものの概念が変わるほど、豊かなものでした。
しかし、その取材をまとめあぐねていた佐々さん。彼女をこのテーマに呼び戻したのは、2018年に受けた一本の電話。ほかでもない、在宅診療の取材先だった京都の渡辺西加茂診療所のスタッフからでした。

佐々涼子(ささりょうこ) 神奈川県出身。早稲田大学法学部卒業後、結婚して2人の男の子を出産。日本語教師を経てフリーライターに。2012年『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』(集英社)で、第10回開高健ノンフィクション賞受賞。著書は『紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている』(ハヤカワ文庫NF)など
「その日、診療所の看護師で私が個人的にも親しくなっていた森山さんが、すい臓がんだと知らされました。すくに京都に向かうと、森山さんから、がんは進行していてステージⅣであること、さらに共同執筆で在宅医療の実践を本にしないかと言われて……。正直戸惑いました。私も体調を崩した後で、執筆もしばらく途絶えていましたから。」
がんのステージⅣとは、がんが遠隔転移している段階のことです。
佐々さんは、これまで著書『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』や、東日本大震災後の印刷所の復活を描いた『紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている』で、命の問題や死のテーマを多く扱ってきました。
在宅医療の取材を始めてからも、やはり在宅で闘病を続けていた佐々さん自身のお母様の死という辛いできごともありました。執筆の辛さも重なり身体のバランスを崩して、そのリカバリーにインドやタイの仏教施設に出かけた経験もあったそうです。
そしてまた、近しい人の死にゆく姿に直面することに…。戸惑ったものの、申し出を受けることにしました。それから8カ月、佐々さんは横浜の自宅から森山さんの住む京都まで、片道3時間の距離を往復しはじめます。
「亡くなっていく人の話を聞くことは、人生で必要不可欠なこと」。彼はその姿で教えてくれた
「森山さんは、やがて仕事も辞めて、まるで長い休暇を取るかのように好きな場所に出かけていました。ドライブで琵琶湖に出かけたり、ときにはディズニーシーに遊びに行ったり。でも、在宅医療の話は一切しない。共同執筆と言われても一体何をどう書いてほしいのか、どうして欲しいのか、私にはよく分かりませんでした。
でもそれは今思うと、彼自身のありのままの姿を私に見せていたのではないかと。死を目前に迷ったり揺れたりしながら、人生の意味を問い続ける。そういうものなんだと彼が身をもって伝えてくれたんだと思います。」
やがて病状は進み、別れのときが近づきます。病院の診察の中で、森山さんは運命を受け入れざるを得なくなります。
「そのときの彼の表情が読めませんでした。来るべきときがきた、と思って受け入れたのか、それとも違うのか、私にはよくわかりません。それからもずっと在宅で過ごしていた森山さんでしたが、本人がお寺に出かけ、自分のお葬式の手はずなどを相談し、その場に私も誘われて同席するなど、旅立ちの準備を見せてくれる日々が続きました。」
そして……。そのとき彼が佐々さんに託したものは? 佐々さんが彼から受け取ったものは?
「森山さんは、看護師として働いている頃から、亡くなっていく人の話を聞くことは人生で必要不可欠なことだと言っていました。それを私に教えることで、本を通じて読者の方々にも伝えたかったのではないかと思うんです」
この本を読み終えたとき、不思議な清涼感が漂います。死というものを、よりリアルに感じて受け入れることで、「死」が、怖い、辛いだけのものではなくなっているのを感じます。『エンド・オブ・ライフ』は、そんな読後感を残す秀作です。
正体の知れないウイルスに、平静ではいられない毎日。日常を遮断し、心静かに本を読むことは、なかなか出来るものではありません。でもそんな今だからこそ、人間の生と死の本質を描くこの本に接する、絶好の機会のようにも思えます。
インタビュー・文 金田千里、撮影・山下みどり

『エンド・オブ・ライフ』佐々涼子 集英社インターナショナル ¥1700(税別)
在宅での終末医療を描いたノンフィクション。命の閉じ方について、末期がんの看護師や多くの素晴らしい患者たちから教えられる、珠玉のストーリーが集められた1冊
速報!「Yahoo!ニュース | 本屋大賞 2020年ノンフィクション本大賞」の受賞作品が、佐々涼子さんの「エンド・オブ・ライフ」に決定!