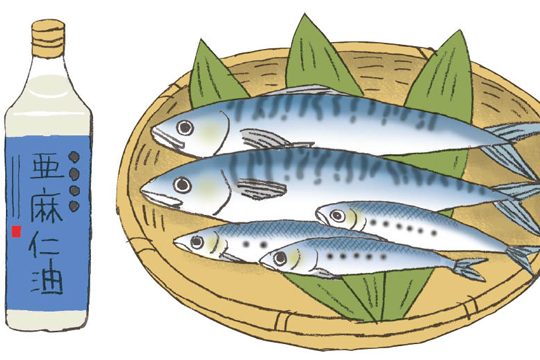作家、歌手、そして現在は、大学で哲学の授業も教えているドリアン助川さん。
2013年に出版した小説『あん』は、22言語に翻訳され、樹木希林さんが主演した同名の映画も話題を呼んだ。
最新刊の『動物哲学物語 確かなリスの不確かさ』は、動物を主人公にした21のストーリー。
クマ、キツネ、クジラ……。地球上の生き物たちが、心の叫びをぶつけながら、自分たちの命を確かめていく。

Profile
どりあん・すけがわ 作家・歌手。明治学院大学国際学部教授。1962年、東京生まれ。早稲田大学第一文学部哲学科卒業。放送作家などを経て、1990年にバンド「叫ぶ詩人の会」を結成。90年代にはラジオパーソナリティとしても活躍。同バンド解散後、2000年からNYに3年間滞在。帰国後、本格的に執筆活動を開始する。どら焼き屋の女性店主と従業員との交流を描いた小説『あん』は各国で翻訳され、フランスの「DOMITYS文学賞」「読者による文庫本大賞」など4冠に輝いた。河瀨直美監督による映画化も話題に。『線量計と奥の細道』、『新宿の猫』、『水辺のブッダ』など、著書多数。
撮影/chihiro. 取材・文/石井絵里
動物、そして哲学。本当に大切なものを凝縮したら…
音楽や言葉を通して、私たちに多くのメッセージを発信しているドリアン助川さん。
『動物哲学物語 確かなリスの不確かさ』は、1話ごとに登場する生き物たちが、己や仲間たちに問いを投げ続ける。
「自分は何者なのだろう?」、「今、ここにいる意味とは?」。
動物が発する疑問や感情に触れるうちに、鈍っていた感性や情熱に火を灯してくれる。
サル、リス、キツネといったなじみ深い存在はもちろん、アマゾンに住むナマケモノやバク、ウルグアイの深い森の中にいるアリクイといった、私たちが日ごろ、あまり目の当たりにすることのない生き物たちも、主人公として描かれているのが興味深い。
物語の中で、彼らの生態や生きている土地を疑似体験することで、異なる生命への想像を膨らませ、なおかつ地球を旅しているような気分にも。
この熱量の高いストーリー、ドリアンさんにとっては構想50年、少年時代の想いや、その後のリアルな体験や学びを、あたため育てて、生まれてきた作品だとか。
「ずっと『動物もののお話を出版したい』と言っていたんですが、周りからは『動物を主人公にした名作物語は、世界中にいっぱいある』、『書いても売れないでしょう』、と言われ続けていましてね(笑)。『いっそのこと、動物じゃなくて昆虫にしたらどうですか』という意見もありました。
でも私は、子どもの頃から本当に動物が大好きで。飼育関係の仕事や、各国の生き物を撮影する動物カメラマンの仕事にも憧れがあったんです」
“根っからの生き物大好き少年だった”というドリアンさんだが、本著のもうひとつの大きな要素、「哲学」とは、どうやって出会い、興味を覚えたのだろうか。
「哲学との出会いは思春期の頃です。学校や社会のルールに違和感を感じることが多い学生で、進学校に在籍していたのに、“偏った勉強しかしない落ちこぼれ”みたいなところがあったんですよね。
そんな中、倫理社会の授業で哲学に出会い、『こんなに楽しい学びがあるのか!』と感動したんですよ。
結果的に、生物と倫社だけが高得点な、アンバランスな学生になってしまい、大学受験も苦労したんですが(笑)。
倫社って受験では暗記科目としてさらっと終わりがちですが、理性そのものについて考えたり、言葉について思いを馳せられる、とても豊かで楽しい時間なんですよ」
ワニとニーチェが繋がって、物語の素が生まれた
動物と哲学。この2つが、表現として結びついたのは、今から15~16年前。きっかけは、ワニだったのだとか!
「本著には収録されていませんが、すごく狂暴なワニを主人公にしてお話を書こうと思った時があったんです。
ワニって恐竜時代からいるけれども、ずっと何かを襲って食べている。同じ行為を何万年も続けていて、苦しくないのだろうかと思ったんです。
もちろん彼らはそんなこと、何も考えて生きていないでしょうけれどもね(笑)。
その時に”同じ行為を繰り返し続けるワニ”と、ニーチェの永劫回帰(世界は進化しているのではなく、ただ永遠に繰り返すのみ)という思想が、頭の中を巡りました。これ、繋げて考えてみたら面白くなりそうだなと。
永遠に繰り返される世界は、苦悩を生み出す素でもあるし、逆にこの世への肯定にもなり得る。ニーチェの永劫回帰の思想と、もう一人、ランボーという詩人の考え方をワニに投影して、歌劇を作ったんです。
この辺りから、動物と世界の思想を交えた物語を、本格的に書くようになりました」

ドリアンさんは、1990年にバンド「叫ぶ詩人の会」を結成。個人の思いや社会に対してのメッセージを言葉にする、ポエトリーリーディングという表現スタイルの、先駆者でもある。
バンドは惜しくも2000年に解散してしまうが、歌手活動は、現在も継続中。
さらに、執筆業でもこれまでにたくさんの作品を生み出してきた。今回の物語を書くにあたっては、アーティストとして、そして一人の人間として、こんな思いもあったのだとか。
「それこそ若い頃は『上海ガニを思いっきり食べたい!』というような、俗な欲望もいっぱいあったんですけれどもね。色んな仕事をしていくうちに、もはや色気や食い気みたいなものは、ほとんどなくなってきてしまって(笑)。
バブルや昭和的な価値観がそぎ落とされていった結果、心の中には本当に大事なものだけが残るようになりました。
それが、動物と哲学だった。
その”大事なもの”が凝縮されたのが、この本。
執筆の期間は、それぞれの動物になりきって生活し、その視点からの世界を描きました。もしかして、動物によってはちょっと変な人、になっていたかもしれませんね(笑)」
個を極める西洋哲学と無から始まる東洋哲学。どちらも面白い!
本著では、ヨーロッパで生まれて発展した西洋哲学と、東洋に古来伝わる東洋哲学、両方の考え方が、動物たちが抱える戸惑いや経験を通じて、私たちの心の中にすっと入ってくるのも、大きな読みどころ!
「西洋の哲学は時代によっても変わりますが、シンプルに言うと”個”にこだわる考え方。
そして”我思うゆえに我あり”のデカルトから始まった個を巡る哲学は、20世紀に入る頃には考えつくされ、否定されて粉々になっちゃっていてね。
否定するといっても、今の”論破”とは違いますよ。あれは、精神が幼いだけ。
西洋哲学の中の否定とは、先人の知恵を受け入れて、そこからさらに新しいものを生み出すという意味です。
第二次世界大戦のあとにサルトルらが広めた実存主義、1960年代に発展していった構造主義、その先にポストモダンの流れがあり…と、フランスの近代~現代思想を追うと、百花繚乱の人智を味わえます。
それは、人間の器を大きくすることにもつながるのではないでしょうか」
東洋哲学には、どんな想いを抱いているのだろうか。
「個にこだわる西洋思想とは、逆の考え方をしていますよね。”個なんて何もないよ”ってところからすべてが始まっています。
私は大学時代、東洋哲学を専門に学んでいましたから、2つの思想の違いや、それぞれのいいところ、面白味なんかがよく分かります。
特に意識をしたわけではないですが、今回書いた本の中でも、両方の価値観が混ざり合った世界が生まれたかもしれません」
記事が続きます
知ることで、世界と自分の関係が変わってくる

こうしてドリアンさんが長年追い続けている哲学の世界は、日常の中でも、たくさんの滋養をもたらしてくれるのだそう。
「個の在り方を追求する西洋の思想と、無が前提の東洋思想を知り得たことで、世界と自分との関係も変わってきましたね。
公園の中を散歩していると、そこには私の大好きな花や鳥たちがいる。彼らは私とは異なる生命体です。
でも同時に、地上の上で”生き物”として一緒につながっている存在でもある。
それぞれの個を大事にしながら、全体の中で活かされていると感じられるのは素晴らしいし、そういう気持ちで世の中を眺めていると、まるで自分が”ひとつの大きな森”のように感じられてくるんですよ」
(ドリアン助川さんが”若さ”、”老い”について、さらに哲学的に考える後編はコチラ!)
<書籍情報>
『動物哲学物語 確かなリスの不確かさ』
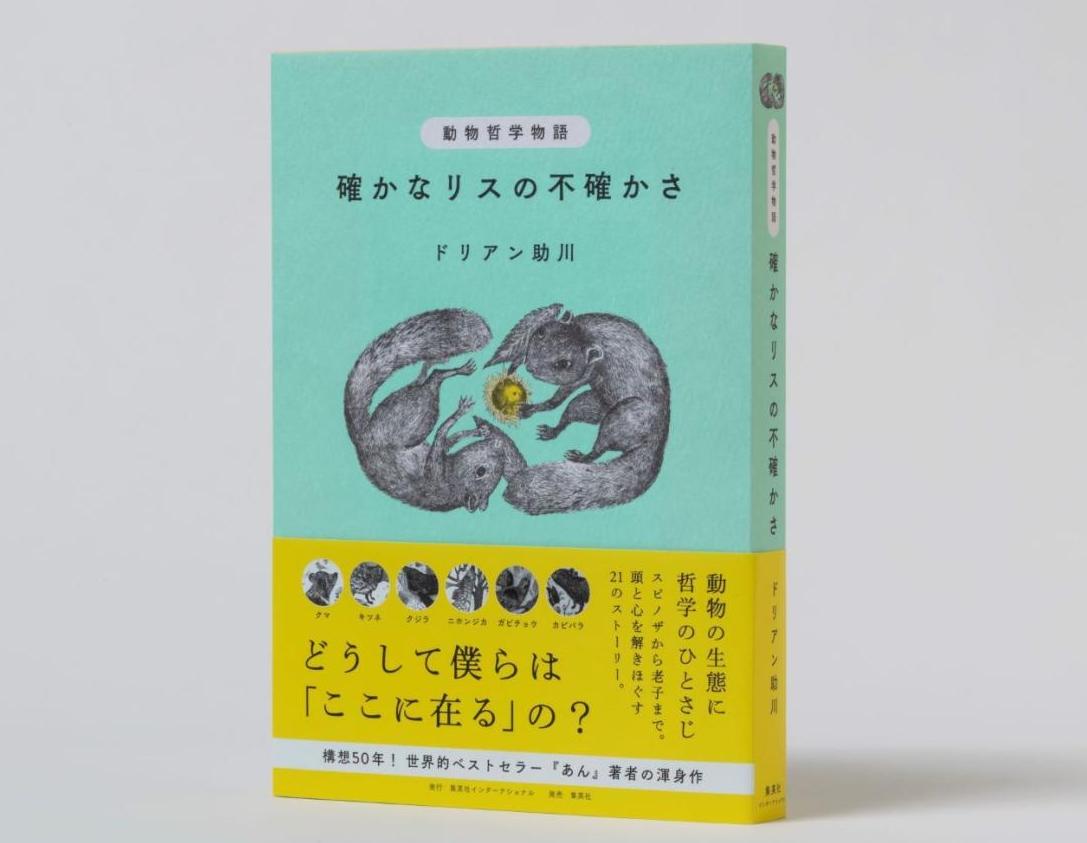
どんぐりの落下と発芽から「ここに在る」ことを問うリスの青年。
衰弱した弟との「間柄」から、ニワトリを襲うキツネのお姉さん。
洞窟から光の世界へ飛び出し、「存在の本質」を探すコウモリの男子。
土を掘ってミミズを食べる毎日で、「限界状況」に陥ったモグラのおじさん。

絵/溝上幾久子
日本や南米の生き物が見た「世界」とは?
動物たちの生態に、哲学のエッセンスを加えた21のストーリー。
哲学といっても、学術的な難しい話はなく、各物語の主人公の叫び、嘆き、そして優しさに触れることで、明日を生きるための底力を上げてくれる。
版画家・溝上幾久子さんの動物の絵が楽しめる巻頭グラビアつき。(2000円/集英社インターナショナル)
本の詳細はコチラから。
★『動物哲学物語 確かなリスの不確かさ』刊行 特別講座も配信中!
ドリアン助川さんが、動物たちの熱い叫びを“スペシャル”朗読!申し込んだ方にはサイン入りの書籍とオリジナルポストカード(1枚)が届きます。特別講座の詳細はコチラから。