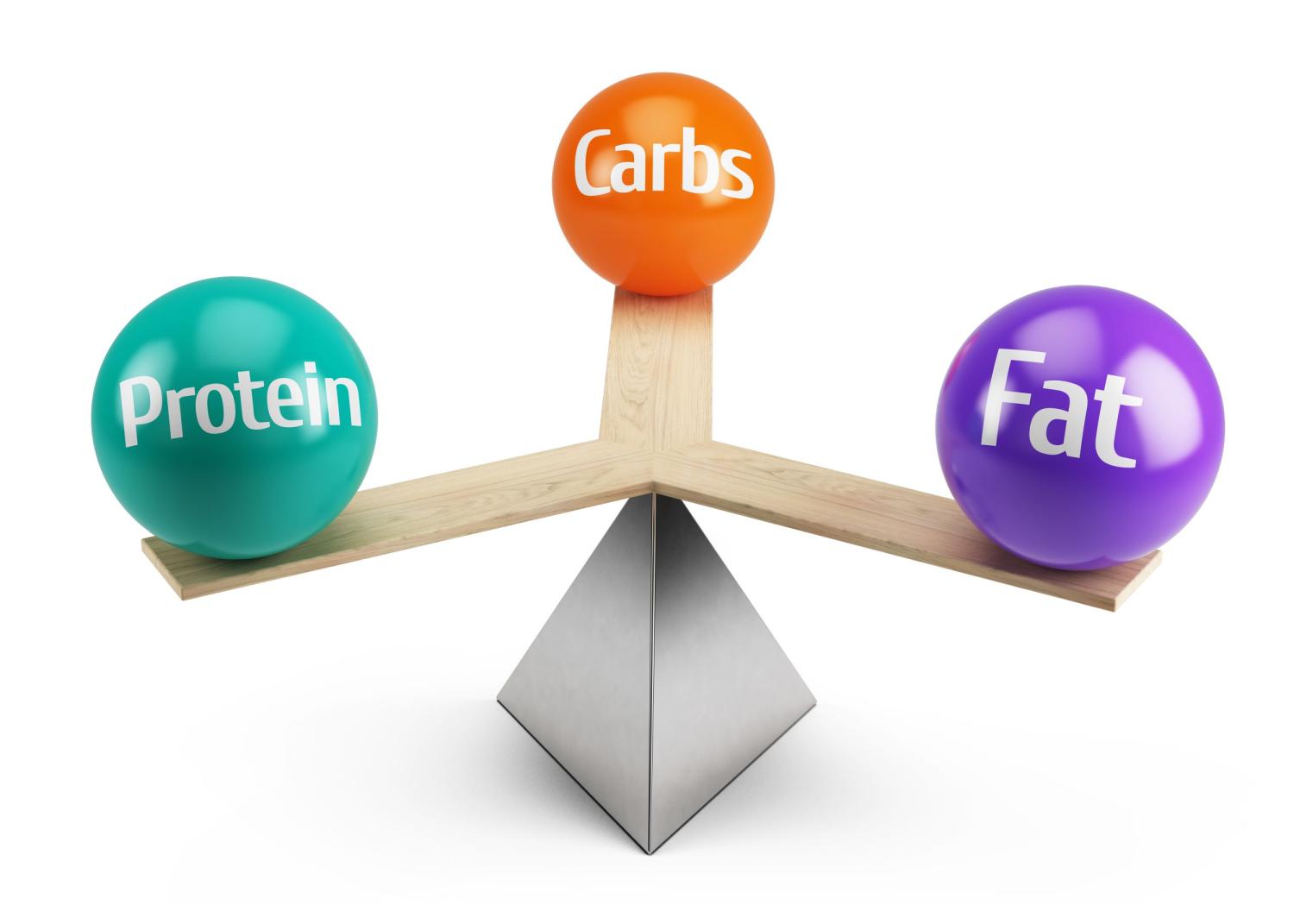
糖質をとりすぎていると、タンパク質不足になりやすいのはなぜ?
「私たちが食べられる総量はだいたい決まっているので、1回の食事でご飯などの糖質をたくさん食べていると、肉などのおかずの量はどうしても減ってしまいます。
例えばパスタを食べたとき、タンパク質は少量の魚介類だけといった場合が多く、タンパク質がほとんどとれません。しかも、麺だけでお腹もいっぱいになってしまうでしょう。
また、最近、糖を過剰にとると、胃の中の食べ物を十二指腸に押し出すMMCと呼ばれる胃のぜん動運動が一時的に止まることがわかってきました。
これは東京大学の研究チームが明らかにした現象で、“糖反射”と名づけられています。
MMCが止まると胃の中に未消化物がとどまるので、胃の不調の原因になります。そのため、ますます肉などのタンパク質がとれなくなってしまうのです」(金津里佳さん)

タンパク質と糖質は、それぞれどれくらいとるのがいい?
よく、PFCバランスという言葉で、とるとよい割合が示されますが…。
「PFCバランスとは、Protein=タンパク質、Fat=脂質、Carbohydrate=炭水化物のバランスのことです。
一般的に、日本人の理想的なPFCバランスは、炭水化物50〜65%、脂質20〜30%、タンパク質13〜20%とされていて、厚生労働省が発行する『日本人の食事摂取基準』にも明記されています。
これは栄養学の基本とされていますが、実はこのPFCバランスには科学的根拠がありません。
日本のPFCバランスは、1950年代に、日本人がどんな食事をしているかのアンケート調査を行い、その平均値で導き出されたものなのです。
当時、アメリカにも似たようなものがあり、それを参考に日本で作ったと思われますが、当時のアメリカのPFCバランスにも科学的根拠がありませんでした。
そもそも人間の体は水分を除くと4割ほどがタンパク質で、それに対して糖質は水分を除いて1%未満。それなのに食事で糖質をいちばん多くとるのは、アンバランスとしか言いようがありません。
これでは、年齢とともに筋肉やホルモンは作られにくくなり、血糖値ばかり上がっていってしまうでしょう。
ですから、このPFCバランスは参考にしなくてOK。
では、どれくらいとるのがよいかというと、個人差も大きいので、数値で考えるのでなく自分の体感で考えましょう。
まず最初に、肉や魚などのタンパク質のおかずを気持ちよくお腹がいっぱいになるくらいまで食べます。そして次に野菜を食べます。
ご飯などの糖質は、最後に適量食べましょう。ご飯なら茶碗1杯を超えない程度の量にし、食べられなければ食べなくてもOKです。この食べ方をすれば自然とタンパク質の割合が増え、糖質の量も適量になります」

糖質ばかり食べたくなってしまう状態を改善するには?
「糖質ばかり食べてしまうのは、血糖値と関係があります。
血糖値が下がると“お腹が空いた! 何か食べろ!”という指令が脳から出ます。血糖値は糖質をとると簡単に上がるので、お腹が空くとつい糖質をとりたくなるのです。
空腹時に糖質が多いものをとると血糖値が急上昇して、今度はそれを下げようと、過剰にインスリンが分泌されて血糖値が急激に下がるので、また糖質をとりたくなってしまいます。
こんな悪循環を防ぐためには、血糖値が乱高下をしないようにすることです。
方法としては、糖質は食事の最後に食べるようにして、先にアブラやタンパク質をとるようにすると血糖値の急上昇が抑えられます。
肉が食べられない人は、食事と一緒にお茶にココナッツオイルを入れて飲むのもOK。
また、どうしても甘いものが食べたくなったときは、糖質量が比較的少ないハイカカオのチョコレートや、甘いたれの焼き鳥や焼き豚などを食べるのがおすすめ。
そういう食べ方をしていると血糖値が乱高下せず、甘いものに手が伸びることも減っていきます。
ただし、糖質を減らす場合には注意点があり、いきなり減らすのはNG。
タンパク質や脂質が不足していて、糖質中心の食事だった人がいきなり糖質を減らすと、体調をくずすことがあるので、最低でも1食150g程度の肉が食べられるようになってから糖質量をコントロールしていきましょう」
【教えていただいた方】

医療法人美健会 ルネスクリニック東京・管理栄養士。北陸学院大学短期大学部食物栄養学科卒業。産科婦人科、人工透析科、栄養療法を主とする自由診療クリニックでの勤務を経て、2019年より現職。「人の身体はみな同じではない」をつねに意識し、日々の栄養カウンセリングに臨む。「食事は治療」との信念から一生続く食事という行為を根本治療ととらえ、論拠が納得できる正しい情報を届けたいという思いから、書籍などで情報を発信。著書に『9割が間違っている「たんぱく質」の摂り方』(青春出版社)がある。 金津さんphoto/久富健太郎
写真/Shutterstock 取材・文/和田美穂


























