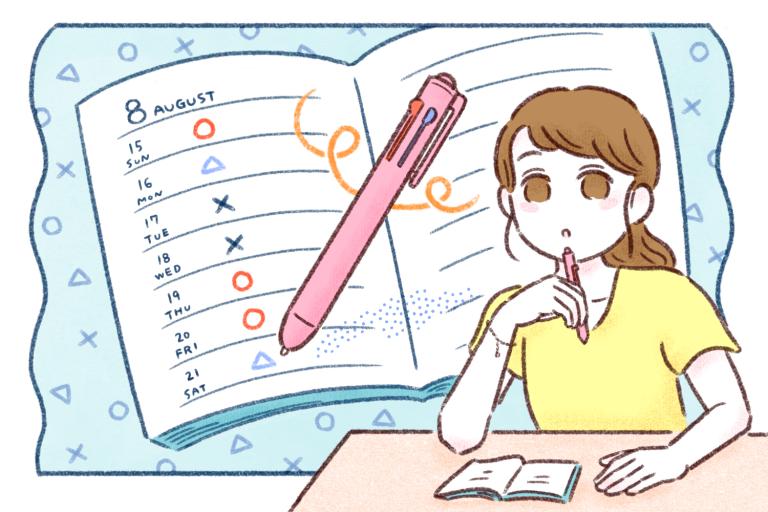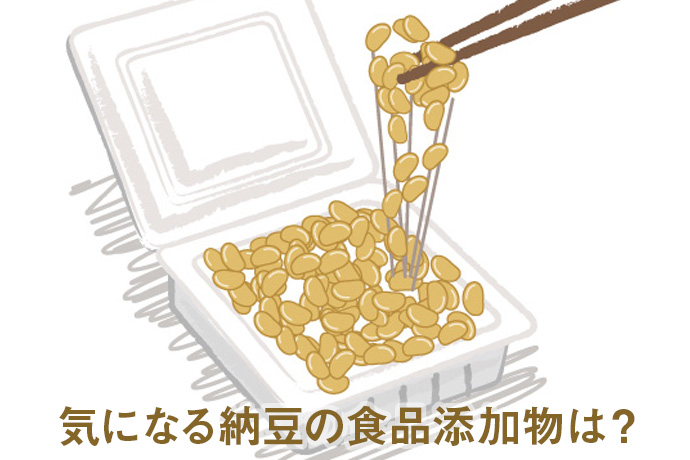慶應義塾大学名誉教授、同大学予防医療センター特任教授。専門は内分泌学、高血圧、糖尿病、抗加齢医学。1983年京都大学医学部卒業後、米国ハーバード大学、スタンフォード大学で博士研究員。京都大学医学部助教授を経て、慶應大学医学部にて教授、2023年より現職。著書やメディア等でホルモンの仕組みや体の働きなどをわかりやすく解説。著書多数。
ストレスが病気を引き起こすという新発見
ストレスがたまって体調をくずす、ストレスで早死にする…「ストレス」という言葉はどうしてもネガティブなイメージがついて回ります。
実際、50代は仕事も忙しい、自身の心身の変化もある、加えて親の老後問題も絡んでくる、といった調子で、日々ストレスを感じて生活している人は多いことでしょう。
でも、ストレスってそもそも何? なぜこんなにネガティブなイメージなの?
「ストレスとは外的な刺激のことです。
もともとは物理学の分野での言葉で、力や圧力が加わってものが歪んだり形を変えた部分のことを『ストレス』、その状態を引き起こした外的な刺激を『ストレッサー』と呼びました。
私たちがよく使うストレスという言葉は、このふたつをひとつにまとめたイメージです」(伊藤裕先生)
「医学において『ストレス』という言葉が使われ始めたのは、1930~1940年代、カナダの生理学者ハンス・セリエ博士が発表した『ストレス学説』がきっかけです。
セリエ博士は、ストレッサーの影響で体内に特定のホルモンが増え、さまざまな反応が起こることを突き止めました。
当時、人が病気になるのは病原体のせいだと考えられていたので、外部からの刺激によって病気が引き起こされるというこの発見は大きなものでした。
その後、セリエ博士は『ストレスそのものが悪いわけではなく、その種類や対処法が重要だ』と語っていますが、『ストレスは病気を引き起こす』という部分が衝撃的だったために、その部分が独り歩きしてしまったのです」
日本でストレス=悪のイメージが定着したのは1980年代以降。
「景気のいいイケイケの時代は人を疲れさせます。そこでストレスに光が当たり、90年台になって景気の低迷とともに、ストレスが社会問題化していきました。
頑張っている人にとって『休んだほうがいいよ』と言われるのは心地よいもの。メディアなどの商業的な戦略もあって『ストレスがあると病気になる』という感じで広まったのでしょう」
いいと感じるか悪いと感じるかは「受け止める側の問題」
悪いイメージばかりが先行しているストレスですが、伊藤先生は「ストレスがないと人は生きていけない」とさえ言います。
「社会の中で生きていると、ストレスと聞くと心理的なものを思い浮かべる人が多いでしょう。
ですが実際のストレスとは、外から受ける刺激のすべて。食べ物、日光、暑さ寒さ、音など物理的な刺激から、誰かと話したときに入ってくる情報なども含みます。

その刺激を受けたときに、不快感や違和感があると『ストレスを受けた』と自覚しやすいだけで、意識に上らないレベルでは体は常にたくさんのストレスを受けています。
ということは、ストレスそのものには『いいストレス』も『悪いストレス』もなく、私たちの感じ方・受け止め方次第。
人のざわめきが聞こえる場所にいて『適度な賑やかさが心地よい』と感じる人もいれば、『ざわついていて落ち着かない』と感じる人もいる。まさにそれです」
記事が続きます
ストレスを受けると体は「よりよくなろうとする」
「私たちの体は、生きている間は片時も休むことなく、常に動き続けています。
何らかのストレスが加わると、まずホルモンが最初に反応します。ホルモンは血液に乗って全身を回り、血管や心臓といった標的機関にたどり着くと『血流を上げなさい』『心拍を上げなさい』といった指令を伝えます。
そうやって常に機能を調整し、体を元に戻そう= よりよい状態にしようと働きます。
これには多くのエネルギーを使うし体にとっては負担が大きいため、この状態は長くはもちません。
大きなエネルギーを使ったあとは、緩んでリラックスするようにできている。
そうしたリズムの繰り返しで体は少しずつ強くなっていきます。
大事なのはリズムがあることであり、ストレスを避けることではありません。
それは物理的なストレスも精神的なストレスも同じ。
ストレスがあってこそ、それを乗り越えることでより強くなれる。
『しんどい思いをしたけどなんとかやり遂げ、成長できた』というのは、50代なら誰しも一度は経験があることでしょう。
まずは、ストレス=悪であり避けるべきものである、という呪縛からいったん距離を置き、冷静に眺めてみることから始めたいですね」
イラスト/ツルモトマイ 取材・文/遊佐信子
伊藤裕先生の話題の著書はこちら