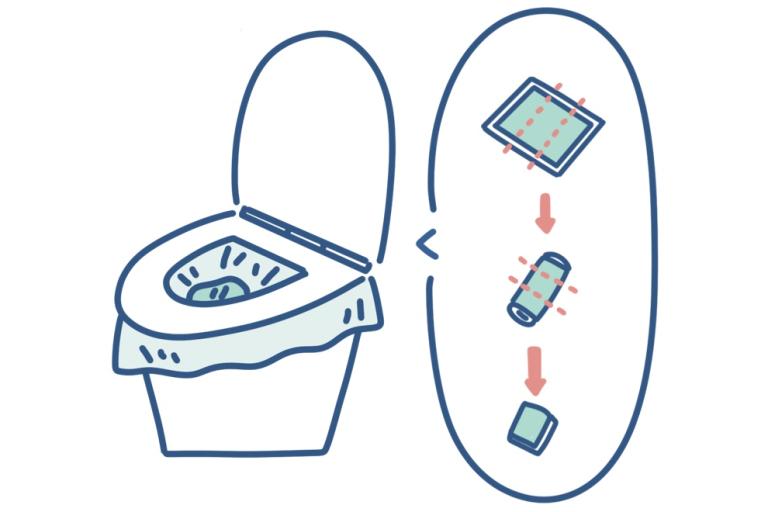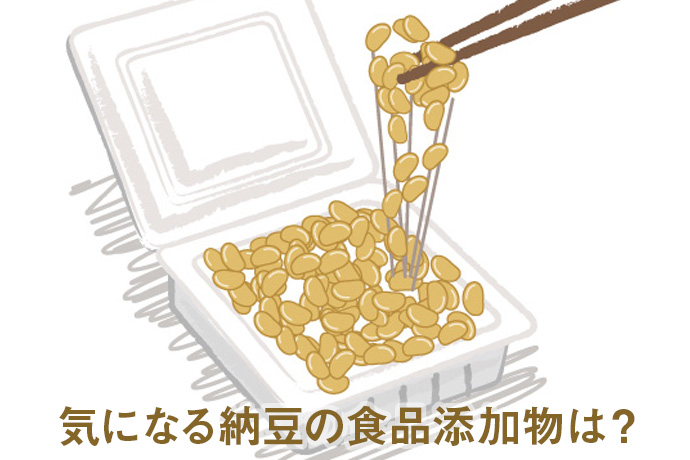年齢のせいか、最近テレビで気になるのが医療関係の番組。
治療の最前線を紹介するもの、病にかかった方のドキュメンタリーなど、さまざまなアプローチの番組がありますが、どちらかというと私はこのジャンルのものを避けがちです。
なぜなら、必要以上に「もし自分だったら。自分の家族だったら」と考えてしまうから。
情報を把握しておかねばという冷静な判断もあるのですが、どうしてもそちらが気になって。
我ながら「それでいいのか?」と思うのですが……。
そんな私が『脳が壊れた』を書店で手に取ったのは
「41歳、脳梗塞になりました」
深刻なのに笑える、感涙必至の闘病ドキュメント
という帯にギョッとしたから。
深刻なことが起きたら、そのまま深刻に受け止める性格なので、「笑えるってどういうこと?」という素朴な疑問がわいてきたのです。
しかも、大ベストセラー『バカの壁』で知られる解剖学者・養老孟司さんの感嘆コメントまで添えられていたのだから、「これは読むしかない!」とレジに向かいました。
『脳が壊れた』の著者は、1973年生まれのルポライター・鈴木大介さん。
社会からこぼれ落ちた人々を主な取材対象にしてきた方で、からだを売って日銭を稼ぐ若い女性の実態に迫った『最貧困女子』(2014年刊行)は大きな話題になりました。
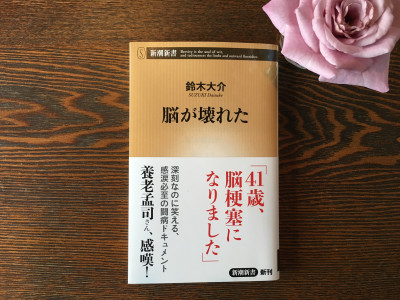
『脳が壊れた』
鈴木大介 新潮新書 ¥760(税別)
突然脳梗塞に襲われた著者が、心身の変化やリハビリの様子をユーモアを交えつつ克明に記録。やがて病が人生の軌道修正につながるまでをつづった、感動の1冊。現実の受け止め方、受け流し方などについて考えさせられる
『脳が壊れた』は、取材も執筆も(実は家事も)旺盛にこなしていた鈴木さんが、41歳のある朝パソコンに音声入力をしようとして、ろれつが回らなくなったところから始まります。予兆はあったけれど、そのときは整形外科で「肘から首の神経障害」と言われていたのです。
すぐさま奥様の運転で地元の脳神経外科に直行。検査の結果は「右側頭葉のアテローム血栓性脳梗塞」でした。つまり、動脈硬化でできた血栓が太い脳血管に詰まったのです。
当然急きょ入院、「血栓を溶かす薬剤や血液の流動性を高める点滴を行い、再発を防ぎつつ、可能な限り早期から機能回復のリハビリを始めましょう」ということになります。
当初鈴木さんは「ただただ猛烈な非現実感と違和感の中で、ワケも分からずボンヤリしていた」。
しかしその後彼は、というかこの本は、いわゆる“闘病記”とは違う特徴をどんどん見せていきます。
高次脳機能障害が残った鈴木さんに起きたのは半側空間無視、つまり左側にイヤなものがあってそれを見たくない(見ようとしても見られない)という感覚。その結果、相手と目を合わせられず右上方を凝視してしまうという症状でした。(その他にも、目に見える症状・見えない症状がいろいろ)
ここで鈴木さんはハタと気づいたのです。
“(僕みたいな)挙動不審な人物を僕は知っている。以前取材させてもらった事のある不良少年のヒサ君だ。”
“彼は脳に何らかのトラブルがあったのでは。
そして今まで取材してきた社会からこぼれ落ちた人々を『面倒くさい人たち』『不自由な人たち』と感じることが多かったのも、そこに理由があったのでは”と。
「だとすれば、これは僥倖だ」「僕は記者として、初めて我が身をもってリアルな彼らの当事者認識を理解できるようになったのかも知れない」と思い至った鈴木さん。
そこを読んだとき「えっ、僥倖!?」と心底驚いたのですが、本当に彼はそう実感し、緊急入院の12日後には「誤字脱字に誤変換でボロボロの(脳梗塞の当事者感覚を文字に残すという)企画メール」をある編集者に送信。
もともとの体育会的気質(!?)もあって、がむしゃらにリハビリを始めます。
もちろんそれは医療スタッフの指導のもと行われますが、彼が編み出しだ“自己錬”がユニーク!
気持ちを鼓舞するために、不自由な左手の親指を田中角栄、人差し指をマリー・アントワネットなどと名付け、その名を念じながら懸命に動かし続けたり……。
努力の甲斐あって鈴木さんは山あり谷ありながら回復していきますが、退院となると新たな問題が。
それは“見た目は健常者でも後遺症が残るとはどういうことなのか”を具体的に語ることになっていて、読んでいる私まで困難な現実を突き付けられたような気持ちになりました。
でもそれらに対しても、バカバカしく(!?)明るい改善法で立ち向かっていくので、思わず笑ってしまうのですが……。
やがて鈴木さんは「なぜ自分が41歳の若さで脳梗塞になったのか」を考えるようになりますが、ここから先はネタバレになるのでぜひ実際に本を読んでいただきたい!
自分と妻、友人たち、そして両親との歴史を振り返ることで、「なぜこんな病に陥るような人間=自分ができたのか」という問いへの答えを、徐々に導き出していきます。それは壮大な人間ドキュメントと言ってもいいくらい、奥が深いもので……。
この本の最後に鈴木さんの奥様によるあとがき的な文章があるのですが、これがまた意外というかなんというか。
本書の前半では天然キャラだと思っていた彼女の知的で冷静な面が表れていて、このご夫婦の絆の深さに心が震えました。
「いろいろあっても必死に生きている人たちがここにいる!」
当たり前のようでこの上なくすばらしいことを、実感させてくれる1冊です。秋の読書リストに加えてみてはいかがでしょうか。
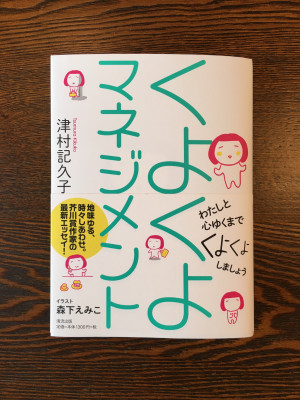
『くよくよマネジメント』
津村記久子 清流出版 ¥1300
心とからだの健康のために、私がたびたび読み返しているのがこのエッセイ。“くよくよする自分を否定せずにマネジメントする”という作家の津村さんの発想が新鮮!「明日の自分を接待するつもりで準備をしておく」という考え方には大納得