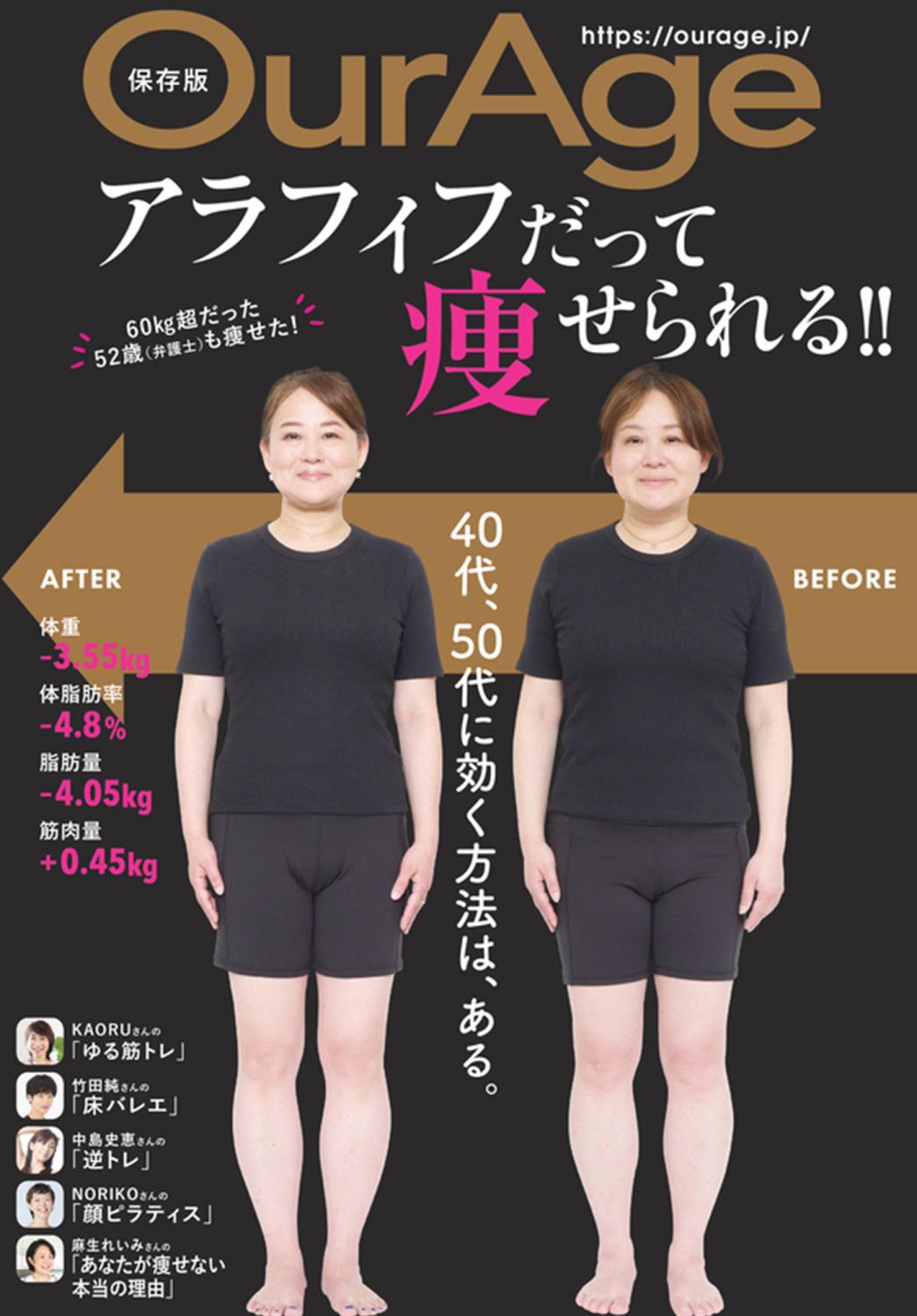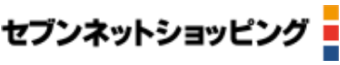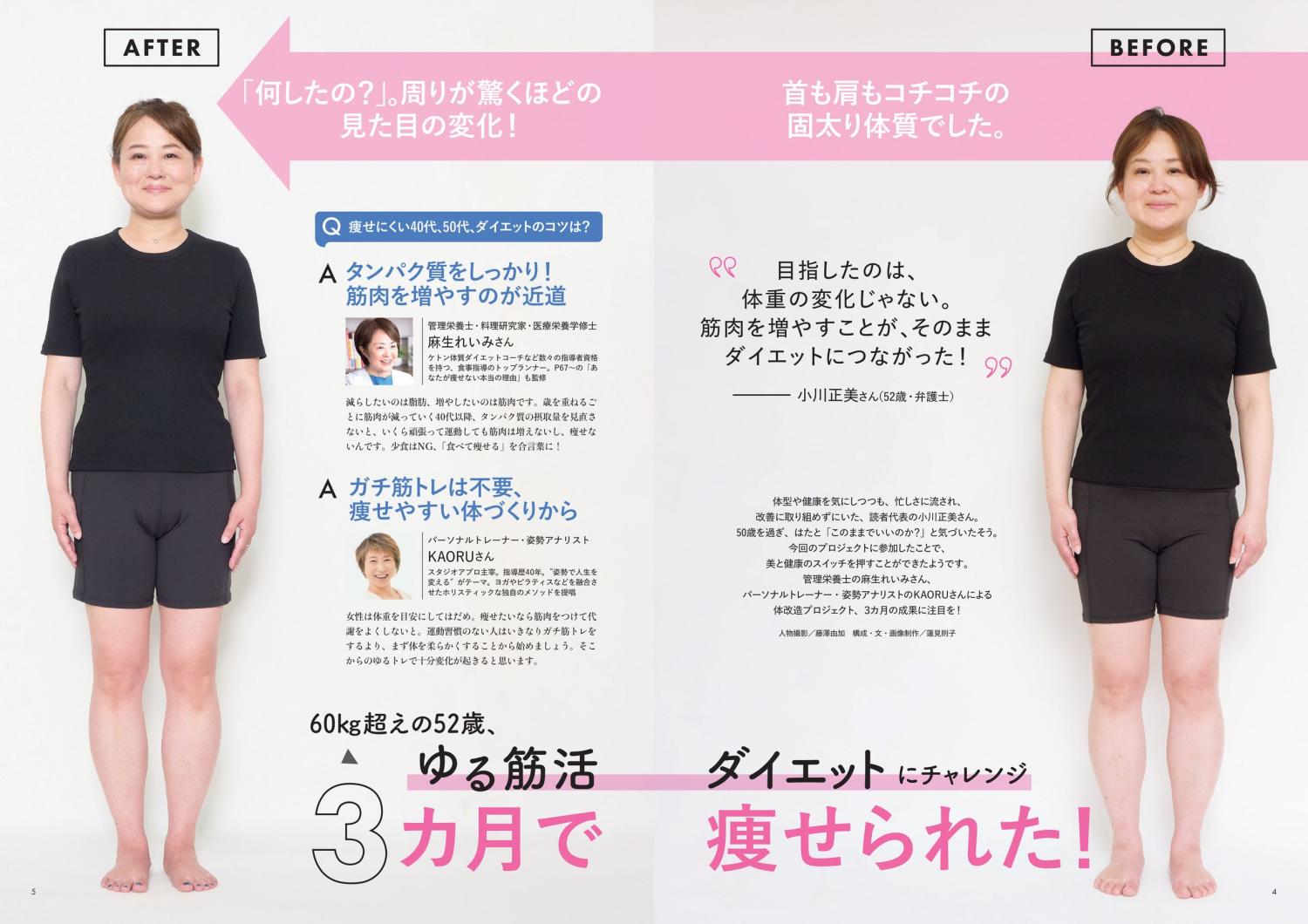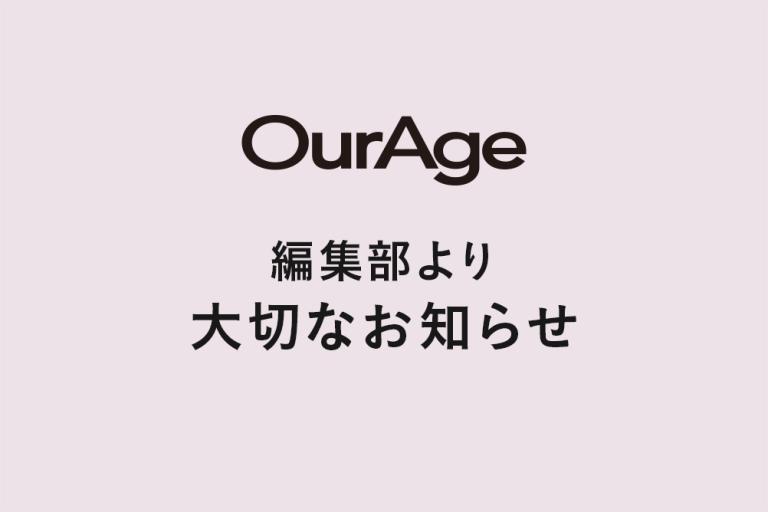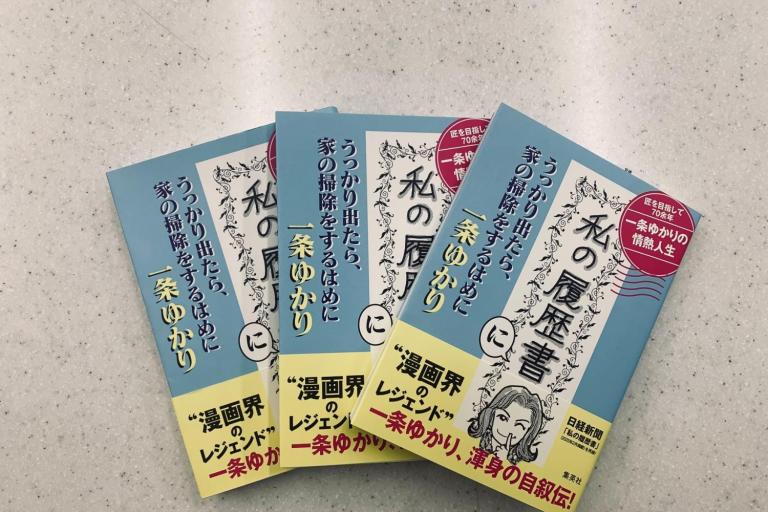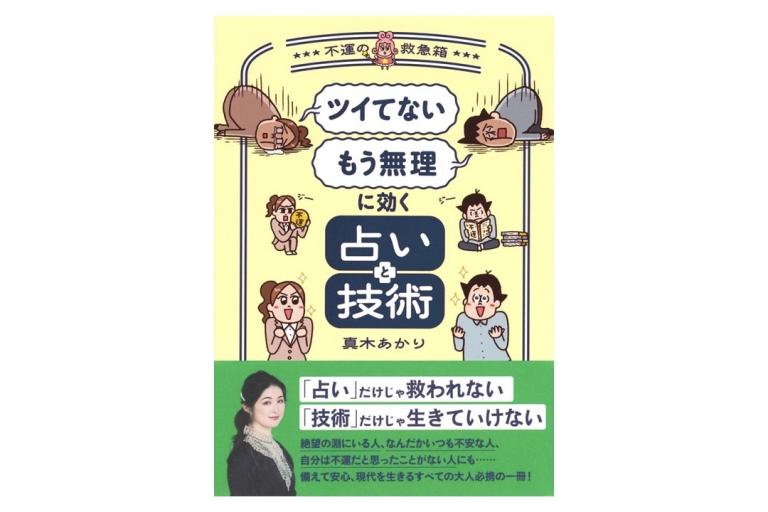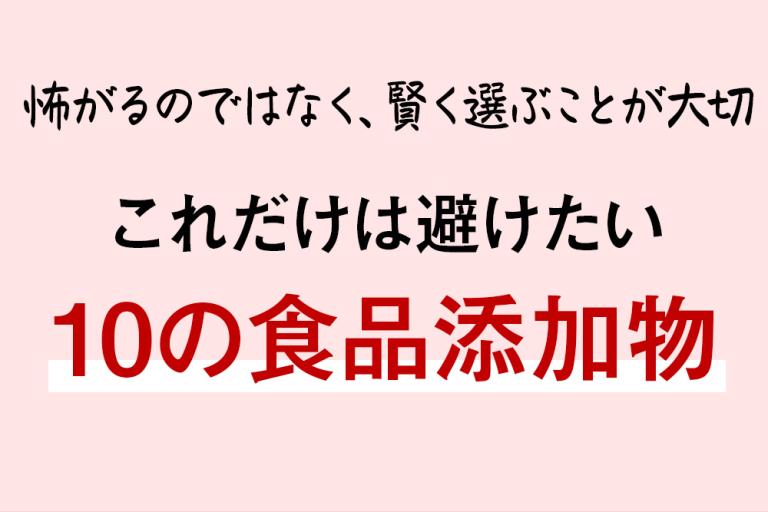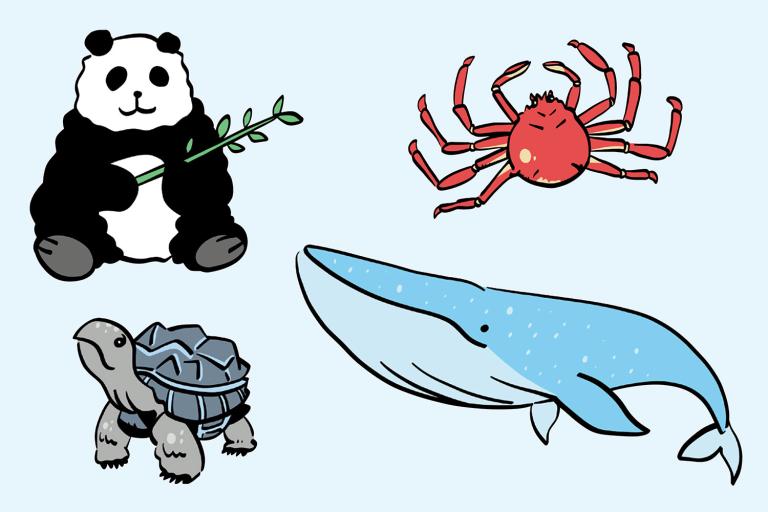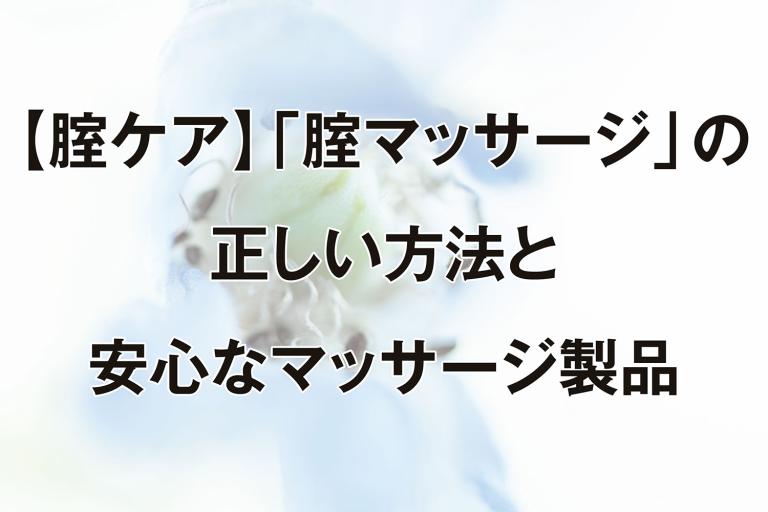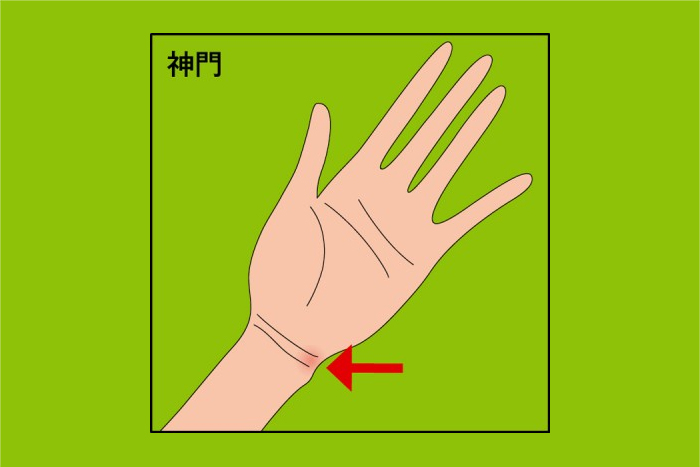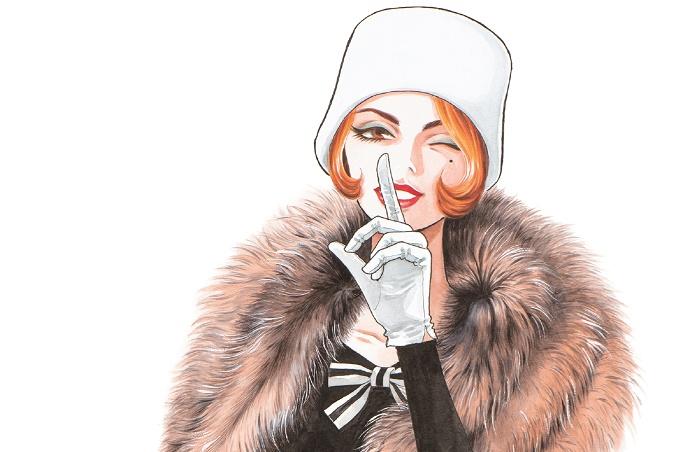一般的に推奨されているタンパク質の摂取量は体重1kg当たり1〜1.5g
タンパク質の摂取量は、1日に体重1kg当たり1gをとるとよいといわれていますが、この数値はどこから来ているのでしょうか?
「厚生労働省の『日本人の食事摂取基準(2020年版)』で推奨している1日のタンパク質の摂取量は、年代によって多少違いがありますが、体重1kg当たり、およそ1〜1.5gとされています。
例えば体重が50kgの人なら、1日50〜75gのタンパク質をとるとよいということです。
では、50gのタンパク質を肉でとる場合、どれくらいの量になるのかというと、食品中のタンパク質量はその食品の重量の20%程度とされています。
ただし、肉のタンパク質は加熱すると元の重量の5〜10%程度減少するので、肉100gに対して5~10g減ることになります。なので、20gあったはずのタンパク質は10~15gになります。
ですから、肉100gのタンパク質を10gとした場合、体重50kgの人なら、1日に約500gの肉を食べましょうということになります。
実際は、調理による損失分は無視して計算されることがほとんどですので、一般的な栄養指導では1日に肉などのタンパク質を250〜375gと言われることが多いです」(金津里佳さん)
いかがでしょうか? とても面倒ですし、そんなに食べられないと思う人が多いと思いますが、本当にこれだけとったほうがよいのでしょうか。
「日々の食事でタンパク質量を計算してとることは、実際、非現実的です。加えて、この連載でこれまでにも話してきたように、タンパク質を消化吸収できる量は人によって違います。
厚労省が出している推奨量はそれを考慮していないものなので、あくまでも参考程度にしましょう。
消化吸収能力を考慮せずに計算で出した量のタンパク質をとろうと無理に食べても、タンパク質を消化吸収できるとは限りませんし、人によっては消化不良による不快症状のせいで、逆に食べたくなくなってしまい、とる量が結果的に減ってしまうので非常によくありません」

自分に適したタンパク質摂取量は、気持ちよくお腹いっぱいになるマックスの量
では、自分にとって適した量を、どのように考えればよいのでしょうか?
「大切なのは、自分が今、消化吸収できるタンパク質量がどれくらいかを把握することです。
自分が肉や魚を中心に、卵、大豆製品などのタンパク質食材を食べたとき、気持ちよくお腹がいっぱいになれるマックスの量が、自分にとって適正な量ととらえるとよいと思います。
食べていて少しでも胃もたれや膨満感などの不快感を感じたら、自分の消化吸収力を超えてしまったということなので、すぐに箸を置きましょう。
この量は、同じ人でも日によって違うと思います。
このようにして、必要なタンパク質量は自分で試行錯誤しながら見つけていくしかありません。これを繰り返すうちに、消化酵素や胆汁酸の量が増えていくので、少しずつ食べられる量が増えていきます。
ひとつの目安は、1食150gの肉や魚を食べられるかどうかです。胃もたれせず、これくらいの量を食べられれば合格です。
魚の場合は切り身だと1切れ約60gくらいなので、これに肉や卵、納豆や豆腐などを組み合わせてとるのもいいと思います。
ちなみに、ダイエットや健康維持のために、野菜から先に食べる“ベジファースト”をしている人もいますよね。
この食べ方だと、特に女性は胃が小さいので、野菜でお腹がいっぱいになってしまいがちで、結果的にタンパク質の摂取量が減ってしまうのでよくありません。
まずは肉や魚などの主菜からしっかり食べて、次に野菜、最後にご飯という順番にするのがおすすめです」
次回5月28日は、タンパク質をとるときに、どのような食材からとればよいかという、「種類」について詳しくご紹介します。
【教えていただいた方】

医療法人美健会 ルネスクリニック東京・管理栄養士。北陸学院大学短期大学部食物栄養学科卒業。産科婦人科、人工透析科、栄養療法を主とする自由診療クリニックでの勤務を経て、2019年より現職。「人の身体はみな同じではない」をつねに意識し、日々の栄養カウンセリングに臨む。「食事は治療」との信念から一生続く食事という行為を根本治療ととらえ、論拠が納得できる正しい情報を届けたいという思いから、書籍などで情報を発信。著書に『9割が間違っている「たんぱく質」の摂り方』(青春出版社)がある。 金津さんphoto/久富健太郎
写真/Shutterstock 取材・文/和田美穂