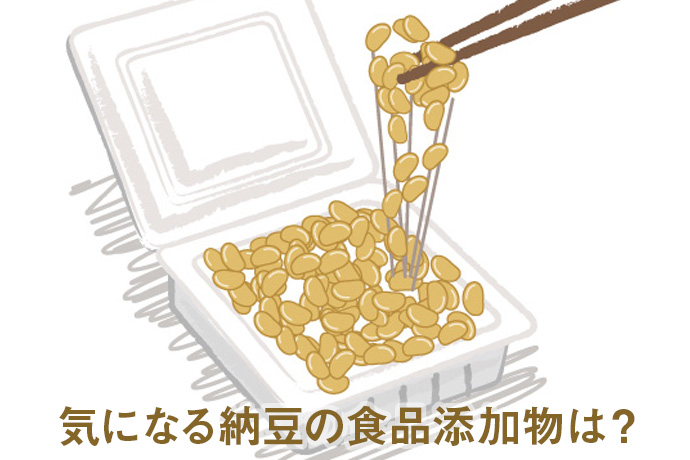わたしの目の前には、日本一の腕前だと評判の婦人科医が座っている。
「先生に切ってもらったらいっぺんでよくなったわ。素晴らしいお医者様よ」との知人の折り紙つきだ。
彼の喋り方から、すでに頭の良さが垣間見える。この人、切れ者なんだろうな。

貧血で手術が中止になってから、だいぶ時間がたってしまった。別の婦人科の意見を聞いて来い、と周囲には言われたものの、からだの調子が悪いうえに、気持ちまで欝々としてしまい、この医師にたどり着くまでは、幼稚園児のように、ずっと医者に行くのを渋っていた。
「セカンド・オピニオンをもらいに行くからCTスキャンの結果をください」と、医師に言うことがまずできない。靴を一足買うのだって、何軒も回って品定めをするのに、自分のからだのこととなると、医師のご機嫌をうかがってしまい、別の医師のところに行って意見を聞いてくるとは言えないのだ。
靴のサイズが違ったら返品できるが、内臓は切ってから、「やっぱりもう一回くっつけてほしいんですけど」とは言えないにもかかわらずである。
ノンフィクションライターなどと名乗って、いつもは威勢のいいことを言っているが、いざとなると権威に弱く、「思わず助けたくなる」と医者に思わせるような愛らしい患者でいたいのである。ああ、恥ずかしい。
そんな、自分への自己嫌悪も手伝ってだらだらしていたのだが、わたしを叱ってくれたのは父だった。
「いい加減、医者に行ってきなさい」
父は、からだの自由がきかなくなった母を10年間家で看病し、最後まで看取った鉄人である。彼は、幼いころ生みの母を亡くし、新しく家にやってきた継母も病気で亡くしたのだが、その二人も看取ったという苦労人であり、わたしから見ると、あふれる愛で家族の面倒を見た、仏さまのような人である。そんな人を、娘の病気で再び悲しませたくはない。
結局どうしたかと言うと、新しい医師のところで、もう一度隅から隅まで検査をしてもらった。もちろんCTスキャンもやり直しである。
その検査結果を目の前にして、第二の医師はこう告げた。
「見てください! 卵巣嚢腫があります。ほかの医師は誰も見つけられなかったでしょう」
「……」
医者ってみんなこうなのだろうか? 確か初診のとき、問診票に卵巣嚢腫のことについて書いたし、それについても話したはずだが、そこはもうすっかり忘れてしまっている。
彼の話は続く。
「今まで何人の医師に診てもらいましたか? 卵巣嚢腫は先天的な病気です。ふたりの子どもを産んだときには、もうからだの中にあったはずです。でも、誰も気づかなかったでしょう?」
自信に満ちたその言葉に、彼の思い込みを訂正する機会を失ってしまった。第二の医師によると、卵巣嚢腫の手術は避けられないことらしい。とにかく、これで手術は確定である。
しかし、最初の医師とは治療方針がだいぶ違った。
「嚢腫のある右の卵巣は取ってしまったほうがいいでしょう」
最初の医師は、卵巣を残して、中のものを掻きだす手術だと言っていたので、内臓摘出と聞いてにわかに緊張した。
わたしは「冷静になれ、冷静になれ」、と自分に言い聞かせつつ、前回の反省も込めて、一番気になる点を医師に尋ねた。
「わたしは子宮筋腫で、出血がひどいのが気になっています。こちらの治療はどうなりますか?」
すると、医師はこう説明した。

「あなたの子宮には、小さい筋腫がたくさんあって、奥にはとても大きなものもあります。これは普通なら、子宮を取る手術になるでしょう」
前の医師には患部を取り除くだけの手術だと言われていたので、気楽な気持ちで診察を受けたが、まさかの「臓器摘出」話。一気に話は一大事である。
「しかし、僕は子宮を取ることには反対です。子宮が大腸と癒着している場合が多く、子宮の摘出をするときに、大腸が薄くなってしまうんですね。すると、大腸がんになったときに、助かりにくい……。そんなこと、誰も言わないでしょう?」
日本一の腕を持つ医師は、日本の婦人科医療にやや懐疑的なようだった。
「ですから、子宮は残して卵巣をふたつ取ってしまいましょう!」
動揺が隠せない。いきなり卵巣を取って閉経させてしまうなんて、まだ心の準備ができない。
医師の言うことは単純だ。卵巣をふたつ取れば、ホルモンは止まり、生理は止まる。それで貧血も治まるというわけだ。
「佐々さんは今40代後半ですよね。あと数年で閉経は訪れます。ですから、数年前倒しかもしれませんが、今切ってしまいましょう。卵巣を残しておくと、卵巣がんになる可能性があります」
がんと聞いて、一層衝撃が走る。
「このままだと、がんになる可能性は何パーセントぐらいあるんですか?」
「200分の1です」
に、200分の1……?
50パーセントとか、10人にひとりとか言われたら、即決だろうが、200分の1。なんだかすごく微妙だ。でも、がんになる可能性が高いと言われたら、穏やかではいられない。
記事が続きます
つまり、これは予防的切除の意味もあるのだ。乳がんになりやすい家系のハリウッド女優、アンジェリーナ・ジョリーが、健康な乳房を予防的に切除して、世界的にニュースになったのは最近のことだ。
彼女の手術をめぐって、賛否両論が渦巻いたが、わたしはアンジーの決断に拍手を送ったひとりである。家族を乳がんで亡くし、まだ小さな子どもを育てている彼女が、自分のためのみならず、わが子のためにも、健康でいたいという気持ちは尊重すべきだし、気持ちは痛いほどわかる。
しかし、いざ自分が選択を迫られてみると、心は揺れる。しかも、最初の医師が臓器は取らないという治療方針を打ち出していたので、なおさらだ。
「あの、どうしても取らなきゃいけないもんでしょうか?」私が聞くと、医師は言った。
「今回は良性ですが、卵巣がんになると大変ですよ。僕は、あなたに、『取ったほうがいい』って言ってるんじゃない。いいですか? 僕から言わせると、『取らなきゃいけない』んですよ。マストです。取らないというなら、本人の自由ですが、のちに後悔しないように、自己責任で決めてください」

実感がこもっていた。医師は金もうけのためにすぐ切りたがると批判する人がいるが、わたしは同意しかねる。卵巣がんの治療は簡単な方ではないらしい。たくさんの患者さんが苦しむのを診てきての彼の実感なのだろう。診察室を出るとき、彼はこう言った。
「これが僕の身内なら、嫌がっていても手術を受けさせます」
わたしは、地下鉄の駅に降りると、ぼんやりした頭のままで、次の電車が来るのを待っていた。
今回はたまたま良性だったが、悪性であることを言い渡される人もいるだろう。もしかしたら、これは天が与えてくれたチャンスであるかもしれない。がんだと言われてからでは遅いこともある。
「切っちゃってもいいかもしれないな……」
そんなことを思いながら、銀色の列車が構内に入ってくるのを、わたしはぼんやりと見つめていた。