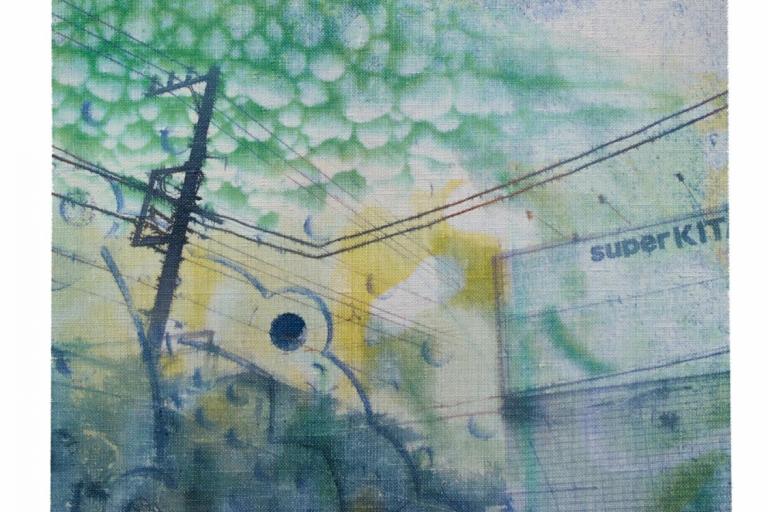第7話 年老いたタヌキ親父
お盆の提灯が飾られる駅前商店街には、代変わりしているであろう同級生の店が数軒あった。そこを訪ねるのが、今回の楽しみでもあった。
「およ? まーたまた、洒落たお茶屋になっちゃってんじゃん」
同級生の一人、ケンちゃんちの茶店が、なんだか今風に改装されている。
ガラス張りで、店内に並べられた大きな茶筒がまるでマリアージュフレールのようだ。
茶、と丸囲みで書かれた大きな暖簾をくぐると、これまた気障な白衣を着たケンちゃんらしいオジサンが、カウンターの中にいた。
胸にソムリエバッジがついている。店には額に入れた「日本茶ソムリエ」の認定証も飾ってあった。
「いらっしゃいませ」
まるでホテルマンみたいに、ケンちゃんが頭を下げた。
「ったく、気取ってんじゃないよ、私だよワタシ」
瞳はサングラスを取って、同級生に声をかけた。それでも分からないようなので、マスクを一瞬はずした。
「・・・えっ、田中?」
ケンちゃんは瞳の変わり果てた姿に驚いたが、同級生であることを確認すると、笑みがこぼれた。
「どーしたの? 同級会にもぜんぜん来ないし、田中はどっか海外でも行っちゃったんじゃないのかって、みんなで噂してたんだよ」
「いやぁ、父親がボケちゃったらしくて、様子見に来た」
「あ、それなー。あるあるだよ。お母さんは?」
「もう十年前に死んだよ。ガンだったの」
「そっかぁ。残念だったねー。十年前って、まだ若いじゃん」
「ケンちゃんちは?」
「オヤジは三年前に死んで、お袋は家にいるよ。たまに店に出ることもあるけど、毎日はもう体力的に無理だね」
「ボケたりしてない?」
「それが大丈夫なんだよ。お茶のカテキンがボケ防止になるからな」
ケンちゃんは自慢げに言った。
「そっか。じゃ親父にも買ってくか。どれオススメ?」
「お湯沸かすのも暑いからさ、冷茶がオススメだよ。これうちでブレンドしてるお茶パック。水出しですぐ出るし、抹茶たっぷり入れてるからさ」
「あ、じゃそれ」
「かしこまりました」
「ったく、気取ってんじゃないよ!」
二人で笑い合った。近所のガキ大将によく虐められて泣いていたケンちゃんが、慶応大学に行き、その後は知らんが立派なオジサンになって、日本茶ソムリエに・・・。
「じゃあね、また寄らせてもらうよ」
「水臭いこと言わないで帰りに寄んなよ。みんなに声かけとくからさ」
「いや今日は無理だからまたね」
記事が続きます
ケンちゃんのお茶店をあとにすると瞳は、商店街から実家方面に抜ける路地に入った。住宅街に入ると、途端に道幅が狭くなる。一通で車がぎりぎり入れる道を過ぎると、実家のある小路、車は入れない細い道路に至った。
「うわぁ、まんまやん」
新しく建て替えた家も数軒あったが、古い木造建築が立ち並ぶ、昭和の時代にタイムスリップしたような界隈だった。空き家なのか、割れたガラス窓にガムテープがバッテンに貼られている家もあった。
この辺りは庭というものはない昔ながらの下町家造りで、通りにいきなり玄関がある。
「あ、ここだ」
玄関先には、悦子叔母が置いたであろう、朝顔とホウズキの鉢植えがあった。
「コンニチワ―」
ガラガラとガラス戸をあけ、声をかけた。風鈴がちりんといい音を奏でる。
そこに、ひとまわり小さくなった悦子叔母が出て来た。
「ひーちゃん? まーまー、すっかり大きくなって」
って、嫌味か。瞳は思った。
そこへ、奥からステテコ姿の老人がひょっこり現れた。
「どちらさんですか? なんちて」
ふざけんなくそジジイ、瞳はマスクの中で、下唇を噛みしめた。
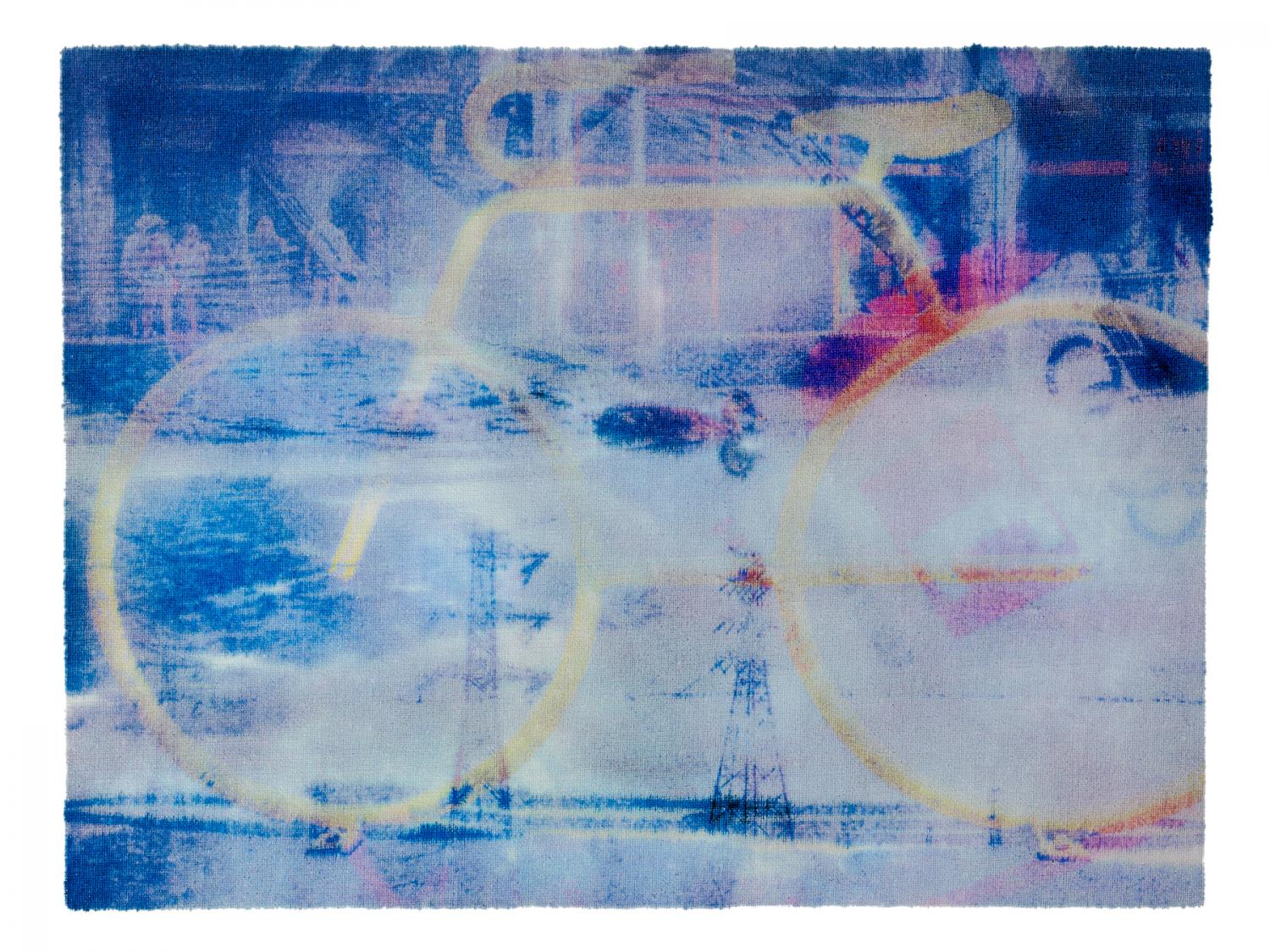
©︎AMU(フォトグラファーユニット.KNIT)