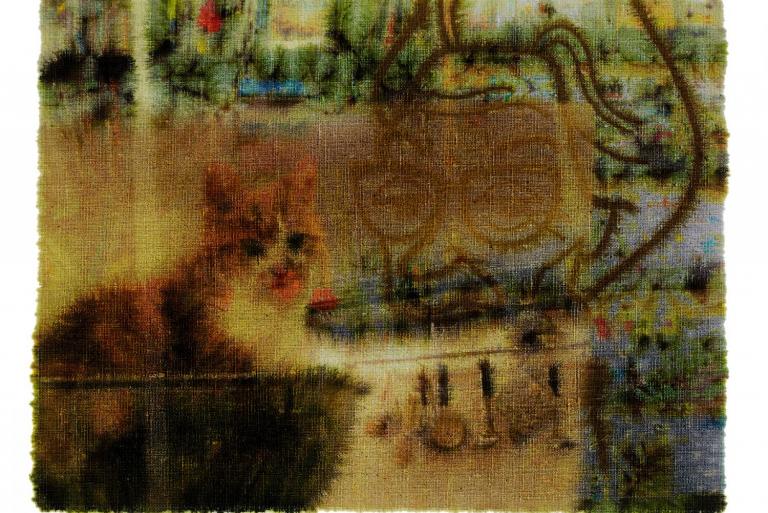最終話 実家のない故郷
九月に入り、従弟の純一から電話があった。
「あ、ひーちゃん? 純一です」
「あ、お久しぶりです。なんかすんません、娘がいながら全てお任せしてしまったようで・・・」
瞳は気恥ずかしかった。
「いーよいーよ、事情はよく分かってるからね。今は請け負い業者が色々あるから、古屋の片付けも金さえ払えばやってくれるんだ」
「ほんと何から何まですんません」
「今日電話したのはね、おじさんが施設に入ったんだけど」
「うん」
ああ、とうとう、と瞳は思った。
「親族はまだ感染予防対策で面会にも行けないんだけどね、ひーちゃんラインとかやってる?」
「それなりに・・・」
「施設のアイパッドで、月一回オンライン面会できるんだそうだよ」
「へー」
時代も進化したものだと、瞳は感心した。
「認知症の進行を遅くするためにも、親族の顏を見せてあげるのがいいらしいんだ」
「ほー」
そういえば瞳が会いに行ったとき、あの日だけ妙にシャッキリしちゃってると叔母も言っていた。
「ここはやはり実の娘であるひーちゃんが、一番励みになると思うんだよね」
「なるほど」
「一回十分、ラインビデオで話せるんだって」
「わかりました」
瞳は純一に言われた通り、メールでラインアドレスを送った。
すると数日後、施設から早速ラインがあり、面会日時が決められた。瞳はドキドキしながら、休みの日に施設のラインビデオと繋がった。
画面に、前回とおんなじステテコをはいた父が現れた。
が、何だか様子が違う。ぼーっとしていて、目も虚ろだ。介護士さんに、
「田中さーん、娘さんですよ~」
と優しく声をかけられても、変な方向を向いている。
「やだ田中さん、こっちこっち。画面に娘さんが映ってますよ~」
父親は、画面に向かってニッコリ微笑み、
「これはこれは、可愛らしいお嬢さんですな」
と言った。
「やだ田中さん、娘の・・・えーっと」
「瞳です」
「瞳さんですよー」
そういわれても、父は、もう瞳が娘であることも分からないようだった。
画面越しにニッコリと微笑み、
「そう~、瞳さんって言うの。可愛い名前だね」
とまで言う。
前回あった時から一カ月もたっていないのに、こんなに早くボケが進むものだろうか。
「今日はちょっと調子悪いみたいですね。また日を改めましょう」
介護士さんはそう言って、ラインビデオを切った。後からラインで、認知症は行ったり来たりするので、日によって分かる時もあるから、また面会の日時を決めましょうとあった。
瞳は父親が、ほんとうに、冗談ではなく自分が分からなくなっていたことに、衝撃を受けた。父はほんとうに、あれが最後で、どこかに行ってしまったのだ。肉体はまだ地上にとどまっているが・・・。
瞳は途端にそわそわし、いてもたってもいられなくなって、再び故郷の地を訪れた。あの家も、あれが最後だったのだろうか。あんな古屋に未練もないが、どうなっているのか確認せずにはいられなかった。
地下鉄で急行し、現場に走った。スローランだが、走り慣れているのでいざというときには走れる瞳だった。
汗が滝のように流れて来る。汗が目に入り、前が良く見えない。
しかしバッグからタオルハンカチを出す余裕もない。
マスクで汗をぬぐいつつ、走り続けた。現場は、更地になっていた。
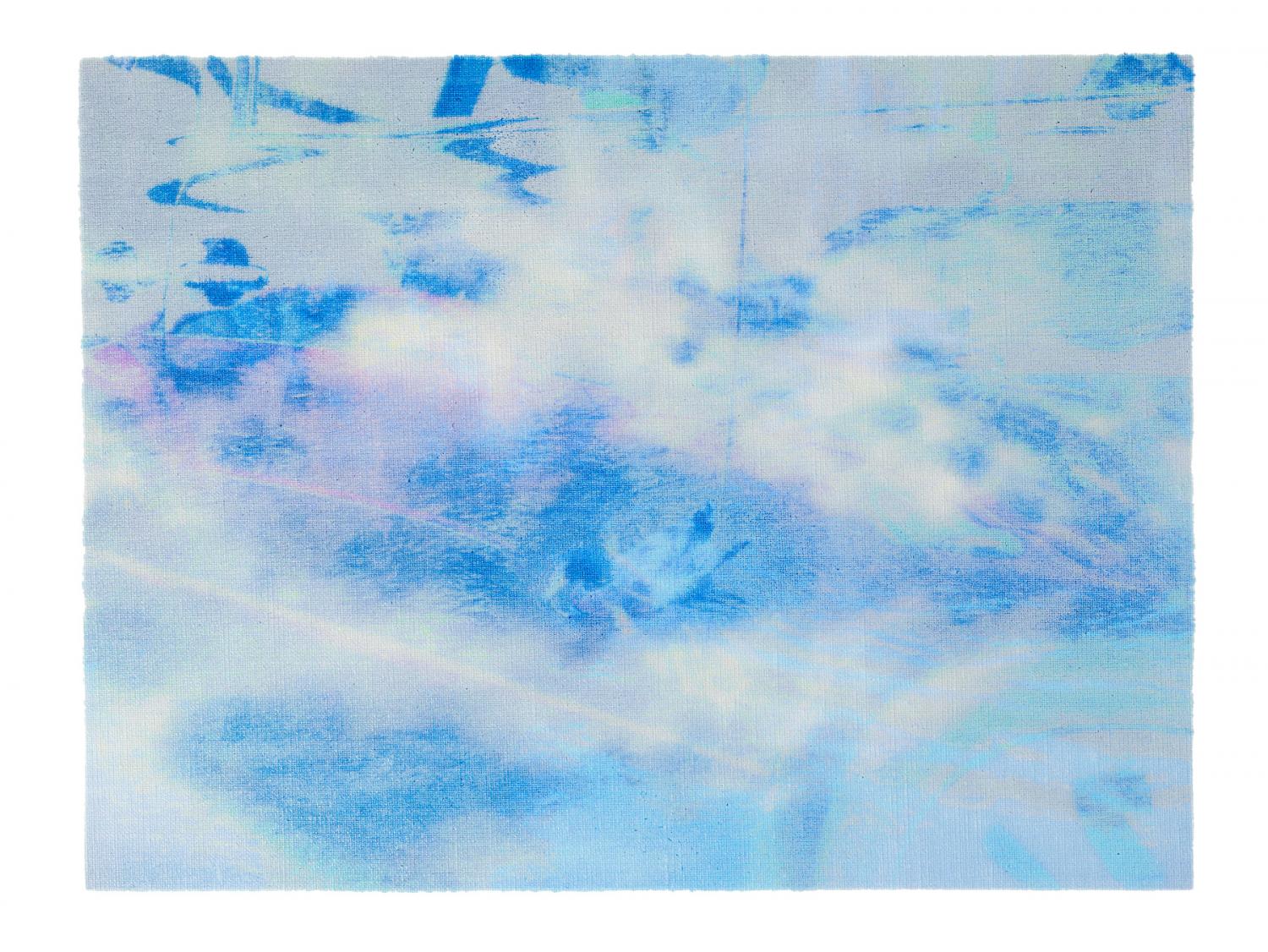
©︎AMU(フォトグラファーユニット.KNIT)
「純ちゃん仕事、早っ・・・」
瞳はとぼとぼと、今は無き実家を後にした。
「せっかくここまで来たから、買い物でもしてくか」
拍子抜けついでに、商店街はお休みだった。
そもそもつぶれている店が多いシャッター通りだが、今日はシャッターが全部下りている。
「あ、今日水曜日か。はぁ~」
水曜日はこの商店街の定休日なのだ。
全身汗だくで、喉はカラカラ、トイレにも行きたくなってきた。
まだ昼間だが、な、生ビールが飲みたい。緊急事態宣言は月末まで延長だったが、この辺りならだしている店があるはずだ。
記事が続きます
商店街を抜けると、見たこともない新しいカフェがあった。
覗くと、昼から酒類の提供もしているようだ。瞳は入店し、
「生ビールください」
と注文した。すかさずトイレに急行すると、
「あ、今使用中です」
と店主。そのときトイレのドアが開き、出て来た男が、なんとお茶屋のケンちゃんだった。
「え、田中?」
ケンちゃんはご機嫌だった。
「ぷっ、酔っぱらってる?」
午後三時だ。
見ると、トイレ横の四人掛けテーブルが、酒盛り状態となっているではないか。
「何時から呑んでんの?」
「いや今日商店街休みだからさ、昼間っから」
なんでも休みの日には商店街の若年寄たちが集まって、ランチミーティングをしているのだという。
「田中もこっちおいでよ」
空いてる席を指さす。
「え、いーよいーよ。私トイレ行って一杯飲んだらすぐ出るからさ」
「んなこと言わずにこっちゃこいや」
酔っぱらったケンちゃんに腕を引っ張られ、びくっとした。
誰かに体を触られるのも、久しぶりの事だった。
「トイレ行って来ていい?」
「あ、そーだ、行って来な」
瞳はトイレに行き、用を足してから化粧を直した。
一応、男が三人いるから、身だしなみだけは整えなきゃと。
「お邪魔します・・・」
瞳は、昼間からべろんべろんになっている男たちの席に座り、ちんまりと生ビールを飲んだ。ぷはーっ、外で飲む生ビールが貴重な今、こんなにも美味しいものか。
「はい、それ終わったらこっち飲めや」
と言って、ケンちゃんがレモンサワーを差し出す。
テーブルには焼酎のキ―プボトルと炭酸水、カットレモンが山ほど置いてあった。
つまみのあたりめや柿の種も。
「いやいやいや、昼間からそんなん呑んだら、帰れなくなっちゃうからさ」
「え、実家あんじゃん」
「もう更地になっちゃったよ」
「へっ、そうなんだ。じゃうち泊まってけば?」
「えー、悪いよ、ご家族もいるでしょうし」
「お袋だけだから心配すんなっ」
ケンちゃんは胸を叩いた。
「こう見えて独身だ」
「えー! この年までお一人で?」
「そーゆーお前はどーなんだよっ」
「悪かったな一人モンだよ」
わっはっはっは~と、独身談義が始まった。
ここに集まる若くもない若旦那衆は全員、独身だった。
なんて不毛なんだろうと、瞳は思った。
高齢化する商店街を、こいつらが復興出来るとも思えなかったが、昼から酔っぱらったオジサンたちが、
「俺がもらってやるよ」
「俺も余ってるから」
とオバサン相手に言い合う姿が面白く、そのうちの誰とも結婚する気にはなれなかったが、瞳は、泣くのを忘れて酔いしれた。
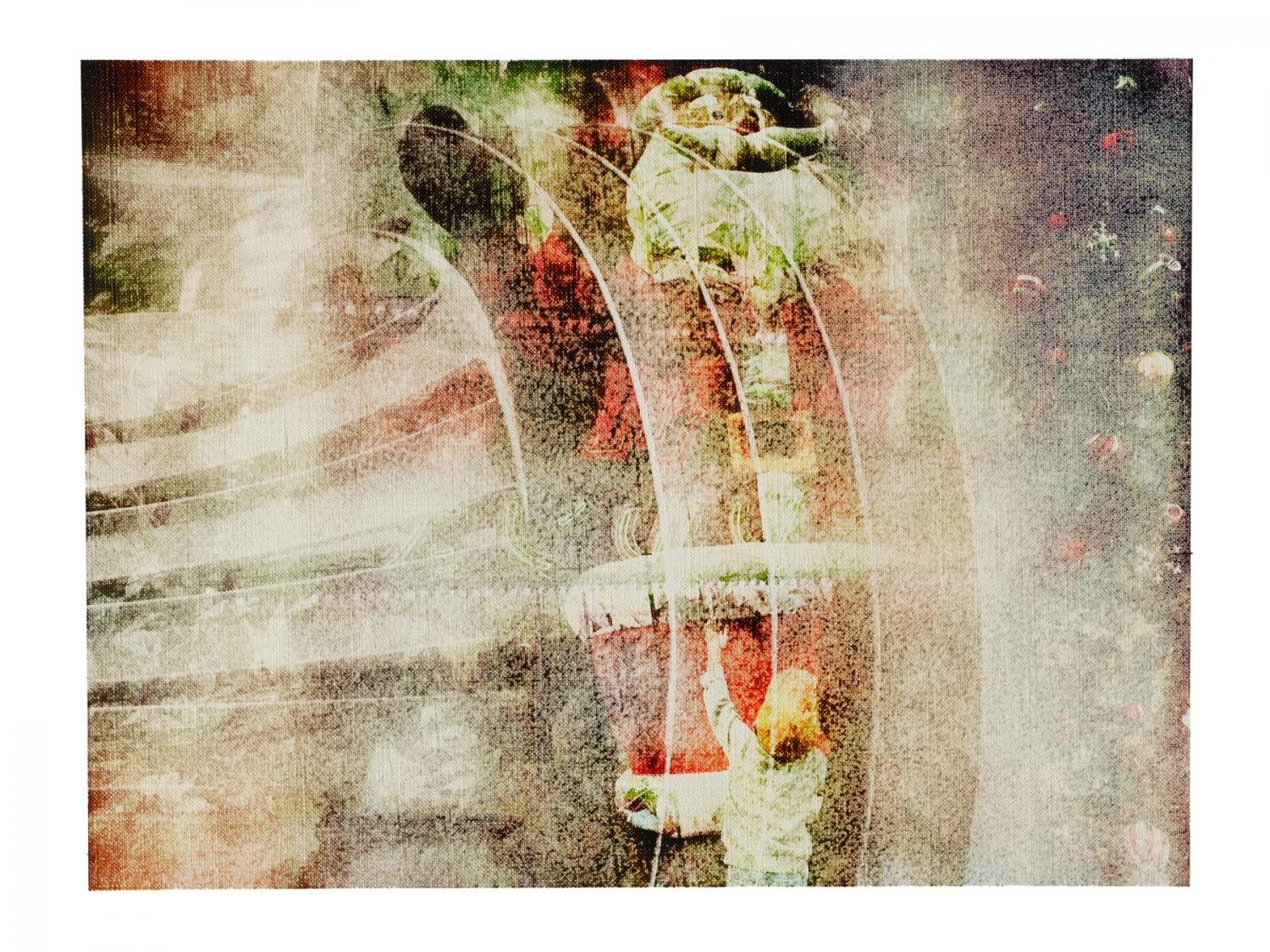
©︎AMU(フォトグラファーユニット.KNIT)