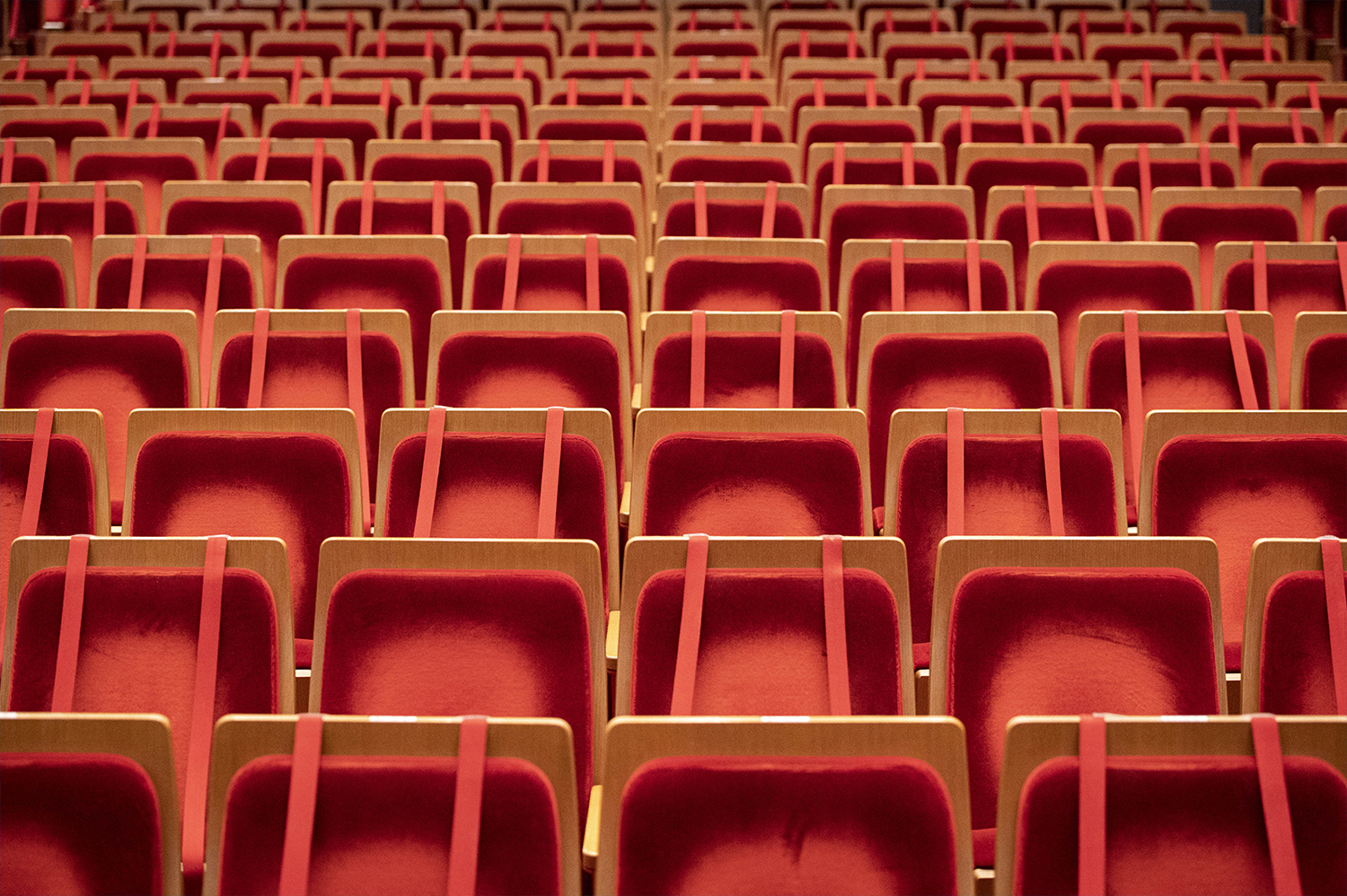最終話 ひな祭りのプレゼント
二月の終わりには、オミクロン株感染者数も徐々に減ってきていた。
「今年はお袋が、瞳のためにお雛様飾りたいって言うから、倉庫から出したんだよ。ちらし寿司作るっていうから、寄ってやって」
とケンちゃんが言うので、瞳は三月三日、お休みを取った。
お母さんが嫁に来るとき持参したお雛様だという。子供は息子二人だから、ずっとお蔵入りしていたものだ。次男のところに孫娘が出来たとき譲ろうと思ったのだが、気に入らない嫁に、
「うちは狭いから五段飾りは無理なんです」
と断られ、お雛様とお内裏様だけの内裏雛を贈ったのだという。それでも大きいと文句をたれられた。飾るところがないと。それは自分の息子の、立派な雛飾りを飾れるだけの大きな家を用意できない甲斐性のなさを詰られているようで、ますます、お母さんは彼女を嫌いになってしまったのだという。
確かに、今風の家には五段飾りを設置するスペースなどないだろう。ケンちゃんちは昔ながらの日本家屋だから、一階に居間とそれに続くお母さんの寝室があり、五段飾りを飾る場所もある。
「襖開ければ十四畳あるからね・・・」
瞳は一人ごちた。
しかしそういう物理的な問題ではなく、お母さんの気持ちを酌んであげない嫁がいけないのだ。瞳は、ケンちゃんママとの付き合いの中で、ずっと捨ててきた思いやりの気持ちを思い出していた。
「こんにちは!」
木戸をカラカラと開け、瞳はケンちゃんちを訪ねた。
「あー、瞳さん、よく来たね」
お母さんは割烹着姿で、嬉しそうに瞳を出迎えた。
「さあ、あがって。今、お吸い物作るからね」
台所から、はまぐりのお吸い物のいい香りが漂ってくる。食卓の上には菜の花のお浸しと、塗りのお椀、ちらし寿司が用意されていた。
「じゃ、ちょっと洗面所お借りします」
「はいはい」
瞳はうがい手洗いを済ませ、台所に戻った。
「お母さん、これ、甘納豆入り雛あられ」
「あー、美味しいやつね。ありがとう。やっぱり甘納豆入ってないとね、雛あられは。最近あんまりないんだよねぇ」
「そうなんですよね。御徒町行って買ってきた」
「ありがとありがと。じゃこれ、まずお雛様に上げてきて」
そう言って、お母さんは小さい器にちらし寿司を盛り、瞳に渡した。
「はーい」
居間には、古い五段飾りが設えてあった。最上段に男雛、女雛。二段目に三人官女。三段目は五人囃子。四段目にお道具。その両脇に、若い男と、おじいさんがいる。
「これは誰・・・」
瞳がちらし寿司を持ったまま立ち尽くしていると、お母さんが後ろから来て笑った。
雛あられをお供えしながら説明する。
「右大臣、左大臣。おじいさんが左大臣で知恵者、右大臣が若者で力持ち。いざというときに守ってくれるんだよ」
「五段目は?」
瞳の五段飾りも実家にはあったが、小さい頃は興味もなかったので、知らないも同然だ。
「仕丁。出かけるときのお付きだね。泣き上戸、笑い上戸、怒り上戸って、賢一の仲間みたいだろ?」
お母さんはそう言って笑った。
「で、これはどこにお供えすれば?」
「お雛様とお内裏様の間だよ」
「あーね」
桃の花も飾ってある。お母さんは仏壇にもちらし寿司をお供えし、瞳に、
「おひつと取り皿持ってきてくれる?」
と頼んだ。一緒に台所に行き、お母さんははまぐりのお吸い物を運んだ。
お雛様の前には炬燵があり、そこに二人で座った。
なんだか、もともとここが瞳の実家であるようなあたたかさだった。
記事が続きます
「さあさ、食べよ食べよ」
「いただきます(^^)/」
寿司太郎を混ぜたであろう甘いご飯に、金糸卵、ピンクのでんぶ、三つ葉と茹でた海老が散らしてあった。
「美味しい」
「そ、良かった。あとで店にも持ってってやってくんない? 賢一お腹空かせてるだろうから」
「はい」
今日はそのつもりで、弁当は作ってこなかった。
「あ、そうか。お吸い物どうしようかね」
「保温ジャー、持ってきてます」
お母さんがそう言うと思い、瞳はスープジャー持参で来ていた。家族に温かいものを食べさせたい。その気持ちは同じだ。
「あんた気が利くねぇ。じゃあとでそれに入れて持ってってやって」
「はい」
瞳は止まらなくなって、パクパクとちらし寿司を食べた。誰かに作ってもらうご飯は、こんなにも美味しいものか。
お母さんは少ししか食べないから、すぐに食べ終わり、立ち上がった。
寝室の箪笥の上の小引き出しから何か取り出すと、
「瞳さんこれ」
と古臭いビロード貼りの小さな箱を差し出す。
「え?」
「ひな祭りのプレゼントだよ。うちは女の子がいないから、瞳さんにあげる」
「え~」
開けると、そこにはでっかい、古い、翡翠のくりぬき指輪が入っていた。
「嫁に来たとき、お義母さんにもらったもんだよ。健康、長寿の石だから」
「えー、そんな、大切なもの」
「大切なものだからあげるんじゃないか。はめてみて。ちょうどいいと思うよ」
「はい」
瞳は言われるまま、その指輪をはめてみた。人差し指、中指には入らない。
薬指にはめると、ピタッとはまった。
「いいねぇ、きれいだねぇ。やっぱあんた、手がきれいだよ」
お母さんは嬉しそうだ。
「なんだかすんません」
「いいよいいよ、どうせそんなもん、私も長年してないしね。死んだら私の着物や宝石やなんか、ぜーんぶ瞳さんにあげるから」
そう言ってお母さんは、保温ジャーをもって台所に去った。
「・・・・」
瞳は、翡翠の指輪のはまった自分の指をしげしげと眺めた。
それはまるで、長年そこにあったかのように、しっくりと似合っていた。
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
「mist」シーズン6は近日公開予定。お楽しみに。
◆「mist」のこれまでのお話は、こちらでお読みいただけます。
◆撮影/初沢亜利 写真集「東京 二〇二〇、二〇二一。」より。