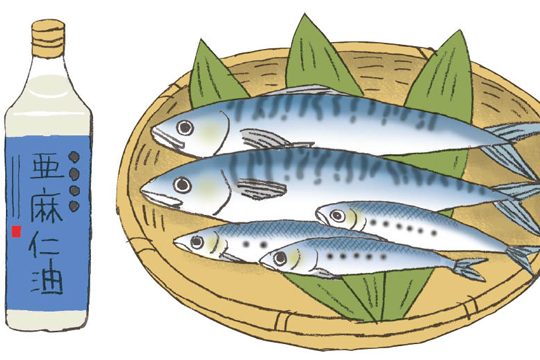日々読んだり書いたりしているうえ、趣味というか習い事がヨガとピアノ。考えるまでもなくインドア派の私ですが、それだけにアウトドア派への憧れはかなり強いものがあります。
「今のこの私では無理だけど、生まれ変わったら山を歩いたり登ったりして、すばらしい景色を眺めてみたい!」
と、よく思う。
その昔、家族のひとりが登山をやっていたのですが、帰宅したとき疲労感とともに「すごいものを見てきたぞ」オーラが出ていたことも、憧れる理由のひとつかもしれません。
だから北村薫さんの『八月の六日間』が“働く山女子”小説だと知ったとき、すぐさま「読まなきゃ!」と思ったのですが、さらに後押ししたのが取材でお会いした書店員さんの「これ、すごくいいですよ……」という言葉。
「すごくいいですよ……」って抽象的な言葉ですが、読み終えたとき彼女の「……」部分の意味がわかった気がしました。
多分、心に残る部分は人それぞれ。いつの間にか自分の人生を重ね合わせて読んでしまうので、何とも言えない余韻が残るのです。

『八月の六日間』
北村薫 角川書店 \1500(税別)
現在は角川文庫 ¥640(税別)
仕事でも私生活でも、疲れることが多いアラフォーという年齢。“わたし”もそんな時期を迎えていたが、山と出会い、大自然に心を開くようになったことで、何かが少しずつ変わっていく。元恋人と意外な出会い方をする後半に注目!
『八月の六日間』は連作短編集。表題作のほか、「九月の五日間」、「二月の三日間」、「十月の五日間」、「五月の三日間」が収録されていて、その名の通りの山登りの行程が描かれています。
主人公は40歳目前の文芸誌副編集長“わたし”。誠実に仕事をしてきたけれど、不器用な性格でもあるので、公私ともに(どちらかというと心が)ややお疲れ気味でした。
そんなとき、同僚の藤原ちゃんから「明日。山、行きませんか」と誘われます。初心者もハイキング気分で登れるコースで、季節は秋。
そこで紅葉のアーチを見た“わたし”は
「空から降って来るのは、素朴なのに荘厳さを感じさせる光。色がそのまま音楽だった。めったに、つんとはしない、させない涙腺が、何だか緩みそうになった。」
初めて行った山でそこが心を開いてくれる場所と知った“わたし”はトレーニングを積み、休暇に登山をするようになります。
基本的にはひとりで行くのも“そのほうがより心が開くと感じるから”でした。
彼女が目指したのは槍ヶ岳や常念岳ですが、雪の裏磐梯を歩くツアーに参加したことも。
ひとりにしろツアーにしろ、黙々と足を運ぶ時間がほとんどです。絶景に見入ることもあるけれど、ずっと気分よく進めるとは限りません。
というか、働く女子だけにぎりぎりまで仕事をしていることも多く、ときには睡眠不足を感じながら歩き始めることもあります。
最初は調子がいいと思っていても、途中から「あれ?」みたいなこともあります。
だから彼女の胸の内はほとんどの場合、期待と不安がないまぜ。
そんななか時折頭をよぎるのは高校の演劇部での苦い経験やかつての恋人のこと、少し前に亡くなった親しい友のことなどでした。
それらはすべてどうしようもないことです。逆に言えばだからこそ、それらをどう心にしまえばいいのか、いつの間にか考えてしまうのでしょう。
別れた恋人と亡き友人に関しては特に、彼や彼女のいない人生を受け入れなければならないという事実に、どこかたじろいでいる感じがあります。
そしてそのことは、“わたし”の心の深い部分に痛みも与えているようで……。
“わたし”は何らかの答えを探すために山に登っているわけではないけれど、日常とは違う場所に身を置き、からだに負荷をかけながら目標に向かう経験を重ねるうちに、考えることが少しずつ変わっていきます。
そして現実のとらえ方――例えば職場の“困ったちゃん”の対処法などにも、どことなく変化が……。
自分のことを若干へんくつだと思っている主人公ですが、彼女の周りにはその個性を認め、いい距離感でつきあっている友人・知人がいます。(特に元上司の女性!)
また山に行けば、その場限りの出会いでも、かけがけのない印象を残してくれる人がいる。ハッとするような言葉をかけてくれた人と、メアドどころか名前も告げ合わないまま別れることだって多いのです。
「これぞ山の素晴らしさ!」と、行ったこともないのにしみじみ思いました。
人との交わりって、長さや頻度が重要ではない。ピンポイントでも一生の宝になるような出会いがここにはあるんだ、と。
簡潔な文章で描かれ、説教がましいところなどないけれど、「人生とは、友とは、過去との向き合い方とは」と何度も考えさせられる小説です。
とにかく“傷つかずにすむよう、自分の感受性をごまかす”なんてことをしないで生きていこうとする主人公がすがすがしい! ちょっとナイーブだけど……。
この2年ほどの間に3回読みましたが、そのたびに胸を打つ箇所が少し違ったのは、私自身が微妙に変化しているからかもしれません。
だからこれからもきっと何度も読み返すはず。そんな本に出会えたことに、心から感謝しています!

『飲めば都』
北村薫 新潮文庫 \670(税別)
北村作品で女性の文芸編集者が主人公といえばこれもそうだが、本作の小酒井都は若手。小説への愛は深いものの、お酒が好きすぎてトンデモナイ失敗をやらかすことも……。ツワモノぞろいの先輩たちとともに働き、飲み、恋をする都の姿が痛快な、お仕事女子小説