いつのまに私たちは・・・
仲の良かった従姉の亜希が、脳梗塞で倒れた。三つ年上だから、五十七歳だ。小さい頃から親族自慢の美人で、誰に対しても優しかった。大学の先輩と恋愛して卒業と同時に結婚、専業主婦になっていた。
夫はエリートサラリーマンだから海外赴任もあったりで、専業主婦にならざるを得なかったのだ。一人息子も商社マンとなって、いまだ自宅住まいだ。今年の春から二人ともコロナでリモートワーク。もともと料理が好きで家にいるタイプだったが、家族三人が三食家で食べる生活になって、大変だったのではないだろうか。
亜希が倒れたのを発見したのは、息子の康介だった。週に一、二回、出社せねばならない日があり、この日は、夫も康介も出社日だった。夫よりも早く帰宅した康介が、
「あー、腹減った、夕飯なに?」
と、いつものようにリビングに入ると、キッチンカウンターに母の姿はなかった。
「ん? 母さん?」
慌ててキッチン内を確認すると、そこに亜希は倒れていたのだ。裏庭に続くサッシのドアから、西日が差し込んでいた。
「さっちゃん? 亜希が、入院したの」
「え?!」
叔母の弘江から電話がかかって来た。
「脳梗塞だったみたい。台所で倒れてたんだって」
「うそ・・・」
「康介が発見したときにはもう四時間ぐらいたってて・・・」
叔母は電話口で涙ぐんだ。
「まだ意識が戻らないの」
「やだ、そんな・・・」
涙が込み上げてくる。
「ほら、今コロナで私らお見舞いにも行けないじゃない? さっちゃんに心配かけたくなかったんだけど、いつどうなるか分からないから・・・」
「・・・・」
脳や心臓血管系は、発見が早くて処置が早ければ助かる可能性が高いと聞いたことがある。四時間もたっていたら・・・。
「病室には家族しか入れないの。それも何かあった時だけって」
「え、じゃ着替えとかなんかは?」
「完全看護だから病院のほら、前開きの着せられてて、いらないんだって」
高齢者である叔母は、まだ元気だがこのコロナ禍において病院には近づないほうが良いだろう。しかし、いつ死ぬかもしれない娘に何もできないとは・・・。
「おばちゃん、しっかりしてね。私、靖さんに電話して、詳しいこと聞いてみるわ」
佐知は電話を切って、亜希の家に電話をかけた。亜希の元気な声で留守番電話のメッセージが流れ、電話には誰も出なかった。
「もしもし、佐知です。おばさんから亜希ちゃんのこと聞きました。詳しいこと聞きたいので、電話ください」
迷惑だろうなとは思いながら、そうメッセージを残して、電話を切った。
しばらく茫然と、リビングに立ち尽くした。窓からは西の空が見える。陽が短くなってきているから、緋色の空は次第に紫になり、やがて帳を降ろした。それは、何かを物語っているようだった。
私たちは、いつのまに死を意識する年齢になってしまったのだろう。想像もつかなかった現実が、今、佐知の前に立ちはだかっていた。
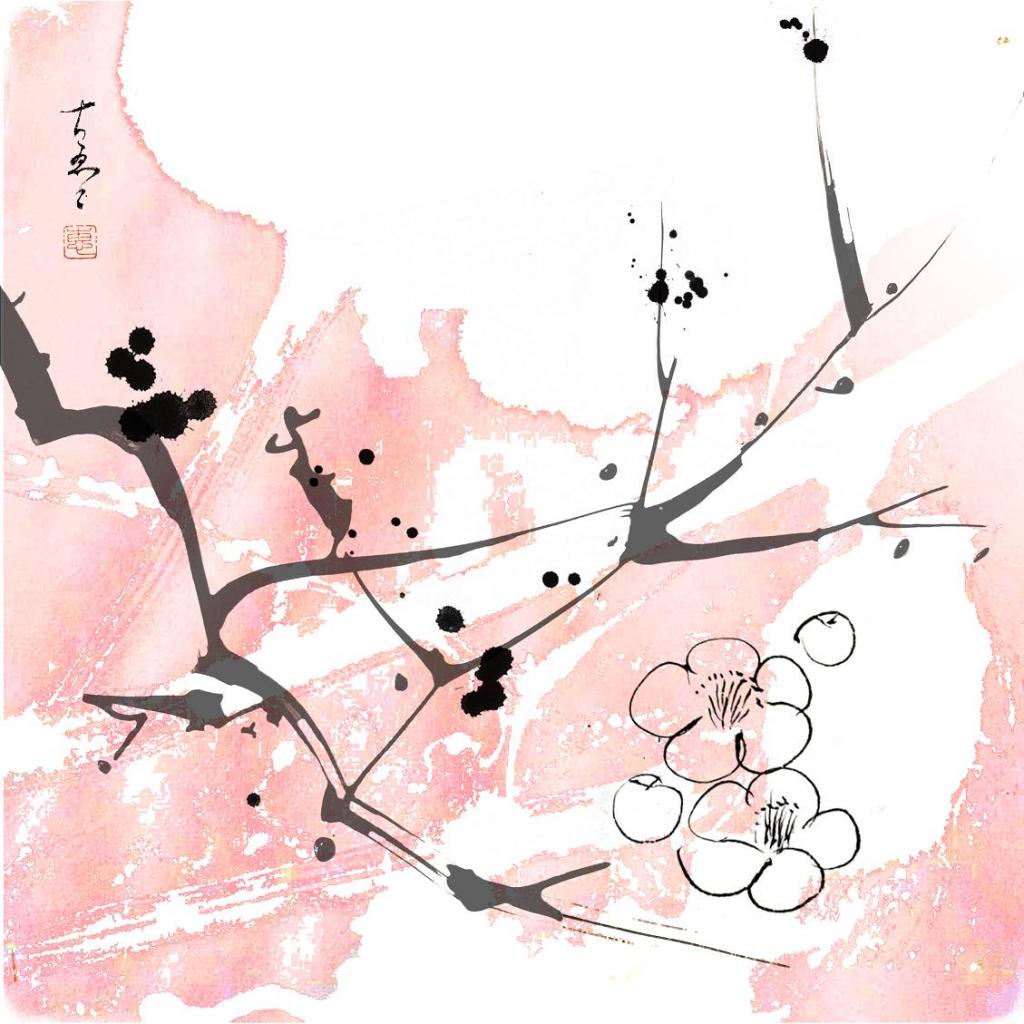
イラスト/原知恵子
次回は、3月11日配信予定です。お楽しみに。





























