第3話 既婚者の友達
瞳の家から東京タワーまで、ひとっ走りするにはちょうどいい距離があった。
東京タワーの麓には大きな木がたくさん植わっている。
その木陰でストレッチしていると、
東銀座のバーでバイトしていた頃の友達、佐知さんからラインがあった。
「今いる?」
「いないー。ランなう」
瞳は短大に入学してすぐバイトを始めたが、佐知さんは四大を出て就職してからだったから、ちょっと年上だ。ハスキーボイスとスレンダーな体が素敵なお姉さんで、瞳はすぐに懐いた。佐知さんが留学していた時はロンドンまで遊びに行ったし、帰国後も妹ぶんとして交友が続いていた。
「いまお参りの帰りなんだけど、豊川稲荷のお稲荷さん、瞳の分も買ったからさ、届けるわ。どんくらいで戻る?」
「えー、嬉しい! あそこの美味しいんだよね。あと三十分ぐらいで戻るよ」
「りょ」
慌てて走り戻ると、マンションの入り口に佐知さんちのでかいVOLVOがあった。
旦那が運転席にいる。外資系金融業にお勤めの旦那さん、金持ちで外面はいいが、内弁慶でケチらしく、よく愚痴ラインが来る。走っている間もビシバシ来ていた。
「マジ朝から大変だったよ。まず目黒不動参拝からの、豊川稲荷でしょう? 参り方にこだわりがあるから、いちいち時間かかるしさー。二礼二拍手一礼するの、横並びで同時にしなきゃなんないんだよ(# ゚Д゚)」
「団体行動大変じゃのう」
「今度は富士山二合目の神社まで行くなんて言ってるの。どんだけお参りすりゃ気が済むっつーの」
助手席で、隣にいる旦那の悪口をラインしているのだから驚くが、助手席に乗っていて機嫌のいい奥さんを見かけたことないから、どこのお宅も似たり寄ったりなのだろう。
「息子は帰ってこないし娘は近所しか付き合わないからさ、豊川稲荷は二人でだよ。マジ死んだ。心が死んだ」
「ま、ラブラブっつーことでw」
マスクした小池百合子の顏に「密です!」と書いてあるスタンプが送られて来た。
車に向かって手を振ると、佐知さんが窓をあけ、パッと明るい顏になった。
「久しぶり~、元気してた?」
「うん、元気だよー」
旦那さんも会釈をしたが、苦虫をかみつぶしたような顏だ。きっと車内も、重苦しい雰囲気なんだろうな・・・。
「これこれ、お稲荷さんと、中目のフルーツサンド」
「えー、嬉しい。ダイワのフルーツサンド、食べてみたかったんだ」
並んで買う、流行りのフルーツサンド屋さんだった。
「買うの大変だったでしょ?」
「今朝は並んでなかったよ。早く行ったから。保冷剤入れてるから大丈夫だと思うけど・・・」
「私もあげるものあるから、ちょっと待ってて」
瞳はそう言い、部屋に走った。
記事が続きます
「また太ったわ、あの子・・・」
佐知は夫に呟いた。
「そうかな・・・ずっとあんな感じだろ」
「いやいや、太ったわよ。あの子、丸顔だからもともと太って見えるけど・・・コロナ太りじゃない?」
東銀座のバーで働いていたことは内緒だから、瞳は留学時代の友達ということになっていた。本当なら夫抜きでドライブして、立ち話でもいいからちょっとおしゃべりしていきたかったが、非常事態宣言下で単独行動は許されなかった。いやさ、休日はいつもがんじがらめだ。
休みの日の夫は、佐知が目の届く範囲にいなければ気が済まないようなのだった。昔はこんな男じゃなかったのにと、しみじみ今後が心配になる。空の巣になった先輩諸氏は、夫に付きまとわれて困ると言っている。
佐知は独身の瞳が羨ましかった。派遣で通販の電話受付なんてつまらない仕事と思っていたが、フリーランスに仕事がない今の時代、継続的にある仕事は羨ましい限りだった。しかも巣ごもり需要で、通販は右肩上がりだ。
親が残してくれた不労収入があって、バイトで小遣い稼ぎができ、一人なら、こんな鬱陶しい思いしないでも済むのに・・・佐知はマスクの中で下唇を噛みしめた。
「はい、これ」
瞳が走り戻って来た。ぴたぴたのランニングウェアで、全身の肉がふるふると揺れている。
「ハルマサでセールだったローストビーフ」
「え、すごーい。ありがとう!」
アメリカ産アンガス牛のローストビーフ。スライスしたら三十枚ぐらいは取れる塊だった。これが破格の値段で大放出されていたのだ。肉のハルマサは近隣の飲食店が仕入れに来る店だが、コロナで需要も減り、フードロス対策の大セールだった。
「火ぃ使うのも暑いからさ、これでローストビーフ丼でも食べて」
旦那さんも嬉しそうに会釈して、車は走り去った。
「豊川稲荷のお稲荷さん、美味しいんだよね」
さっきブランチしたばかりだが、走ったらすでに小腹が空いて来た。いただきものはまず母親の祭壇にお供えすることにしている。
「ちーん」
おりんがないので、口で言う。
ここのインテリアに仏壇は合わないから、お洒落な祭壇を暖炉の上に設えてあった。お線香も嫌いだから、短いインセンスを、蓮の形をしたインセンスホルダーで焚く。
働き者で、退職と同時に燃え尽きるようにして死んだ母。瞳はその生活を支える、家事手伝いという名の専業主婦だった。若い頃は服飾関係の仕事に就きたいという夢もあったが、母親の世話をするのが運命のような気がした。
苛酷な不動産業界でしのぎを削った母。サポートなしでは勤まらなかったし、わずか半年ばかりの闘病生活も、瞳がいなければ成り立たなかっただろう。
「うがい、手洗い、お稲荷さん♪」
細身のお稲荷さんが五つ入っている。それをサクサク食べながら、冷たい麦茶をぐびぐび飲んだ。
「この、黒ゴマがいいんだよね」
酢飯に黒ゴマが混ぜてあるのだ。添えてあるガリをカリリとやり、また食べる。
「美味しい♡」
勢い、五つ平らげた上に、フルーツサンドも行ってしまった。
「え、すごい。ほとんどパイナップル」
薄いパンと生クリームに、スティック状のパイナップルが入っている。
「冷たくて、夏のデザートにぴったり♥」
佐知さんと久しぶりに、一瞬だけどリアルで会えたことで、瞳の気分は一気に上がった。会いに来てくれたことが嬉しかった。
「よし、洗濯して掃除して、日が暮れたら韓ドラ見ながら一杯やっか」
猫たちにチュールをあげて、久しぶりに前向きな気持ちで家事に勤しむ瞳だった。
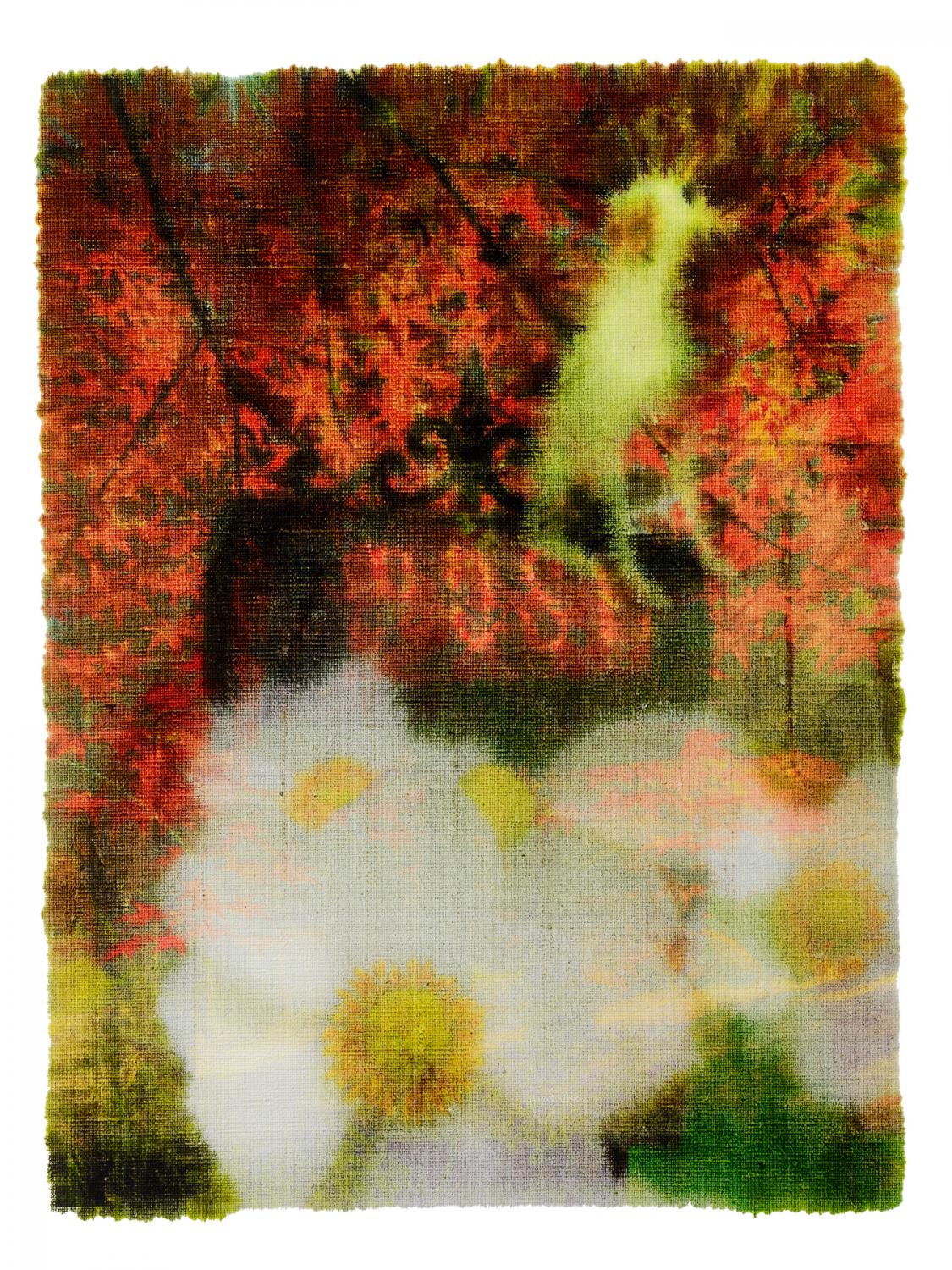
©︎AMU(フォトグラファーユニット.KNIT)
◆これまでのお話はこちらからどうぞ。「mist」シーズン1・シーズン2も読めます。






























