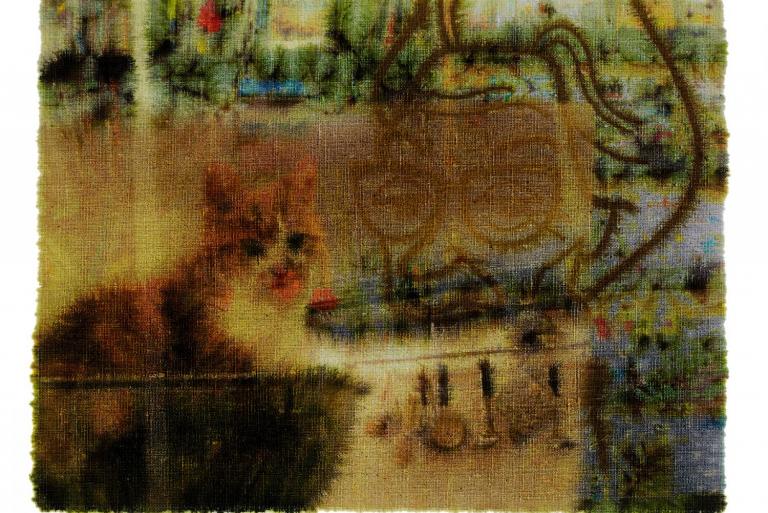第8話 二十年ぶりのお盆
二十年ぶりに足を踏み入れた実家は、古くはなっているものの、きちんと綺麗に整っていた。叔母が電話で言っていた、父の垂れ流しで凄い臭い、ではなかった。
かつて居間だった、そして夫婦仲が悪くなってからは父の寝室になった和室の仏壇には、ちゃんとお盆のお飾りが設えてある。
茄子やキュウリに割りばしを刺した馬、野菜籠、提灯・・・。
懐かしさが込み上げた。
祖母の遺影が微笑んでいる。瞳は線香をあげ、手を合わせた。
「さあさあ、こっちへ」
悦子叔母に呼ばれて、
「お邪魔します」
と、瞳は奥の台所兼食堂に向かった。
「やだよ、お邪魔しますなんて。おまえの家じゃないか」
叔母は眉間に皺を寄せた。父親はすでに食卓に座っている。
台所の入口にかけてある暖簾をくぐり、父のはす向かいに座った。
「ひーちゃんお昼ご飯まだでしょ? 冷麦でも茹でるから、食べて行きなよ」
「え、でも、二人とも高齢者だから、私はマスク外せないよ。まだワクチン打ってないし・・・」
「こっちはもう二人とも二回接種してるから大丈夫だよ」
「いやでも、ワクチンも100%じゃないっていうし・・・」
「水臭いこと言わないでさ、久しぶりじゃないの、みんなでごはん食べるのなんて」
確かに、誰かと食事を共にする滅多にない機会だった。
「じゃあ、サクッといただいちゃおうかな」
「そうしなそうしな」
台所で叔母が前掛けをかけ、支度をし始めた。
「これでも食べて待ってて」
冷蔵庫からスイカと麦茶を出してくれる。
「いただきます」
懐かしい風景だった。おばちゃんの後ろ姿、おばあちゃんにそっくりになったな・・・。
かつて、母が働き始めてから父方の祖母が一緒に住み始め、家事を担ってくれていた。祖母は綺麗好きで、家中を雑巾がけしてぴかぴかにしていた。
老人ホームに入るまで、家事をしながら一家を支えていたのだ。
結局父はなんにもできず、祖母いなくなったら、連れ合いに先立たれた妹を呼び寄せて、世話をしてもらっていたのだろう。
「これ、お土産」
「あ、どうもすみません」
父に手土産を渡すと、すまなそうに頭を掻く。
頭はほとんど丸っぱげで、風前の灯火のように毛が三本、生えていた。
どこかで見たことある・・・あ、おばけのQちゃん・・・。
「兄さんもなんだよ、他人行儀に」
氷水に放った冷麦を出しながら、叔母が言う。
「いただきます」
父親はそういうと、冷麦を勢いよくすすった。
たくさんのお辛味、冷ややっこや、商店街で買って来たであろう、天ぷらもある。
「ほら、ひーちゃんも食べなよ」
「はい、いただきます」
父親は麺つゆに天ぷらをつけて、麵と共にうまそうに食べている。
見とれるほどの食欲だった。
「・・・・」
この親父は本当にボケているのだろうかと、瞳は不思議に思った。
叔母が察してか、耳元で囁いた。
「今日は調子がいいんだよ。ひーちゃん来るからって張り切っちゃってさ。粗相がないようにって、オムツまで履いたんだから」
思わず吹き出しそうになったが堪えた。ウケてはダメだ。親父がいい気になる。
しばし沈黙が続いたが、苦し紛れに瞳はつい、誰かに喋りたくてウズウズしていたことを、普通にしゃべってしまった。
記事が続きます
「さっき駅で酔っ払いがさ、なんか変な札、ぴって、改札でかざして入ろうとしてんの。口でぴって、言ってんだよ笑っちゃった」
「バカな酔っ払いだなー」
二人は笑い始めた。
「駅員さんが来てさ、それは違いますって、真顔で注意してんの。それでもまだ口でぴっ、とか言って入ろうとするから、連れて行かれちゃった」
「パスモだと思ってるんだろうねー」
と悦子叔母。
二人とも楽しそうで、瞳もなんだか楽しくなってきた。
気が緩むと、膀胱がパンパンなことにも気づいた。
「ちょっとトイレ行って来ていい?」
「いいよいいよ、自分の家なんだから勝手に行きな」
台所横のトイレに入ると、そこは、昔と変わらぬ、敷石調のタイルが貼られた、和式トイレだった。水洗だが上に水溜があり、つり下がるチェーンを引っ張って水を流す昔ながらの方式だ。
こんなものが、壊れもせずまた残っているとは・・・瞳は驚いた。
「すげー、レトロ」
思わずつぶやきながら、用を足した
ある意味、遺跡だ・・・。
ここは自分の実家でありながら、そのカルチャーショックは、まるで開発途上のアジアを旅しているようだった。どこにも旅行に行けない今、久しぶりにワクワクしている。
用を足したあと、洗面所で手を洗った。
石鹸は、牛乳石鹸だった。何も変わっていない。
タオルは洗いざらしの、近所の工務店の薄いタオルだった。
「じゃ、デザートにスイカいただきます」
「はい、召し上がれ」
瞳がスイカにかじりつく様子を、二人は微笑んで見ている。
え、うそ、ナニコレ? 幸せじゃん。
瞳は心の中で、ぶるぶると顏を横に振った。
いやいや、そんなことをしに来たわけではない。本題に入らねば。
と思ったとき、父親が、白い縦型の封筒を差し出した。
「なにこれ?」
「遺書だ。今風に言うと、エンディングノートだ」
言わんでいい! 瞳は心の中で叫んだ。
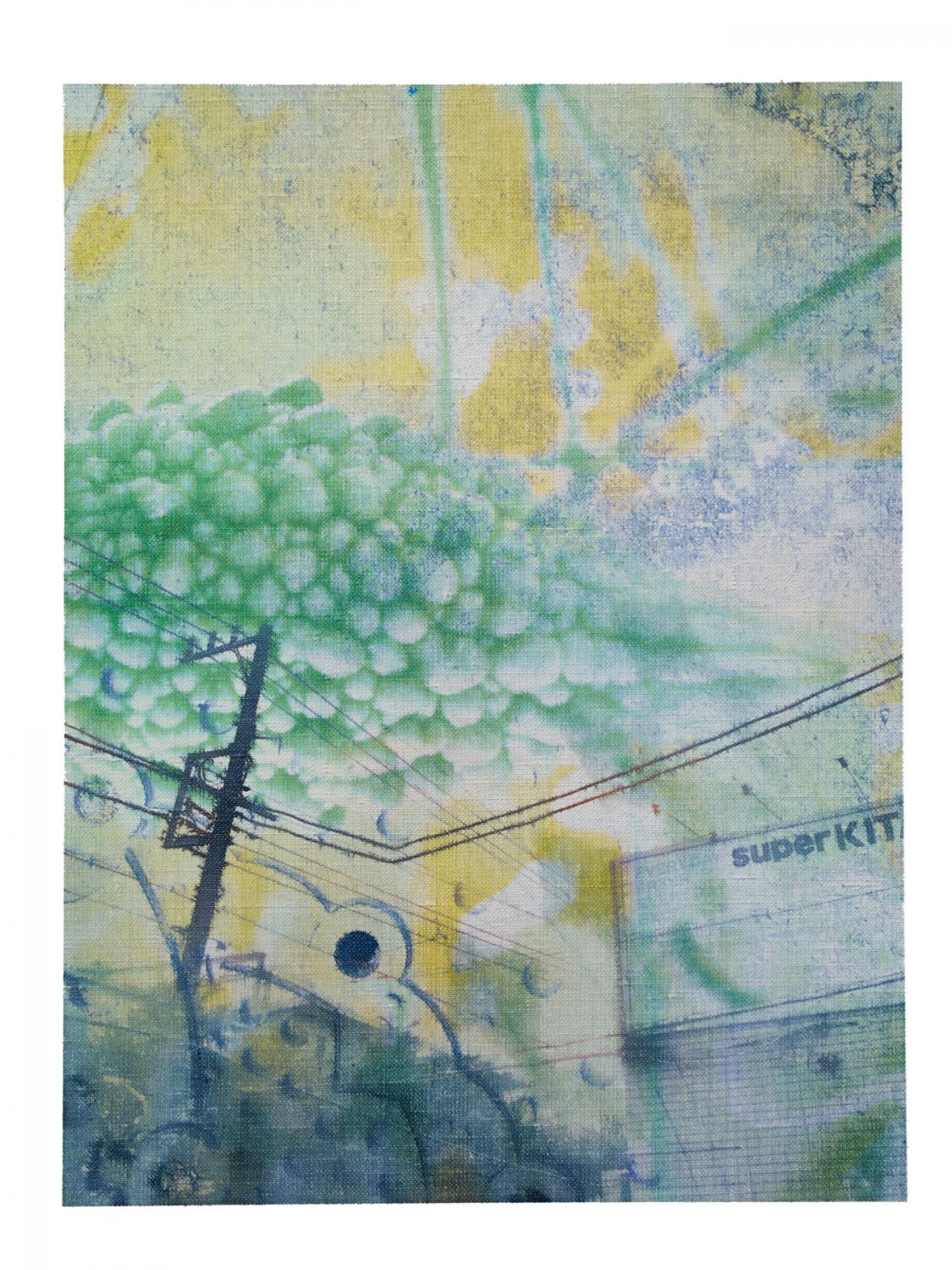
©︎AMU(フォトグラファーユニット.KNIT)
◆小説「mist」のシーズン1、2、3のここまでのお話は、こちらでお読みいただけます。
◆次回は、9月21日(火)公開予定です。お楽しみに。