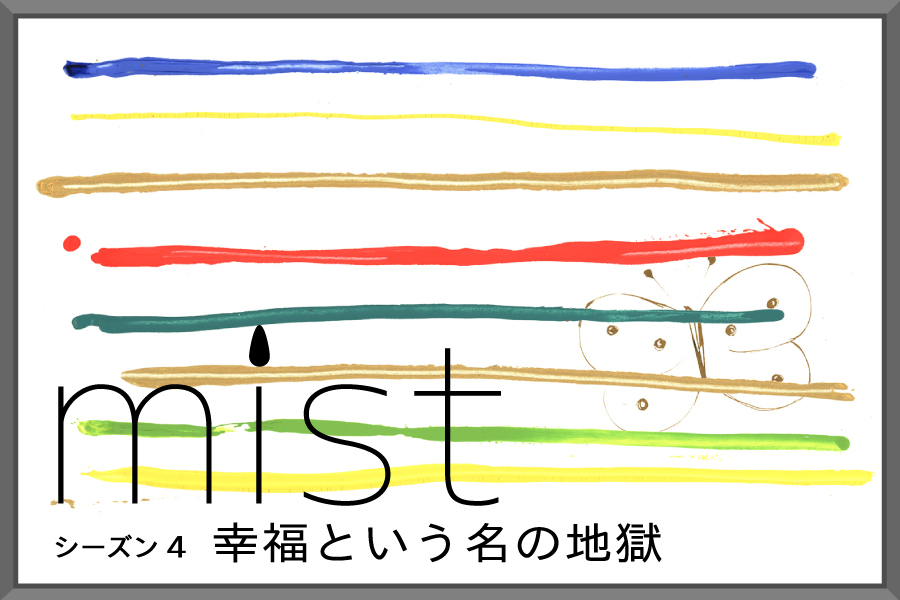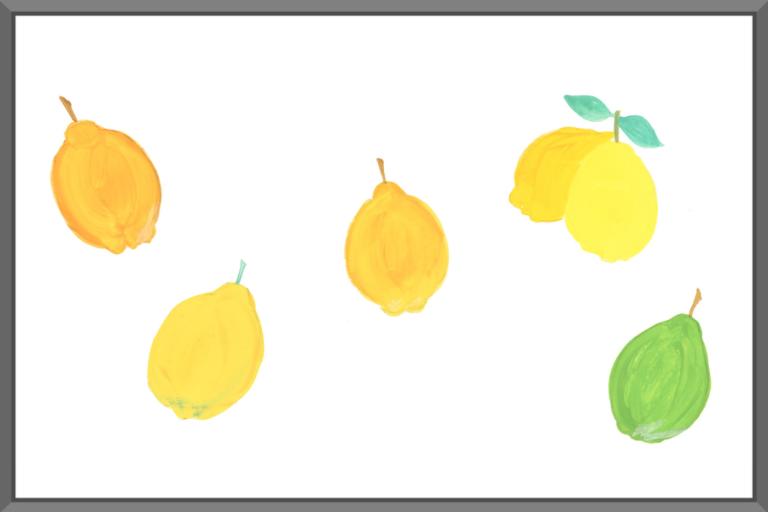第9話 心ここにあらず
母親が院内感染でそれこそ緊急事態だというのに、貴美子は幸せだった。
もし、「愛の不時着」に嵌っていなかったら、このストレスには耐えきれなかっただろう。
最も、一日中心配していたところで、何も出来ないのも事実だった。
もしものときのことを考えて準備するなど、それこそ不吉だ。
自分自身、こんなときにこんなことしていていいのかな? という気持ちもあったが、気分が落ちずにいられるという意味では、「愛の不時着」は頼もしい存在でもあった。
心配事があり機嫌が悪いと、夫の存在はますます不愉快だった。週の半分は自宅勤務だったり、時差通勤でうだうだしていたり、逆に夕方えらく早く帰ってきたりするのだ。
それなのに、家の事をやったり、母親の病院に代わりに行ってくれたりはしない。小学生の子供みたいに、次のごはんを楽しみにしているだけだ。
のみならず貴美子のいないときはこともあろうに、「ネットフリックス」で「全裸監督」を見ているのだ。
ある日、病院から貴美子が帰ってくると、リビングから女の喘ぎ声が聞こえた。
夫は焦ってテレビを消し、
「お帰り~」
とそらぞらしく貴美子を出迎えた。
不信に思って裕太の視聴履歴でそれを発見したとき、
「ったくいやらしい・・・」
と、貴美子は呆れた。
八十年代のポルノビデオ監督の話だ。男って、何歳になってもホントいやらしいっ。
「おぞ~っ」
女性ホルモンが枯渇してからまるで少女のようになっている貴美子は、身の毛がよだつ思いだった。
「だいたい、裕太のアカウントでそんなの見たら、息子にだってばれちゃうじゃない」
そうなったら父親の威厳はどこに・・・。
しかしそれを指摘すると、烈火のごとく怒ることは目に見えているので、ほっておくことにした。
もともと、優しくて何があっても怒ることがない男だったが、年を取って変わった。黙って好きにやらせていればご機嫌なのだが、一つでも何か言うおうものなら、激怒し、いじけて数日機嫌が悪くなるようになった。
そうなると貴美子も気分が悪いので、ほっとくのが一番だった。
今日は出勤日だったから、貴美子はほっとしていた。やった! これで午前中家のことを済ませ、母親の病院に行って、スーパーに寄って買い物を済ませば、夕方一人で「愛の不時着」が見られる。
美味しいコーヒーを淹れて・・・。
それを考えるだけで、気分が良くなった。「愛の不時着」の中で主人公ジョンヒョクの兄が生前、弟のことを「あいつのことを思うと気分が良くなる」と言っていた。
夫はその真逆で、あいつのことを考えると気分が悪くなった。
「行って来まーす」
夫が上機嫌で玄関を出て行く。
「行ってらっしゃーい」
貴美子はそう声をかけて、心の中で言った。
「帰ってくんなー」
それもまた困るけど・・・と思い直して、
「できるだけ遅く帰って来いよー」
と言い直した。
「へっへっ」
貴美子はほくそ笑み、早く、確実に家事を済まそうと気合いを入れた。
記事が続きます
洗濯物を干していても、米を研いでいても野菜を洗っていても、掃除機をかけていても雑巾がけをしていても、いやさトイレ掃除のときですら、「愛の不時着」のシーンやセリフ、登場人物を思い出すと、笑みがこぼれた。
北の村のおばさんたち、ジョンヒョクの部下の男の子たちを思い出してはクククと笑った。北と南、財閥一家の恐ろしい策略や攻防の中、ほっと一息つけるコメディタッチのシーンがあるので、貴美子は飽きずに見ることが出来た。
これが、純愛だけだったり、サスペンスアクションだけだったら、こんなにも嵌っていなかっただろう。「愛の不時着」は、貴美子が嬉しいご馳走がてんこ盛りだったのだ。
「愛の不時着面白すぎる~」
貴美子は瞳にラインした。
「今どこ?」
「もう十一話だよ、もうすぐ終わっちゃう」
「まだまだ楽しめるよー」
「終わっちゃったらどうしよう?」
「大丈夫。オススメたくさんあるから」
瞳は韓流ドラマファンもう十年以上だから、そして一人暮らしだから、それはそれはいろいろ見ていた。自分自身の恋愛が終わってから、韓流に嵌ったのだ。
貴美子は遅咲きだが、コロナ禍において、韓流ドラマをもっと早く知っていたら、一年間あんなに苦しむこともなかったかもしれないと思った。
コロナ以前に、そしてコロナ禍も、瞳はいつも機嫌がよく、貴美子が愚痴を聞いてもらっていた。独身で派遣で働く瞳を、不安じゃないのかなぁと不思議に思っていたが、その秘訣が韓流にあったとは!
一番嫌だった夫とのドライブの最中でも、「愛の不時着」のシーンを思うと、楽しくなれた。話下手な夫の息苦しい無言の時間も耐えられたし、無理に絞り出すつまらない話も、我慢出来た。適当な返事をして、聞き流し、心は「愛の不時着」に飛んでいる。
一話が長いからかなり見ごたえはあったが、たった十六話で終わってしまったとき、貴美子は、それまで毎日わくわく暮らしていたのに、風呂を洗いながら、
「あー、つまんねー」
と口走ってしまった、自分に驚いた。

イラスト/押金美和