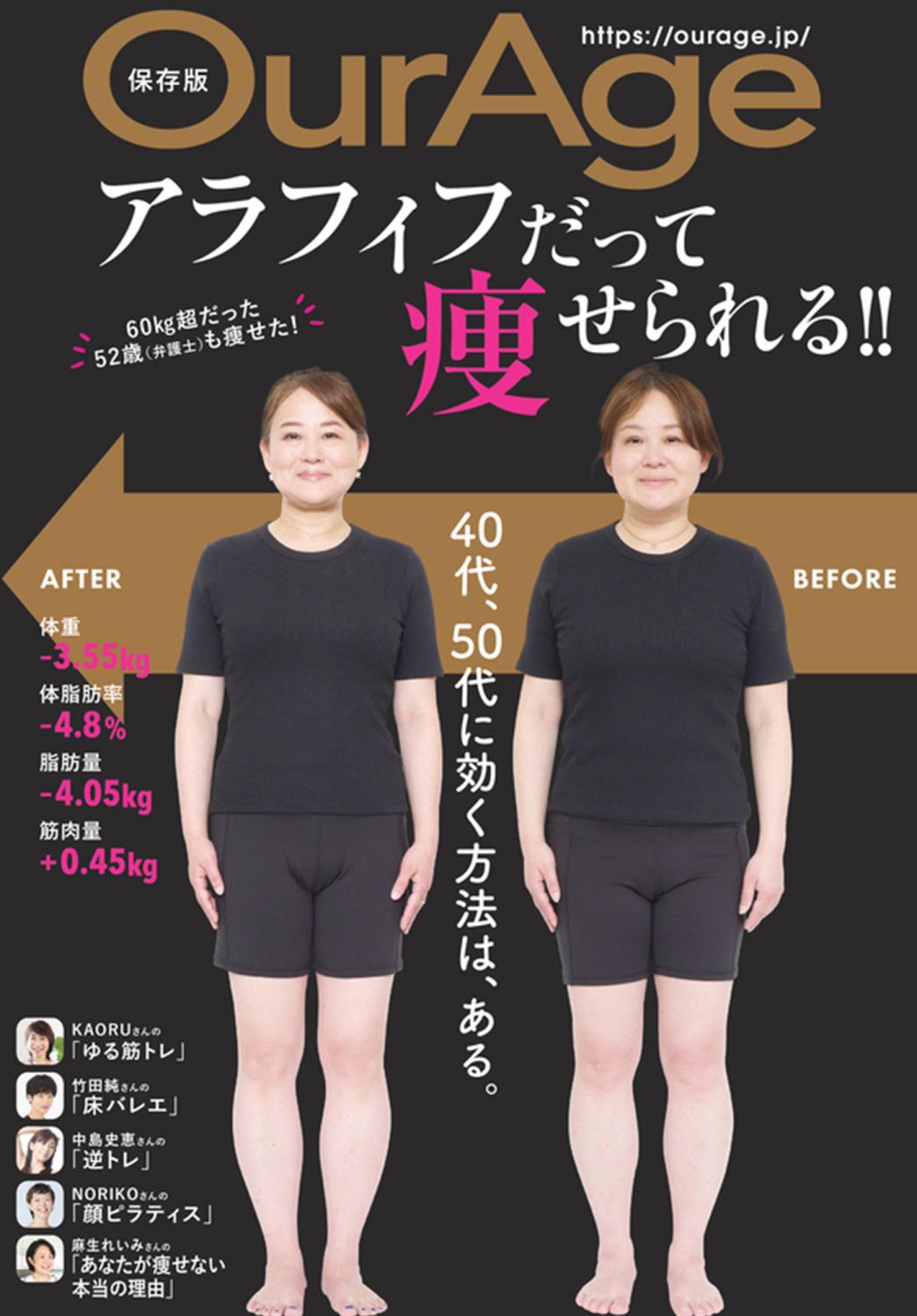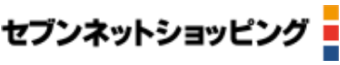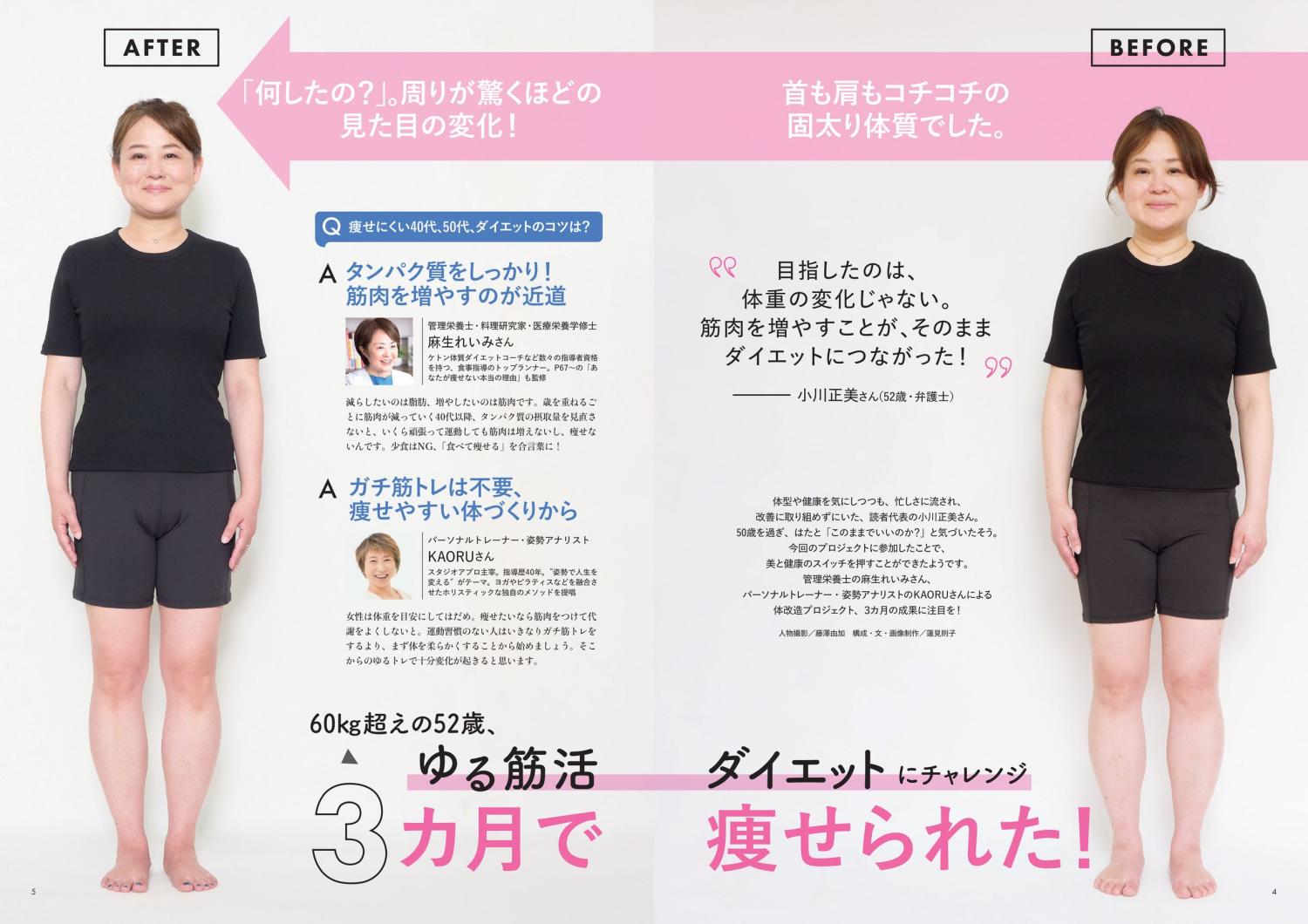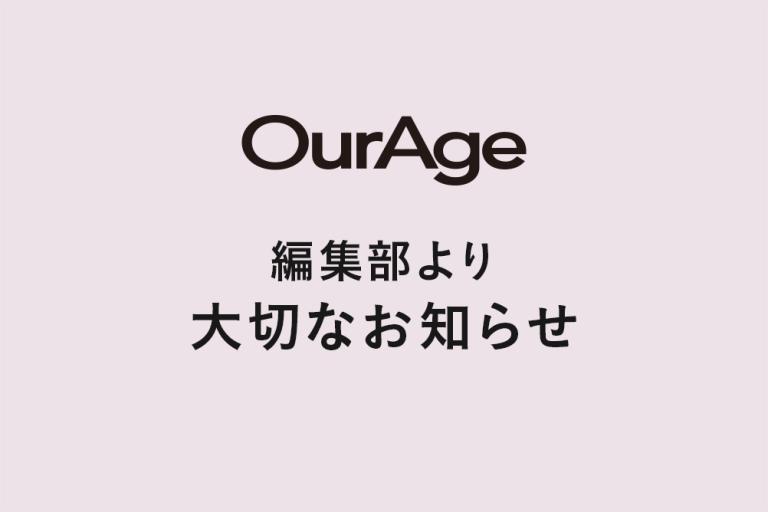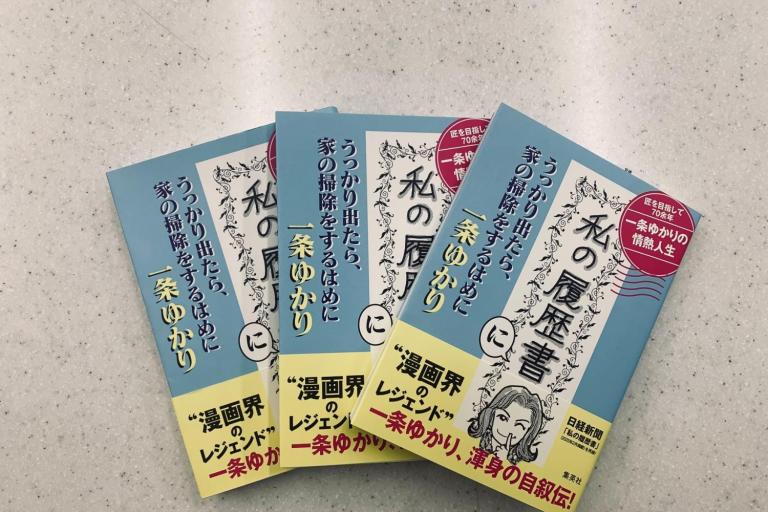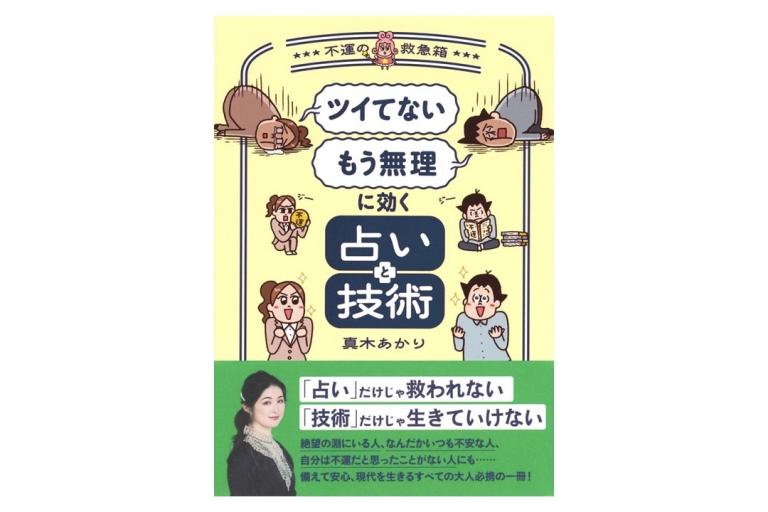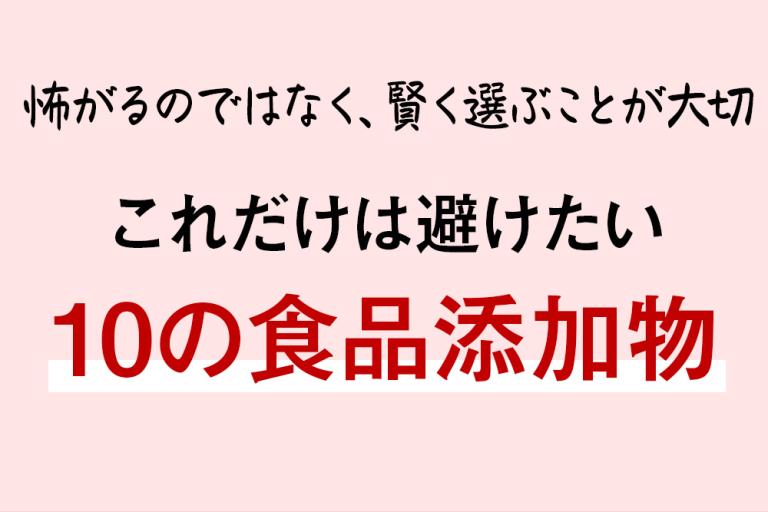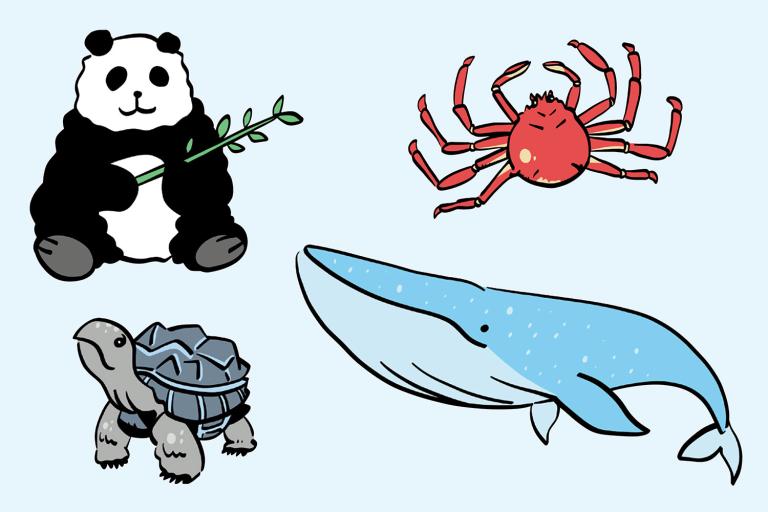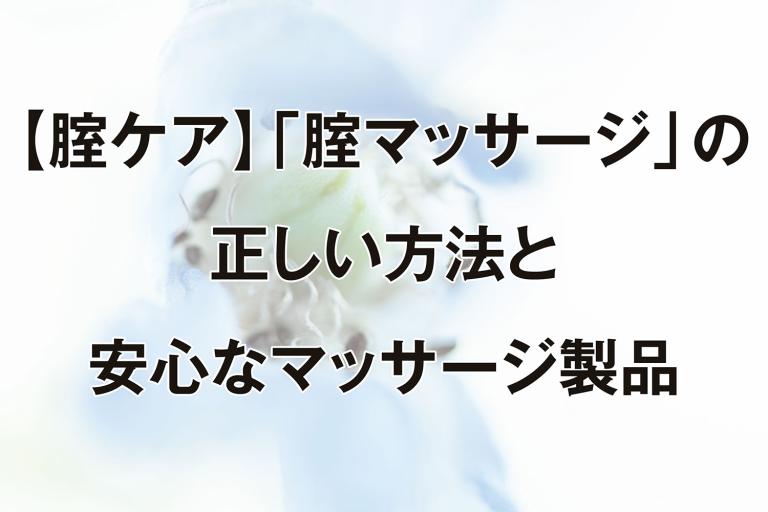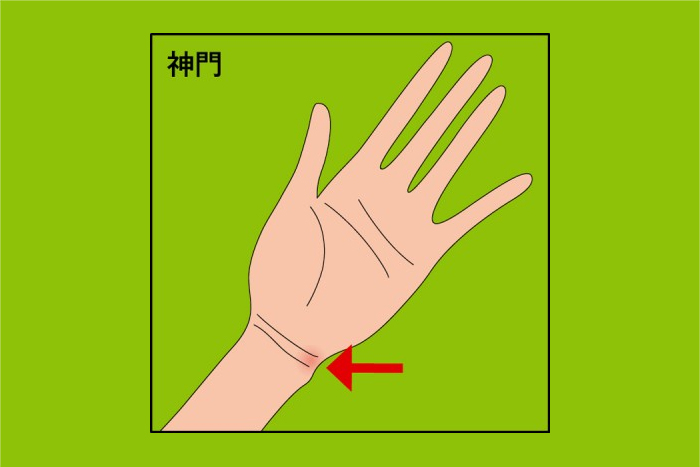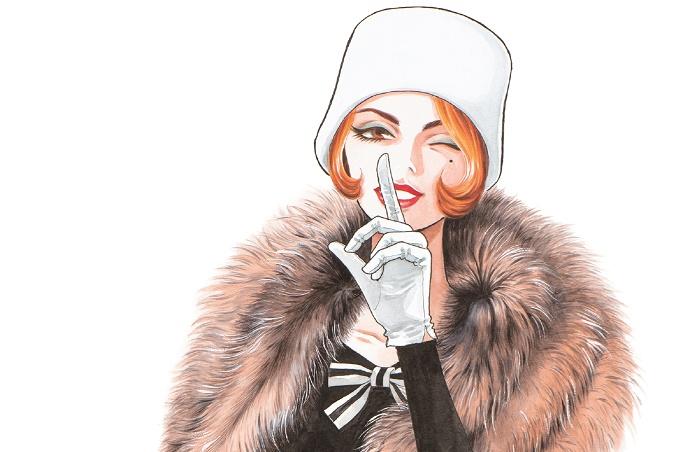夢だった漆喰(しっくい)壁。調湿性と心地いい空気に惹かれて決断
昨秋、自宅マンションをリノベしました。
22年前、新築マンションを軽くリノベしてから入居し、当時も今も夫とふたり暮らし。人員構成が変わらないのでスケルトンにして間取りを変えるような大規模リノベの希望はありませんでした。
ただ、壁を漆喰にしてみたかったのです。実は入居時にも漆喰壁を検討しましたが、工事に1か月以上かかると聞き断念。結局その時は石膏ボードにオフホワイトのペンキを塗る形で仕上げてもらいました。マットなペンキ壁の仕上がりも見た目には大満足でしたが、漆喰壁だとより空気が心地いいのだろうなあ、という憧れを密かに抱き続けておりました。
22年たって、室内のあちこちに傷みも出てきたので、細かい修理とともに、壁を漆喰にしてはどうだろうと思いたちました。
そもそも漆喰のメリットとデメリットとは?
リノベに当たり、改めて漆喰について調べてみました。ご存じの方も多いかもしれませんが、原料は消石灰(運動場に線をひく、あの粉です)です。元々はサンゴ礁が長い年月をかけて石灰石になり、石灰石を焼いて水を加えたものが消石灰とのことなので、完全な自然由来の素材です。
漆喰にひかれる理由・メリットは?
① 調湿性がある。
私が漆喰になによりひかれていたのは、調湿性です。夏の過度な湿気を吸い、冬の乾燥時には湿気を出して湿度を調節、部屋を快適に保ってくれるそう。
② 強アルカリ性なので、カビや細菌を防いでくれる。
カビや細菌、ダニがつきにくく、シックハウスの原因になるホルムアルデヒドを吸着する効果もあるそうです。
③ 防臭性がある。
壁が息をしているので、気になる臭いを吸い込みます。
④ 燃えにくい。
マンション火災のニュースを目にすることが増え、燃えにくさも気になる要素となりました。
⑤ 長持ちして、二酸化炭素を吸い続ける。
お城や塀、お蔵などを見てもわかる通り、漆喰壁は100年ぐらいもつ丈夫さがあり、その間、ずっと二酸化炭素を吸い続けるのだそうです。
これは、どう考えても、漆喰壁にすると室内の心地よさが増しそうではないですか!
またリノベ会社の方によると、漆喰の左官職人さんの高齢化が進み人手不足で、今後、漆喰壁がなかなか頼めなくなるかもしれないとのこと。もう、夢をかなえるなら今だ!と、心を決めました。
念のために、私が聞いたり体験した漆喰のデメリットも書いておきます。
漆喰壁のデメリット
① 最初は白い粉がつく。
完成当初は、服や布バッグなどが少しこすれるだけで、接触部分が白くなってびっくり。ただ、手ではたいたり洗えば簡単にとれました。しかも3か月ほどで、まったくつかなくなりました。
② 汚れがついたら消しゴムで
昔から外壁や塀にしてきたぐらいなので、基本的に丈夫だし汚れもつきにくいようです。ちょっとした指の跡を見つけた時には、消しゴムでこすったら消えました。ただ、お茶やコーヒーなど色の濃い水分がしみ込んでしまった場合は、メラミンスポンジや目の細かいサンドペーパーで薄く削り取るなどの対策が必要とのことです。
③ ピンが刺さらない。
以前の我が家の壁は石膏ボードの上にペンキを塗った仕上げだったので、目立たないピンを刺して額やかごなどを飾ることができました。その点、漆喰は堅牢でピンが刺せません。無理に刺すと周囲が削れてしまったり、ひび割れの原因になるということでやめました。
④ 地震でひび割れが起こる可能性も。
地震が起きたら、壁にひび割れが出る可能性があることは最初にリノベ会社の方から言われました。まあ、地震の被害はどんな壁にも(壁以外にも)起こりうるだろうからと考え、納得の上で依頼することにしました。
ついに漆喰壁の作業開始。漆喰の商品名はその名も「城かべ」!
まずは、作業の様子をお見せします。
壁のペンキを削り落として、石膏ボードを平にします。その後、黒っぽいシーラー(下地)を塗った段階が、この写真の壁の状態です(シーラーを塗る理由は後ほど)。天井には、すでに漆喰(1度目)が塗られています。作業台や足場などがたくさん持ち込まれ、たいへんな作業であることが見てとれます。

我が家の漆喰の商品名はその名も「城かべ」!

「城かべ」という名前に妄想が膨らみ「江戸城とか白鷺城と同じ漆喰だったりして?」と興奮しましたが、職人さんによると「単にそういうイメージで名前をつけただけでしょう」とのこと。調べたら、1度目の東京オリンピックが開催された1964年からある定番商品でした。
いやいや、でもこの「城かべ」製の漆喰壁の中でくつろいだり、寝たりしたら、気分はお殿様ですよ。(なぜか妄想するイメージは「姫」ではなく「殿」になる私!?)
記事が続きます
漆喰の色は「白」、塗り方は「こて押さえ仕上げ」に
ちなみにペンキの場合は、ひと口に「白」といっても少しほかの色を混ぜれば何百色でもバリエーションが作れますが、漆喰の白は1色だけ。かなりの真っ白です。完成後、最初はまぶしいと感じたほどでしたが、お城や酒蔵なども、元はこんな風だったかと想像すると、味わい深く思えます。
 職人さんのコテなどの道具類。もっとたくさんあって、場所によって使い分けておられました。
職人さんのコテなどの道具類。もっとたくさんあって、場所によって使い分けておられました。
 先ほどのシーラー(下地)を塗る理由ですが、コンクリートからは「アク」と呼ばれる汚れなどが染み出るそう。アクを抑える効果のある下塗り材であるシーラーは漆喰には不可欠なのだそうです。シーラーをしっかり塗った後に漆喰の左官作業に入ります。
先ほどのシーラー(下地)を塗る理由ですが、コンクリートからは「アク」と呼ばれる汚れなどが染み出るそう。アクを抑える効果のある下塗り材であるシーラーは漆喰には不可欠なのだそうです。シーラーをしっかり塗った後に漆喰の左官作業に入ります。
実は我が家の場合も、シーラー後に漆喰を塗って乾かしてみたら、なんとリビングの天井から黄色っぽいアクが出たそう! 結局天井は漆喰の大幅な塗り直しが必要だったとか。アクは、タバコをはじめ焼き肉の煙などでも付くのだそう。う~ん、うちは誰もタバコを吸わないし、リビングでの焼き肉も10年以上前に数回しかしていないのだけれど、その数回が原因? これは謎のままです。
ところで、漆喰壁を依頼するときに、リノベ会社の方に、マンションだと珪藻土も人気があると提案されました。珪藻土は、ザラザラぶつぶつした質感で私のイメージではやや和風テイスト。今までのペンキで塗った壁と同じような、白く滑らかな壁にしたい希望があったので、やはり漆喰にすることに。
また、近所のカフェや古本屋さんなどで若いオーナーさん自らが仲間と漆喰を塗っているのを見かけたりSNSでも見たりします。そういうDIYだったり、街の地中海レストランなどはあえて「こて」の跡をつけて塗って、味を出していますよね。
そういった一目で漆喰とわかる仕上げも魅力的ですが、私はお城や塀などに使われてきた昔ながらの手法「こて押さえ」仕上げという、職人さんの技術が必要なフラットな仕上げをお願いしました。
左官職人さんは二名で、作業は最初に一番大変な天井を完成させてから壁を。さらに細かい部分という順に進みました。塗って数日乾燥させてまた必要な部分を塗るというのを、繰り返しておられました。私やリノベ会社の方には違いの判らない「乾きの差」や「色の差」をチェックして追加の塗りを判断するのだそうです。まさに職人さんの目と技で完遂したといった表現がぴったりの美しい仕上がりで、おふたりには感謝の気持ちでいっぱいです。

右写真は、とくに凹凸のある部分を見つけて寄って撮影しましたが、なんとか漆喰とわかるでしょうか。
長年続いた結露との戦いに決着!? 二重窓にしたおかげか?それとも?
さて、漆喰壁の工事が終わって仮住まいから戻ってきたのが10月後半だったので、もう湿度は高くなく、調湿性に関しては当初、効果がよくわかりませんでした。
ところが! 2月になってハッとしました。
この冬、1回も窓に結露がついていない!
窓の結露って本当にいやですよね。
冷たい飲み物を入れたコップの外側に水滴がつくように、窓ガラスが外の空気で冷やされて、暖かい室内側に水滴がつく、ということだと思いますが、冬の朝、窓の内側が結露しがちなのです。
我が家の結露との戦いの歴史
1.2002~2015年【結露しっぱなし期】
家にある9つの窓のうち、5つの窓と、それとは別のガラスドア1つが冬の3か月間、毎朝、結露する。ほっておくとゴムパッキンがかびるので、拭かざるを得ない。とほほな日々。
2.2015年【結露対策スタート&挫折期】
結露する5つの窓のうち、3つを二重窓に。マンションではガラスの交換などはできないので、当時普及し始めた、マンションでも簡単に取りつけられる内窓を設置。工事も1日で終わり手軽です。
ただ期待むなしく、二重窓にした3つのうち、結露しなくなったのはキッチンの出窓ひとつだけ。リビングの窓ふたつと、キッチンのガラスドアは、相変わらず結露し放題。がっかり。
3.2024年~ 【瓢箪から駒で大成功期!】
家のほとんどの壁を漆喰に。また、入居当初から結露する北側の2部屋(寝室と荷物部屋)の窓にも内窓を付けて二重に。2015年にリビングに内窓を付けても結露が治まらなかったため、今回もあまり期待していなかったのだけれど…そういえばこの冬、1度も結露していない! ラッキー!?
 右写真が内窓を取り付け、窓を閉めたところ。左写真は内窓を開けたところです。手すりのバーの内側に、内窓が取り付けられているのがわかるでしょうか。
右写真が内窓を取り付け、窓を閉めたところ。左写真は内窓を開けたところです。手すりのバーの内側に、内窓が取り付けられているのがわかるでしょうか。
結露しない快適さ! これは体によいに違いない
冬中1度も結露しない日が来るとは! しかも、一番結露がひどかったのに、二重にできないキッチンドアまでも一切結露なしです。
今年の冬は乾燥していたからでは? という疑問は確かに残ります。
ただ、毎日料理はするしバスタブにお湯も張るので、室内の湿度はそれなりにある。しかも、今年の2月は特に寒い日が続き、室内外の気温差は大きかったはずです。
それらを踏まえて、実は心待ちにしていたのが雪。過去に雪の日に結露しなかったことは1度もないので、早く確認したかった。ついに来た3月の雪の日は、家じゅうのガラス窓を何度もパトロール。それでもやっぱり、結露しませんでした!
結露がなければ、タオルで拭く手間もいらないし、なにしろカビの発生に対する心の負担が一気に軽減します。
まさに、私にとって天国。ニーズにばっちり合致した結果がついに手に入りました!
今回北側の2部屋を二重窓にしたことも結露をなくすサポートになったとは思いますが、10年前に二重窓にしたリビングの窓まで初めて結露しなくなったのは、どう考えても漆喰壁のおかげです。
漆喰の実力おそるべし!
この快適さが、ずっと続きますように。
それでは、今回の「定年女子あるある(かもしれない)川柳」いかせていただきます。
「城かべ」が 夢叶えたり 殿気分
※今回の内窓取り付け工事の費用は2か所で約27万円でした。断熱性向上のリノベにはエコの補助があり、リノベ会社を通して補助金(約7万5000円)が出ました。私が受けたのは「先進的窓リノベ2024事業」です。
また、一定の条件を満たせば「マイホームの一般省エネ改修工事を行った」人が対象の税金の控除もあります。我が家は窓リノベを10年前と昨年の2回に分けてやったため、今回の費用が基準額の50万円に達しなくて対象外でした。窓リノベを計画した際には、そのあたりも調べてみてくださいね。