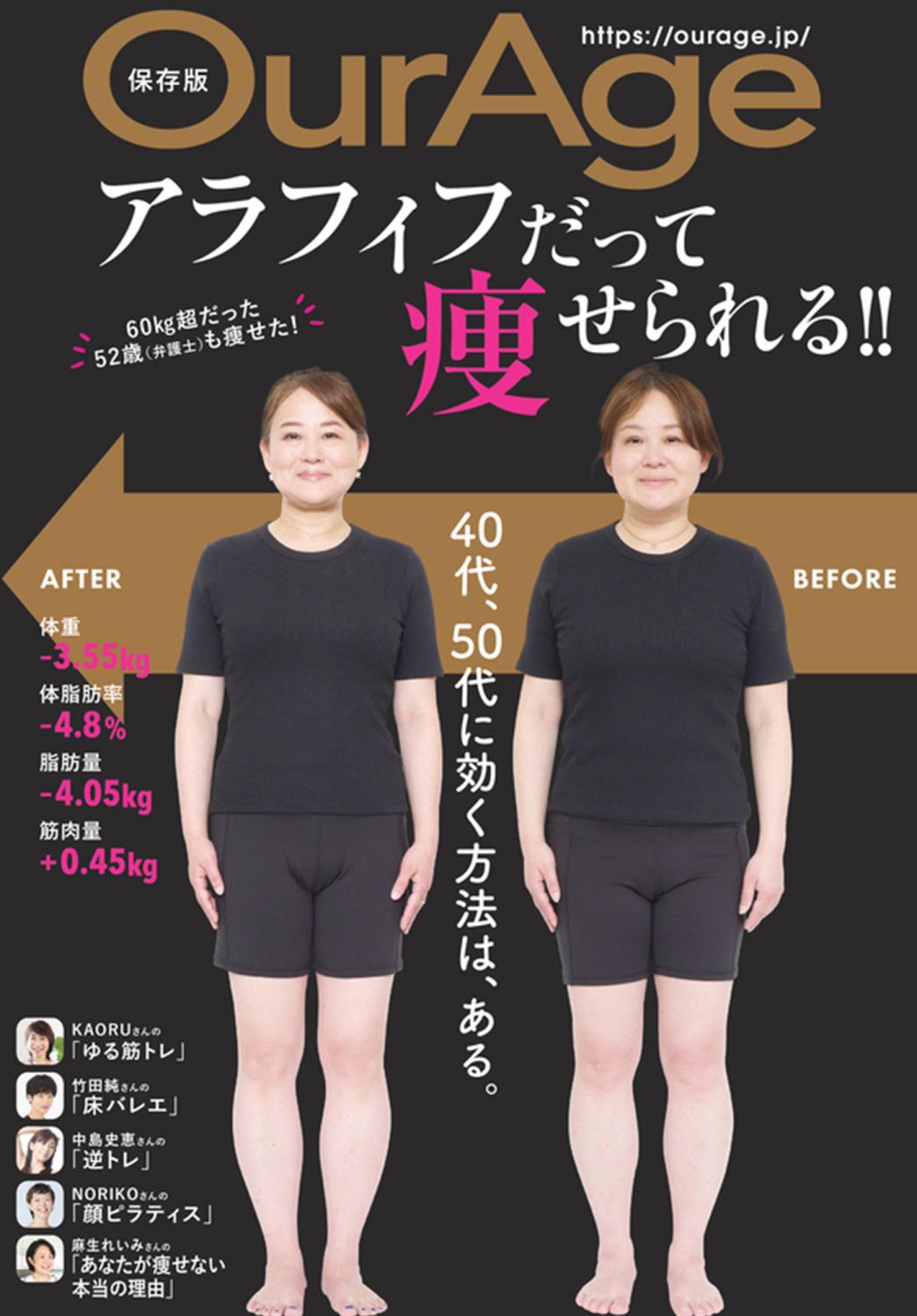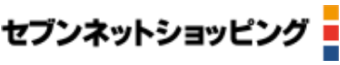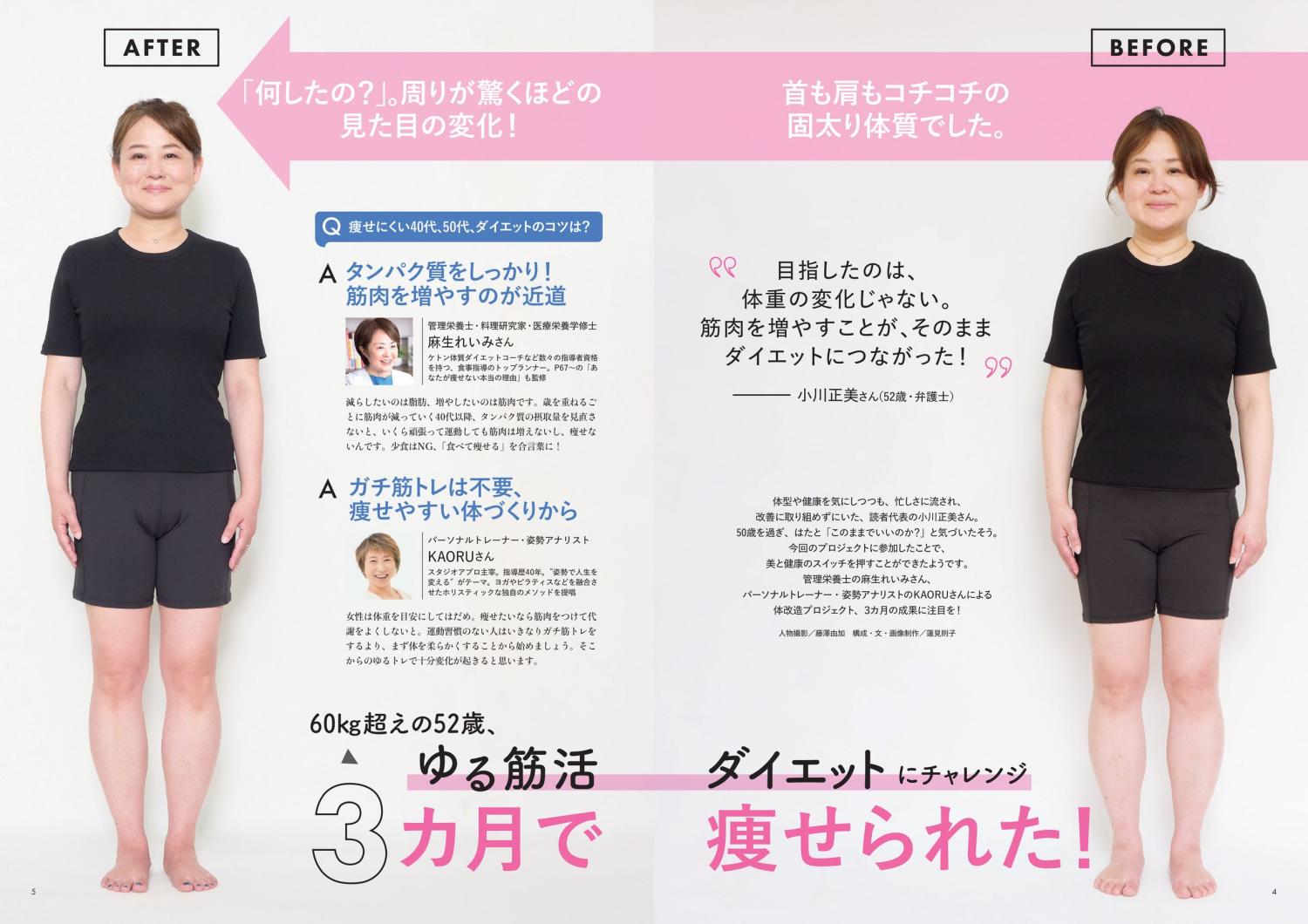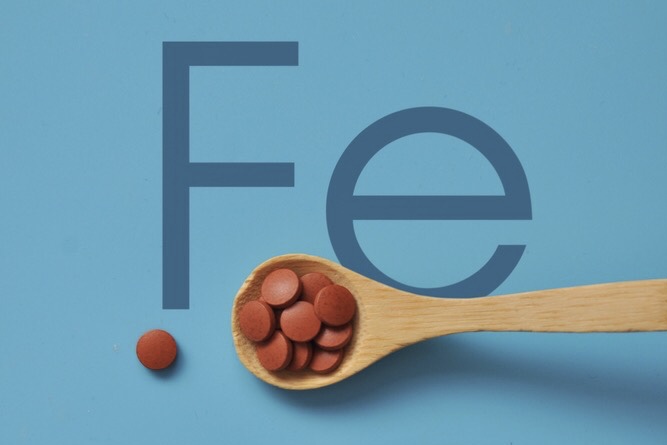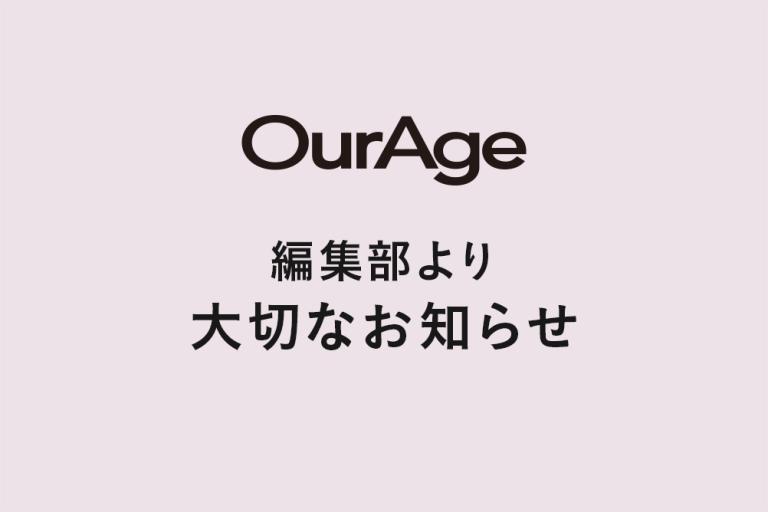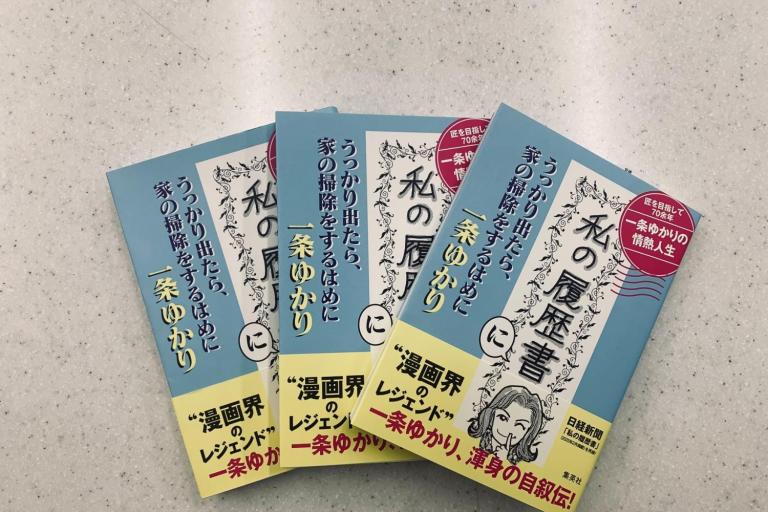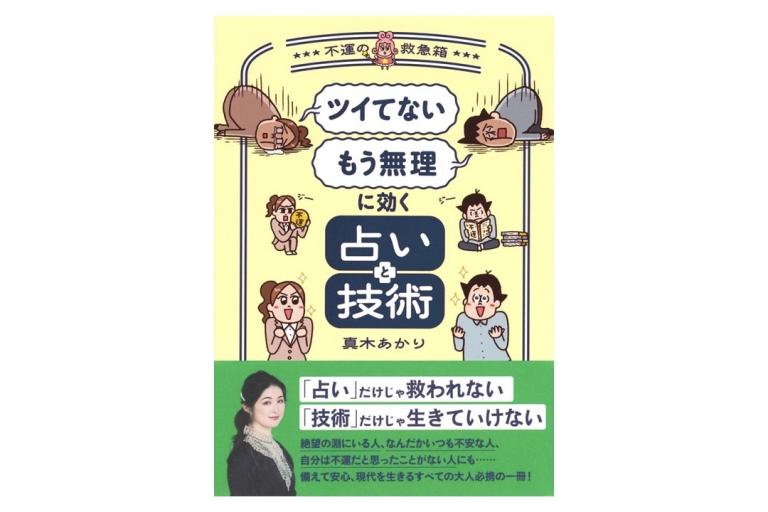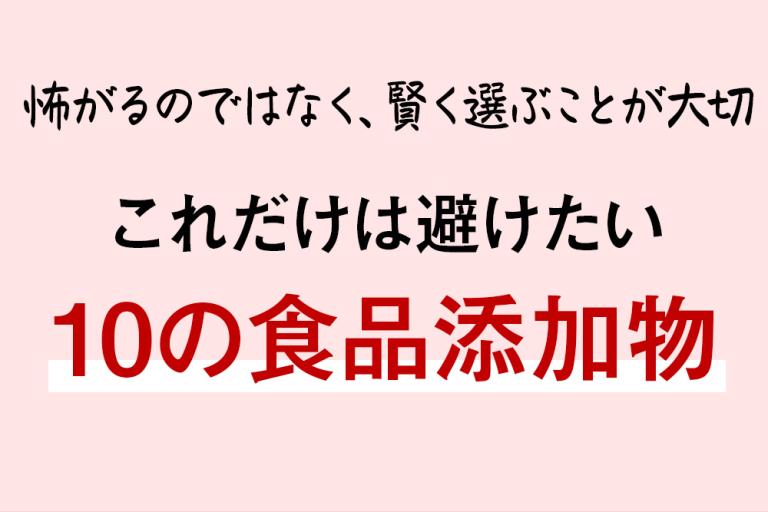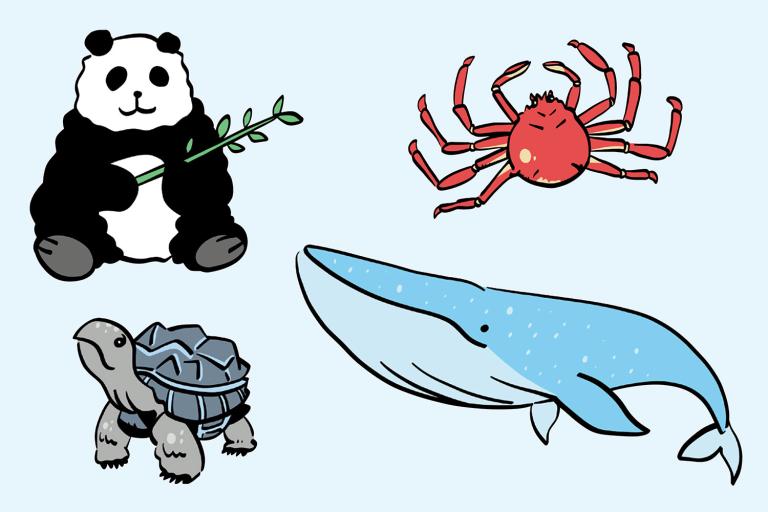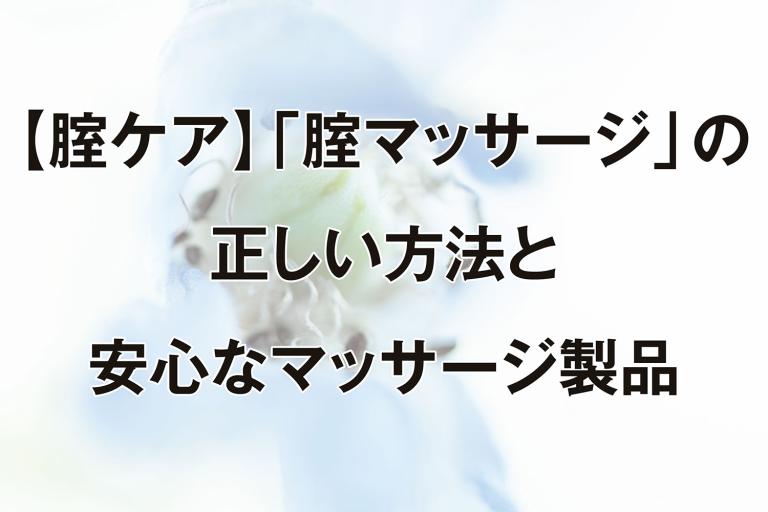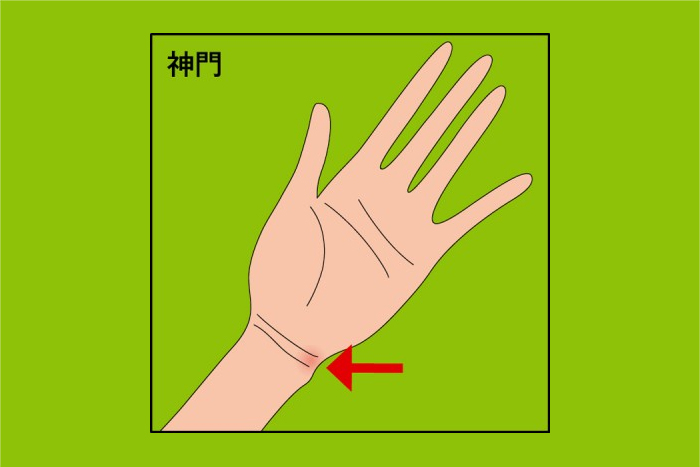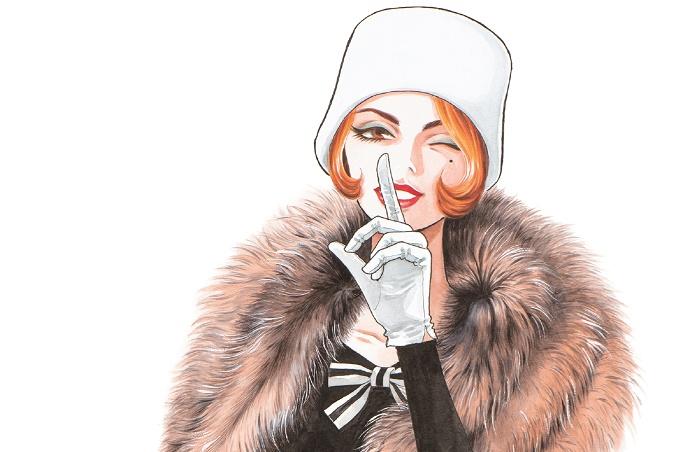特に意識してとりたい「ミネラル」は、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛の4つ。
骨、歯、皮膚、髪の健康維持や、筋肉・神経の調整、疲れやすさの改善などに欠かせません!
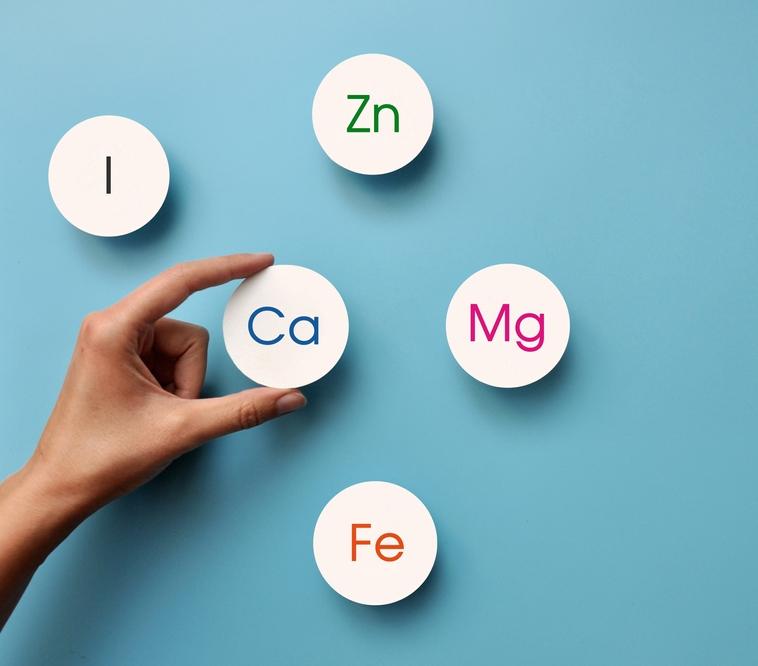
加工食品をとることが多い現代人の多くは、3大栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)は足りているけれど、ビタミンやミネラルが不足している“新型栄養失調”の人が多数。
そのため、サプリメントを取り入れるなら、まずとるべきなのはビタミンやミネラルであるという話を、この連載の第1回~第4回で紹介しました。
今回は、そのうちの「ミネラル」のとり方について、医師の林巧先生に伺いました。
「ミネラルは、ビタミンと同じく不足しやすい栄養素。
特に意識してとりたいのがカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛の4つです。
それぞれ、ほかのミネラルとのバランスを考えてとるなど、とり方にコツがあるので覚えておきましょう」(林先生)
重視したい4つのミネラルのうち、ここでは、「カルシウム」と「マグネシウム」について詳しく紹介します。
1)カルシウム
骨や歯を健康に保つために、欠かせないミネラルです
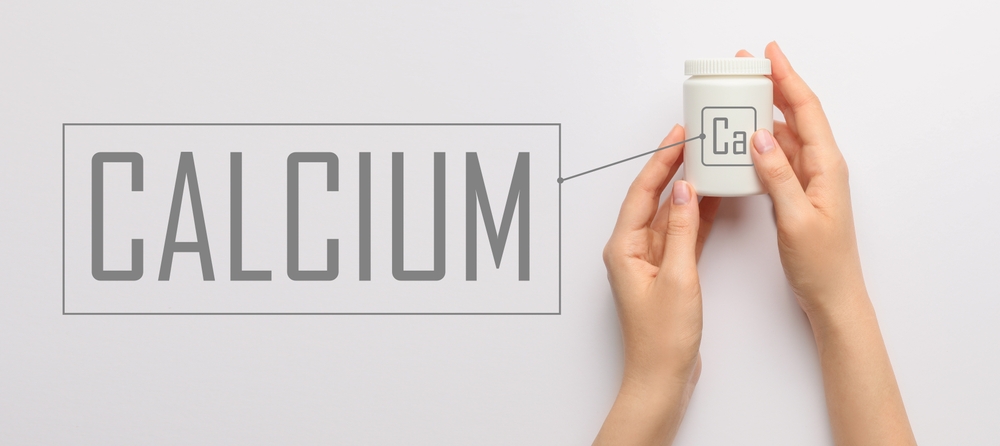
「カルシウムは、体重の約1~2%(体重50kgの成人で約500g~1kg)と、ヒトの生体内に最も多く存在するミネラルです。
カルシウムの主な働きは、まず、骨密度の維持と骨粗しょう症予防です。
女性は、閉経後に女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌がなくなると、骨粗しょう症になりやすくなるので、カルシウムの摂取は、40代、50代の女性にとってとても重要です。
筋肉や神経の正常な機能を維持する働きや、心血管の健康の維持、心拍リズムの調節などの働きもあります。
また、カルシウムは、歯の象牙質の主成分であり、エナメル質の再石灰化にも関与するので、健康な歯の維持にも欠かせません。
再石灰化とは、唾液に含まれるリン酸イオンやカルシウムイオンが、歯に取り込まれて失われた部分に再び補充され、自然な修復が行われることです。
そのほか、血液を凝固させて出血を抑える作用にも関与するなど、体内で重要な働きをしています」
記事が続きます
カルシウムのとり方のポイント
「一度にまとめてたくさんとると体外に排出されてしまうので、朝・昼・夜と3回に分けるなど、こまめにとるのが効果的。
一日にとる量は、パッケージに記載された量を目安にとりましょう。
それから、カルシウムはマグネシウムとセットでとることがポイントです。
どちらかをとりすぎると、一方がうまく働かなくなってしまうからです。
とるときの比率は、以前はカルシウムとマグネシウムの割合は2:1がよいといわれていましたが、最近は1:1がよいといわれています。
カルシウムとマグネシウムが一緒に配合されているサプリメントも多いので、そういったものを選ぶと手軽にとることができます。
これもパッケージに記載された量を守ってとりましょう。
食品では、小魚、桜エビ、木綿豆腐や納豆などの大豆製品、小松菜、青梗菜、ひじき、乳製品などに多く含まれています」
2)マグネシウム
骨の健康維持、筋肉と神経の調整、血圧の調節など、重要な働きがあります

「マグネシウムは、人体のすべての細胞に広く分布するミネラルで、体内で300種類以上の酵素反応に関与しているため、さまざまな働きがあります」
ひとつが骨の健康維持。
「マグネシウムは、カルシウムとともに骨の形成に関与していて、体内のマグネシウムの約50~60%は骨に存在し、適切なレベルを維持することで骨密度の低下を防ぎます」
もうひとつの働きが、筋肉と神経の調整
「マグネシウムは筋肉の弛緩に重要な役割を果たしていて、不足すると筋肉のけいれんやこむら返りが起きやすくなります。
また、神経系の正常な働きの維持にも関与しているので、不足すると神経過敏やストレス反応を増やす可能性があります。
そのほか、血圧を調節して心血管系の機能を維持する働きや、インスリンの働きを助けて血糖値を安定させる働き、大腸内での水分調節を助けて便通をよくする働きも。
神経の鎮静作用を持つため、リラックスや睡眠の質の向上にも役立ちます」
記事が続きます
マグネシウムのとり方
「上のカルシウムのパートでお話ししたように、1:1のバランスでとることです。
とる量はパッケージに書かれている量を目安にとりましょう。
食品では、そば、海苔やひじき、わかめなどの海藻、納豆、豆腐、ごま、魚、牡蠣、とうもろこし、バナナ、ココアなどに含まれています」
【終わりに】
いかがでしたか?
思っていた以上に重要で多岐にわたる働きをしていることに、驚いた人も多いのではないでしょうか?
健康維持や、私たちの体が正常に機能するために欠かせない「カルシウム」や「マグネシウム」。
効果的な方法で意識してとりたい栄養素ですね。
毎日の食事でミネラルが多い食品を取り入れながら、サプリメントもうまく活用して健康を維持しましょう。
【教えていただいた方】

はやしたくみ女性クリニック院長、医師。1966年、北海道札幌市生まれ 。札幌医科大学卒業。札幌医科大学附属病院では更年期専門外来を担当。斗南病院、函館五稜郭病院、NTT東日本札幌病院を経て、2009年「はやしたくみ女性クリニック」を開業。 日本産婦人科学会専門医、日本女性医学学会(旧日本更年期医学会)女性ヘルスケア専門医、日本女性心身医学会認定医、日本抗加齢医学会専門医、日本骨粗鬆症学会認定医、日本性差医学・医療学会認定医などを取得。産婦人科、女性内科、性差医療の視点から保険診療、保険外診療の両面で、その人その人に合ったケアを行い、女性のこころとからだの健康をサポートしている。
写真/Shutterstock〈イメージカット〉 取材・文/和田美穂