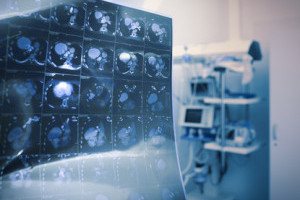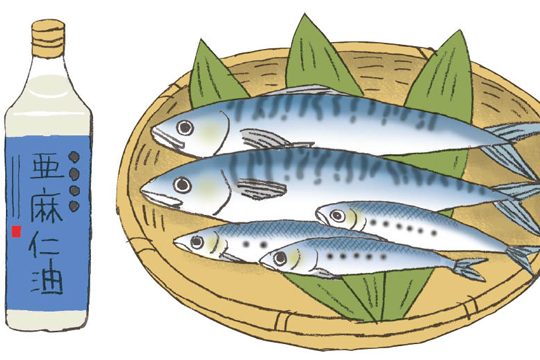この手術(前回参照)を受けるために、一週間は入院しなければならないそうだ。そのことを家族や最小限の友人、仕事先に告げ、急ぎの仕事を片づけ、病院から指定された前開きのネグリジェなど、一生着そうもない入院グッズを買いそろえるなど、師走のような忙しさで、ばたばたと用意をしているうちに、あっという間に手術前日になった。
留守を預かる長男が、わたしのからだを心配しているようだった。こわがらせて気の毒だが、彼には麻酔などで万一のことがあったときの緊急連絡先をいくつか告げ、昏睡状態になったときには延命措置をしないようにと念を押した。「うまくいくよ。頑張って」と送り出されたので、「わかった、わかった」と明るく家を出た。
この病院に初めて来たときには軽いカルチャーショックを受けた。

ラベンダー色に統一された室内の壁紙には小花模様があしらわれ、そこはかとなくバラの香りが漂っている。BGMにはオルゴール。かなりファンシーである。卵巣嚢腫摘出に乙女心はいらないのだが、若い妊婦さんには必要なのだろう。
昔、息子を生んだのは、お化けが出そうなほど古い市民病院だったので、わたしは、なんだか落ち着かずに、きょろきょろしてしまった。今の産婦人科は、こうなっているのか。
寝巻に着替え、荷物を部屋に収納し、すっかりくつろいでいると、夕方遅くに看護師がやって来て、手術に必要だからと、「へそのゴマ」を綿棒で取り除きはじめた。「何か気になることがありますか?」と聞かれたので、「そういえば」と、疑問に思っていることを聞いてみることにした。
「もともとは貧血で受診したんですが、薬も処方されずじまいで、今日になってしまいました。貧血も治してくれるんですよね」
すると看護師は、にわかに心配そうな顔をして、「じゃあ、採血しておきましょう」と、へそのゴマ除去もそこそこに、血を取ってどこかへ行ってしまった。そしてとっぷり暮れたころ、医師がわたしの部屋を訪ねてきた。
「いやあ、佐々さん、貧血が思ったよりひどいですねえ。これだと出血をしたとき、輸血のリスクが伴いますので、明日の手術は中止しましょう。お薬を飲んで貧血がよくなるか、様子をみてください」
しばらく、言葉の意味が呑み込めずにぼおっとしてしまった。あまりの衝撃的な事実に言葉を失ったのだ。
そうか、わたしはメスが入れられないほど、具合が悪いのか……。
いや、しかし待ってほしい。わたしはそもそも、医者も驚くほどのひどい貧血持ちだから受診したのだ。貧血のための薬をもらいたい一心で受診したといってもいい。
しかし、手術が決まってからは、乳がん検診などの、今回の手術とは関係のない検査は受けさせられたが、血液検査はついに一度もされなかったし、貧血の薬も処方されなかった。手術前に貧血の薬を飲んで体調をコントロールする時間はあったはずだし、できなかったとしても、入院してパジャマに着替え、へそのゴマまで取る前に、ちょっと検査すればわかるはずだ。
もし、わたしが貧血について尋ねなかったら、検査もされず、そのまま手術していたのだろう。
〈これってひょっとしてウッカリ?〉
わたしが来院した理由を忘れていたのか、それとも、うまく伝わらなかったのだろうか。わたしは重度のウッカリ者なので、他人のウッカリには共感してしまうところがある。医師は卵巣嚢腫の発見で、わたしの困りごとをすっかり忘れてしまったのだろう。わたしからみれば、卵巣は自分のからだのごく一部でしかないのだが、医師にとっては卵巣に、からだがくっついているようなものなのだ。
よく「医師は人間全体を診なければならない」と、自戒をこめて書いてある本を見かける。しかし、産婦人科の混雑ぶりを見れば、患部に向き合うのが精いっぱいで、医師が人間としての患者と向き合うなんて、どう考えても限界があるのがわかる。
毎日毎日、医師は卵巣を診ている。若い卵巣、年老いた卵巣、大きな卵巣、小さな卵巣。そのひとつ、ひとつにどんなヒストリーがあるかなど、わかるはずがないのだ。
わたしはどこかで、治療はフルコースで医師にすべてお任せで、余計な口をはまさなくても、自動的にすっかり治してくれると信じ込んでいた。診察室で医師の前に座れば、あとはぴったりの治療法を見つけてくれるものだと、どこかで甘えていた。

わたしの人生の舵を握るのは、ただひとり、わたしだけなのだ。貧血はどうするのか、卵巣嚢腫が見つかって以来どこかでずっとひっかかっていたのに人任せにしていたのがいけない。ちゃんと医師とコミュニケーションを取りながら、ひとつひとつ確認していく必要があったのだ。
あまり愉快な経験ではなかったが、腹を開いてから「あ、この人血が薄い!」と気づかれなくてよかった。だから手術の延期を決めてくれたのは正解だ。正直なお医者さんでよかったと思う。
わたしはのろのろと服を着替えると、部屋に広げた荷物をまとめて、来た道をとぼとぼ戻った。
息子が会社から戻ってきたので出迎えると、「うわああっ」と幽霊を見たかのように驚かれた。それはそうだろう。万が一のことを言い残して入院したはずの母親が家でぼーっと立っているのだ。顛末を話すと、彼は眉をひそめて、「それさあ、もう一度ほかの医者で診てもらったら?」と言って黙ってしまった。
手術前のわたしは異常なほどのハイテンションだった。きっと、来るべき開腹手術に備えてアドレナリンが噴き出していたのだろう。それが、いきなり手術中止となってわたしは気持ちのやり場に困った。困難に立ち向かうほうが、なにもできないよりよほど楽だ。入院するために空けておいたスケジュールは一週間空っぽだ。
しかし、他人の人生を書かせてもらえるほどのエネルギーがどうしてもわかない。文章に力がこもらないのだ。仕事でお世話になっている編集者や取材を受けてくださった方々に心で詫びながら、ゴロゴロして過ごしているうちに、気持ちは急降下し、欝々とした気分になった。
一週間単位での入院スケジュールを再び組むのもおっくうだし、別の医者に行って最初から、婦人科特有の愉快じゃない検査を一からするのも耐えがたい。
ぜんぜん元気が出ない。
でも、「これはほかの医者にも、かかってみよというお告げなのでは?」というささやき声がどこかから聞こえてくる。こんなときにすらライター根性が顔を出す。思いもかけないアクシデントが降りかかると、「これからどうなるのだろう」とちょっと興奮してしまうのだ。つくづく因果な商売である。